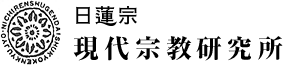現代宗教研究第44号 2010年03月 発行
『立正安国論』考
研究ノート
『立正安国論』考
岩 田 親 靜
はじめに
昨年、現代宗教研究所の例会で拙者は「『守護国家論』考」と題して発表をさせていただく機会を得た。本発表はその続編となるものである。先の発表では、政治と宗教の関係は、論じることはなかった。また、浄土教批判に限ってではあるが、教学的には「守護国家論」にくらべ「立正安国論」には問題があると述べた。それに対して、なぜ日蓮聖人は「立正安国論」に加筆を加える形を取ったのか?抜本的書き換えを行わなかった理由は何なのか?という趣旨の質問もあった。そのことに答えつつ、十三世紀に北条時頼に上呈された『立正安国論』の精神をどう受け止め、現代に生かすべきなのかを模索してみたい。
一、『立正安国論』(文応本)
旅客来りて嘆いて曰く、近年より近日に至るまで、天変・地夭・飢饉・疫癘、遍く天下に満ち、広く地上に迸る。牛馬瓜に斃れ、骸骨路に充てり。死を招くの輩、すでに大半に超え、これを悲しまざるの族、あえて一人もなし。
右は言うまでもなく『立正安国論』(以下『『安国論』と省略』の冒頭であり、現世が当に地獄の様相であることを示している。この文章から日蓮聖人は災難の原因を探り始め、謗法である法然浄土教の存在を問題であると指摘する。また法然浄土教を止めない為政者に『仁王経』・『涅槃経』を引用し正法帰依する必要を促すのである。従来、右の『安国論』の構造・思考は日蓮特有のものと考えられてきた。しかし近年、末木文美士博士の指摘によりこの点は修正されるべきものに変わってきた。
邪法の流行が国家の厄災を招くので取り締まるべきだという論法も、必ずしも日蓮だけの特有なことではなかった。例えば、『立正安国論』よりは遅れるが、真言宗の心定という僧に『受法用心集』(一二七〇)という著作がある。(中略)邪法とは立川流のことであるが、『立正安国論』で日蓮が展開しているのとほとんど同じ議論を展開している。心定が『立正安国論』を読んでいたとは思われないので、同時代にある程度流布していた考え方であったのだろう。(末木文美士『仏典をよむ 死からはじまる仏教史』新潮社 二〇〇九 二七四・二七五頁)
「同時代にある程度流布していた考え方」だとするならば、『立正安国論』の問題は、末木博士が指摘するように「一介の無名の僧侶が堂々と政治論を政権の中核にいる政治家に提出した」事実であったのだろう。『安国論』は宿屋入道を通じて前執権北条時頼に上呈された。これは日蓮聖人が北条時頼こそが為政者と考えていたからであろう。時頼は佐々木馨博士の研究によれば、真言密教と臨済禅を重視していたのであり、現実に自身は禅僧蘭渓道隆を師として仏門に入っているのである。必ずしも法然浄土教を肯定的に見ていたわけではない。しかし、結果として日蓮聖人は弾圧を受けることとなった。
かつて権門寺院から異端として排撃され続けてきた専修念仏も、日蓮の時代にはすでに旧仏教との和解を実現し、幕府権力と結び付いて体制仏教化していた。それゆえ、鎌倉幕府に対する日蓮の『立正安国論』提出という行動は、同時代の政治的・宗教的権威に対して、ともに挑戦状をたたきつけたことを意味した。激しい反発は当然予想された。しかし、日蓮は身命を惜しまず信念を貫く実践こそが、仏から授けられた聖なる使命であると確信していたのである。(佐藤弘夫『日蓮「立正安国論」』講談社 二〇〇八 四九頁)
右は佐藤弘夫『日蓮「立正安国論」』の中の文章である。ここでは「同時代の政治的・宗教的権威に対して、ともに挑戦状をたたきつけたこと」としている。しかし拙者は「『守護国家論』考」でも触れたが、『安国論』の思想から考えれば、弾圧回避を考えていたと思われる。また当時の鎌倉の浄土教にとって『選択集』を批判されることそのものは問題ではなかったと考えられる。そのことは末木文美士『仏典をよむ 死からはじまる仏教史』でも指摘されている。
まず、法然批判という点を考えてみよう。(中略)しかし、法然が念仏を説いたところからもう半世紀以上経っていて、日蓮当時の厄災の原因としては、やや時代が離れすぎている。当時確かに法然の孫弟子の良忠らが積極的に鎌倉で布教を展開していたものの、彼らはむしろ他の流派と協調主義を取り、決して日蓮が言うような『法華経』を誹謗する態度は取っていない。それに、念仏が盛行していたのでない。今さら災害の源として法然を取り上げる日蓮の批判は、いささか時代錯誤でピントが外れている感じが否めない。(末木文美士『仏典をよむ 死からはじまる仏教史』新潮社 二〇〇九 二七八頁)
高木豊「立正安国論再読」では次のように述べている。
専修念仏者法然房源空の弟子長西の弟子で諸行本願義と呼ばれる立場にあった道教房念空が鎌倉仏教のリーダーとして鎌倉名越の新善光寺を拠点にして活躍しています。鎌倉での当面の批判の対象が、念仏であったのですから、当然この念空をリーダーとする念仏者との対決が、日常的に展開していたと考えなければならないでしょう。『立正安国論』を書いてから念空らとの対決が始まったのでなく、念空らとの対決の続いているなかで『立正安国論』が書かれたと言うことを無視すると同書のなかで解き難い問題があり、それが『立正安国論』の提出のいとであったという事を迂闊にも見落としていたのではないかという反省が、今老生にはあります。(髙木豊「立正安国論再読」福神 第一号 九一頁)
高木博士は末木博士の「今さら災害の源として法然を取り上げる日蓮の批判は、いささか時代錯誤でピントが外れている感じが否めない。」のような批判を推測し、右のように「念空らとの対決の続いているなかで『立正安国論』が書かれた」としているのではないか。しかし『安国論』以前の遺文で良忠・念空の存在にふれているものはない。むしろ高木博士は「解き難い問題」を無理矢理、解決しようとしたのではないか。
末木博士の当時の鎌倉では「念仏が盛行していたのでない」との指摘から考えれば、日蓮聖人は専修念仏批判そのものが弾圧につながるとは考えていなかったのではないだろうか。佐々木馨博士の指摘「予想だにしない弾圧を加えられた」と考えていたのではないだろうか。
弾圧の理由は他にあると考えるべきであろう。この点で佐々木博士は鎌倉幕府が山門派(叡山)を否定し、寺門派(三井)を肯定したことを述べ、幕府が日蓮聖人を山門派と見なしていたとしている。また末木博士は『安国論』の上呈を「前代未聞、驚天動地のこと」と指摘しており、思想が問題になったのでなく、行動が問題になったのではないかということを暗に示している。
日蓮聖人は『安国論』を上呈する相手を北条時頼とした。これは、実際の社会・政治を実状に合わせて認識していたことを意味している。一方で法然浄土教批判は、末木博士の指摘ではないが「いささか時代錯誤でピントが外れている」すなわち実状にあっていない。しかし、宗教家が政治状況を正確に把握していながら、専門と言ってよい宗教界の動向、それも鎌倉という限られた空間での動向を理解していないなどということが、本当にあり得るのだろうか。
むしろ、日蓮聖人は法然浄土教批判が「時代錯誤でピントが外れている」ことは理解していたのではないだろうか。法然浄土教批判であれば、為政者の共感を得られやすいと考えたのではないだろうか。批判するべきものを批判し、為政者の信頼を受ける。その上で、法華経の精神に基づく政治を求めるという方法を考えたのではないだろうか。(と考えれば、『安国論』は目的を指し示しているが、方法・手段の一つでしかない。)
この点は『安国論』の結論と言われる左記の文章の解釈においても重要である。
汝早く信仰の寸心を改めて、速かに実乗の一善に帰せよ。しかればすなわち三界は皆仏国なり。仏国それ衰えんや。十方は悉く宝土なり。宝土何ぞ壊れんや。国に衰微なく、土は破壊なくんば、身はこれ安全にして、心はこれ禅定ならん。この詞、この言、信ずべく崇むべし。
先にふれたように『安国論』を上呈した相手は前の執権北条時頼である。汝が北条時頼とするならば、為政者が実乗の一善に帰すことで、三界は仏国、十方は宝土となり、国土は安穏に成るのであるから、『安国論』の目的は達成される。身が安全になることや、心が禅定に入るのは結果として表れるものであって副次的効果でしかない。故に「心はこれ禅定ならん」の表現は時頼の信仰を意識したものであったかもしれない。(この点については浜島典彦「『立正安国論』の受け止め方」(『大法輪』二〇〇九 第七十六巻第八号 一一三頁)にも指摘されている。)
また、この文章は従来の仏教思想から考えると著しく異なるものであり、日蓮聖人の思想の特徴とも言える箇所でもある。
奉仕をするかどうかということは、結局、心の問題です。
「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行なったりするならば、苦しみはその人につき従う。─車をひく(牛)の足跡に車輪がついて行くように。
ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも清らかな心で話したり行なったりするならば、福楽はその人につき従う。─影がそのからだから離れないように。」(『ダンマパダ』)
この趣意は、心のあり方によって、世のすがたが、すっかり変わって見えてくる。そうして心のあり方によって万事がかわっていく、ということを述べております。(中略)
この世の中を、地獄にするのも、極楽にしてくれるのも、ただ心一つであると言えましょう。(中村元『仏典のことば 現代に呼びかける知恵』岩波書店 二〇〇四 二〇一・二〇二頁)
右は中村元博士の晩年の作品『仏典のことば 現代に呼びかける知恵』の文章であるが、ここでは心のあり方を変えることで現象世界の認識が変わっていくことを述べている。『安国論』も表現だけみると右の「心のあり方を変える」に似ている。しかし「汝」が為政者(北条時頼)を指すことに注目すると、見方がかわってこよう。為政者の「心のあり方を変える」ことで現象世界の「認識」を変えるのではなく、現象世界「そのもの」を変えようとしたのでではないだろうか。
『ダンマパダ』が個人の心を問題としているのに対し、『安国論』は「死を招くの輩、すでに大半に超え、これを悲しまざるの族、あえて一人もなし。」と多くの人々の苦しみを問題としているのである。この根底には言うまでもないことだが、民衆の苦しみを救いたいという「慈悲」の精神がある。『立正安国論』の上呈は、日蓮聖人にとっての慈悲行・利他行に他ならなかったと考えられる。
二、広本との相違
次に、弾圧を受けることとなった『安国論』(文応元年 文応本)と後に書かれた広本の関連について考察してみよう。(広本に関しては、中尾堯文博士により京都本國寺に所蔵されていたものが、真筆本でないことが発表されている(中尾堯文「『立正安国論』の思想」(東京都西部教化センター主催 連続講座記録「『立正安国論』をいかに読むか」 一七五頁下))。だからといって真跡本でないと断定されたわけではない。ここでは真跡本と考え比較する。)
ここでは広本の特徴的な五点を上げてみたい。(なお広本の本文を《 》で括って示した。)
① 愛国心の表明
天照太神・正八幡は我が国の神、文応本ではその国と表現したものが、「我が国・この地」になっている。
諸仏・諸経《・法華経の教主釈尊》・諸菩薩・諸天《・天照太神・正八幡》等をもつて、捨閉閣賀《の悪言》に載す。
その国を侵逼し《我が国を侵し》、自界叛逆してその地《この地》を掠領せば、あに驚かざらんや、あに騒がざらんや。
② 法華経重視の明確化
○真言と法華の勝劣が加わる。「一乗の元意を開発せん」が加わる。
法水の浅深《顕密の浅深》を斟酌し、《真言・法華の勝劣を分別し》、仏家の棟梁を崇重せん《一乗の元意を開発せん》。
○三説超過と法華最勝
その上、《法華経に云く、「薬王、今汝に告ぐ、我が所説の諸経、しかもこの経の中において法華最も第一なり」と。また云く、「我が所説の経典無量千万億にして、已に説き今説き当に説かん。しかもその中においてこの法華経最もこれ難信難解なり」と。また云く、「文殊師利、この法華経は諸仏如来の秘密の蔵なり。諸経の中において最もその上にあり」と。また云く、「衆山の中に須弥山これ第一なり。衆星の中に月天子最もこれ第一なり。また日天子のよく諸の闇を除くがごとく、また大梵天王の一切衆生の父なるがごとく、よくこの経典を受持することあらん者は、またかくのごとし。一切衆生の中においてまたこれ第一なり」と》
③ 諸宗批判
○唯識・真言・三論・華厳の祖師を邪見とし、法然はそれ以上の大邪見と規定
《具に事の心を案ずるに、慈恩・弘法の三乗真実一乗方便・望後作戯論の邪義にも超過し、光宅・法蔵の涅槃正見法華邪見・寂場本教鷲峰末教の悪見にも勝出せり。大慢婆羅門の蘇生か、無垢論師の再誕か。毒蛇を恐怖し、悪賊を遠離せよ。破仏法の因縁・破国の因縁の金言)これなり。しかるに》人皆その妄語を信じ、悉く彼の選択を貴ぶ。
④ 為政者への批判が増加されている
仁王経・大集経の引用文の増加
⑤ 謗法者への対応がより厳しくなっている
早く一闡提の施を止めて《謗法の根を切り》
夫れ釈迦の以前の仏教はその罪を斬るといえども、能仁《忍》の以後の経説はすなわちその施を止む。《これまた一途なり。月氏国の戒日大王は聖人なり、その上首を罰して五天の余党を誡む。尸那国の宣宗皇帝は賢王なり。道士一十二人を誅して九州の仏敵を止む。彼は外道なり、道士なり、その罪これ軽し。これは内道なり、仏弟子なり、その罪最も重し。速かに重科に行え。》
文応本では大乗仏典を誹謗したことを問題にしたかのように表現しているが、広本は法華経誹謗を問題にしており、諸宗批判の要素も増加している。さらには布施を止めることは、一つの方法とするのみで、罪科を加えることを主張しており、自身の立場をより明確に示すようになっているのである。
さてこの章の最後に「なぜ日蓮聖人は「立正安国論」に加筆を加える形を取ったのか?抜本的書き換えを行わなかった理由は何なのか?」の質問に対して考えてみよう。
先にも示したように『安国論』の上呈は、日蓮聖人にとっての慈悲行・利他行に他ならなかったと推測できる。しかし結果としてではあるが、日蓮聖人は『安国論』の提出により幕府から弾圧を受けることになった。皮肉ではあるが社会的存在として公に認識されたと言ってよい。それにより、日蓮聖人自身の内的構造である法華経の色読も行われることとなった。それ故、『安国論』がなければ、『開目抄』も『観心本尊抄』も成り立たなかったと考えられる。
とすれば、日蓮聖人が『安国論』に書き加え、訂正を行ったのも理解できよう。法然浄土教批判という教学的面では『守護国家論』に劣っていたとしても、自身を社会的存在、法華経の行者として成り立たせるものは『安国論』に外ならない。当初は、日蓮聖人にとって目的に対する手段であった『安国論』が、「『安国論』なくして日蓮なし、日蓮なくして『安国論』なし」という存在に変化していったと考えられる。
三、『立正安国論』の現代的意義
「『安国論』なくして日蓮なし、日蓮なくして『安国論』なし」であったとするならば、『安国論』の現代的意義を考えることは、必要不可欠な問題となる。
先に触れたように『安国論』は為政者が正法帰依する必要を説く。しかし十三世紀ではなく、二十一世紀の日本に生きる我々にとって経文に符合しない、謗法であることが本当に問題なのであろうか。自己の正当性を都合のよい経文を集めることで主張するのであれば、人それぞれの考えがあることになり、意見はかみ合わない。また経文といえどもそれぞれの立場により解釈が異なる可能性を有している。この点は近年の日本国憲法の九条解釈の幅をみれば明らかであろう。
東京外国語大学教授の町田宗鳳博士は著書『なぜ宗教は平和を妨げるのか』(講談社+α新書)で
一方から見れば、相手陣営は邪悪で独善的な狂信集団以外の何ものでもない。しかし、もし邪悪で独善的な陣営の中に身を移してみることができるなら、そこにも否定しがたい「正義」があることに気づくだろう。「正義」というのは、つねに身内の理屈なのであって、当事者が考えるほどには普遍性がないものと言える。
右のような視点に立つ時、『安国論』の論理がそっくりそのまま現代に通じるものであると考えるのは無理があるのではないだろうか。
しかし、一方で『安国論』の視点は先にも指摘した「現世が当に地獄の様相であること」(危機)に対する克服法の提示にあったのであることを重視すれば、現代にも通じる視点や普遍性を見いだすことも可能だと考えられる。
政治と宗教の関係はどうあるべきかが人間社会の重要課題であったことは、二千年昔の古代ローマでも、一千五百年昔のルネサンス時代でも、二十一世紀の現在でもまったく変わっていません。なぜなら政治は社会生活を担当し、宗教は精神を担当するのだから、精神を担当する別のこと、例えば哲学に興味のない人にとっては、人間として生きるうえでの両輪のようなものだからです。(中略)つまり政教分離することで、古代ローマもルネサンスも十八世紀の啓蒙思想も、この問題を解決しょうと努め、また相当な程度には成功してきたのです。
しかしこれ以外の時代は、宗教が政治の分野を侵してくるんですね。(中略)
なぜこのような現象が起こるのか考えてみたのですが、私ごときに解答が得られるわけはないのは当たり前だけど、いつ、何が原因で宗教の反撃といってもよいこの種の現象が起こるのかはわかる。宗教の反撃期に共通しているのは、まず第一に政治が機能しなくなること。皇帝のものは皇帝に、のはずなのに、皇帝が統治能力を失ったのが第一の原因です。政治が機能しなくなること、それは経済にはね返ってくるから、生産性は落ち、インフレは庶民の生活を直撃し、経済力の衰退は安全保障への出費の削減につながるので、安全と食の保証という人間の二大基本要求を満たせなくなる。現実がこの惨状では、人々は来世に望みを託さざるをえず、また日々の生活でも、強力な何かにすいがりでもしないと生きていく力さへも失ってしまう。宗教が猛威を振るうのは、地獄は死後のことではなく、現世のことになってしまった時代なのですよ。
(中略)マキアヴェッリの言葉ですが
「天国へ行く最も有効な方法は、地獄へ行く道を熟知することである」
と知り、その線で生きていける人のことです。ところが、不安と絶望の時代では、地獄に行く道とは何かを知ろうとも努めず、ただただ天国に行こうと願ったあげくが地獄に行ってしまったと言うことになる。(塩野七生『神の代理人』新潮社 四〇八・四〇九頁)
右は塩野七生『神の代理人』のメイキングでのべられた文章である。『神の代理人』メイキングでは「政治が機能しなくなる」ことにより「安全と食の保証という人間の二大要求を満たせなくなる」結果として人々は「強力な何かにすがり」つくとのべている。
『安国論』は、安全と食の保証という人間の二大要求を満たせなくなった現状を憂い、その原因を強力な何かにすがろうとする精神であるとし、為政者の精神を正すことで政治を機能させようとするものではないだろうか。また、「不安と絶望の時代では、地獄に行く道とは何か知ろうと努めず、ただただ天国へ行こうと願ったあげく地獄に行ってしまった、ということになる。」という指摘は、現実を直視しせず、弥陀にすがる浄土教のイメージ(『安国論』「今世には性心を労し、来生には阿鼻に堕せん」)とも符号する。
このように考えると、現代に生きる我々が『安国論』から学ぶべきものは、たとえ現実がどんなに苦しくとも「あきらめない」、原因を探り出し、改革を断行する姿勢にあるといえよう。
鎌倉時代、日蓮聖人は世の乱れ(現実・危機)を直視し、為政者(北条時頼)に宗教政策の見直しを訴える(方法)ことで、国を安定させようとした(理想・克服)と考えるならば、二十一世紀の日本に生きる我々は、誰に何を訴えるべきなのであろうか。
現代日本は言うまでもなく民主主義国家である。とすれば為政者は我々民衆になると考えられる。日蓮宗の「立正安国・お題目結縁運動」では「いのちに合掌」と訴えているが、具体的には「環境・平和・いのち」が守られる世界を目的としているといえよう。では「環境・平和・いのち」が守られる世界(目的)の獲得はどのような方法(手段)で行われるべきなのだろうか。
現代社会と宗教との関連を考える場合、注目すべきは、、ダライ・ラマ十四世の存在であろう。言うまでもなくダライ・ラマ十四世はチベット仏教の法王であり、チベット国王である。自身は対外に避難しなければならなくなり、チベットは民族浄化や宗教弾圧にさらされ、実質的には亡国の危機にさらされているといってよい。この危機に対して、ラマは非暴力を貫き、「愛と思いやり」を訴えることで、宗教の壁を越え世界の世論を味方に付けるという手段で、自身の帰国、チベットの高度な自治権の獲得という目的を果たそうとしている。
ラマは「他の宗教を信仰している人々を仏教に改宗させることに興味はありません」と述べている。これは宗教の壁を越え世界の世論を味方に付けるためであるともいえるが、結果としてダライ・ラマのファンになり、チベットの支援者になっているものは多い。
宗教性はあるが、積極的布教は行っていない。にもかかわらず信者は増え、テロを行うより、チベット帰国の可能性も高まり、ダラムサラは一大観光地となり、結果として亡命政府ならびに民衆への支援がされることとなっている。
この点を考えた時、我々日蓮宗の「立正安国・お題目結縁運動」はどうあるべきなのだろか。昨年の正法のお盆号で拙者自身は、『安国論』の現代的意義にも触れているが、その考えは今も変わらない。
『立正安国論』は冒頭で、地震・飢饉・疫病などによって与えられたいのちが全うできない、納得いかない死が多いことを指摘しています。民衆の苦しみ、悲しみを理解し、事態を救っていくような手が打たれないことに怒りを感じたのです。(中略)
上田紀行『目覚めよ仏教!』の中で、ダライ・ラマ十四世は上田氏の「社会的不正に対して仏教者は怒って良いものなのか。」 という質問に対して、「慈悲をもって怒れ」と述べています。日蓮聖人は、それに先だつこと七百五十年前に『立正安国論』をもって幕府に意見を言い、他者を救わんとしました。まさに、慈悲を以て怒ったのだと思います。
私たちが日蓮聖人のように生きるというのは難しいと思います。しかし、我々一人一人が、自分だけでなく相手を思いやる。周囲の人々の苦しみを想像し、共感する。そのことで、生きやすい社会になり、結果として「いのち」を全うし、納得した死を迎えることができるようになる。このことは実現可能ですし、目指すべき世界のように思われます。
右の表現は「立正安国・お題目結縁運動」と題するものとしては、宗教性が弱く、積極的布教とは言えないかもしれない。しかし、その分普遍性がある。この考えに基づいて宗門運動を考えるならば、社会とのつながりを構築しつつ自己ならびに他者の変革を求めていくことではないだろうか。具体的には一教師一社会事業の推進といってよいかもしれない。
私自身の体験から言えば、ボランティアを通して知り合った人々からいろいろな考え方や経験を学ぶことができるとともに、精神的なことや宗教的なことへのニーズに対する返答を通して、他者の人生に貢献することも可能である。経験そのものが十分に意味あることであるが、副次的効果として布教とまで行かなくても、宗教と宗教者への尊敬を獲得することは充分に可能である。
1 末木文美士『仏典をよむ 死からはじまる仏教史』新潮社 二〇〇九 二七六頁
2 佐々木馨『執権時頼と廻国伝説』吉川弘文館 一九九七 六六〜九三頁
3 佐々木前掲書 一二九頁に「日蓮にとっては、平行線どころか、天台宗の復興、延暦寺の再興を期す「法華経の行者」である、という理由から、予想だにしない弾圧を加えられた。」とある。
4 佐々木前掲書 一二三〜一三〇頁
5 末木文美士『仏典をよむ 死からはじまる仏教史』新潮社 二〇〇九 二七六頁