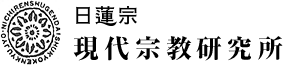「葬式仏教」を考える 2010年10月 発行
「葬式仏教」を考える
巻頭言日蓮宗現代宗教研究所所長 三原 正資1
《講演》 葬式仏教は仏意に適わないのか山口県立大学教授・善應院住職 鈴木 隆泰5
《講演》 「葬式仏教」と中世の日蓮宗市立 市川歴史博物館学芸員 湯浅 治久27
《講演》 葬式仏教の公益性と仏教再生第一生命経済研究所主任研究員 小谷みどり51
シンポジウム69
後記日蓮宗現代宗教研究所主任 髙佐 宣長94
講師レジュメ裏表紙側から収録
巻 頭 言
日蓮宗現代宗教研究所所長
三原 正資
日本は、有史以来、西方の文明を摂取して、自国の文化を形成するという営みを繰り返してきた。かつて、日本を「劇場国家」すなわち、他国で書かれたシナリオを上演する劇場であり、自前のシナリオを持たない国家であるとする議論がなされたりしたが、日本の文化・文明について考えるとき、日本文化の持つこうした傾向を否定することは出来ないであろう。
梅棹忠夫は『文明の生態史観』に次のように書いている。
日本人にも自尊心はあるけれど、その反面、ある種の文化的劣等感がつねにつきまとっている。それは、現に保有している文化水準の客観的な評価とは無関係に、なんとなく国民全体の心理を支配している、一種のかげのようなものだ。ほんとうの文化は、どこかほかのところでつくられるものであって、自分のところのは、なんとなく劣っているという意識である。おそらくこれは、はじめから自分自身を中心にしてひとつの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境諸国民族のひとつとしてスタートした民族とのちがいであろうとおもう。
近年、内田樹が『日本辺境論』を著した際、その書によって主張せんところは要約するとかかることである、として引用したために、再び注目されている一節であるが、ここに記されていることも同様の認識に基づくものであると言えよう。そして、この「文化的劣等感」は、たとえば、明治初期の廃仏毀釈運動などに見られる如く、自国文化を弊履の如く捨てるというような、些か極端な現れ方をして来たのが日本の歴史であり、それがまた一層の劣等感を助長することにもなっているのではないだろうか。
日本人の日本仏教に対する姿勢にもこうした性癖や症状があらわれている。「葬式仏教」ということばによって自国の宗教を極度に蔑視し、キリスト教をファッションのひとつとして生活に取り入れるというような態度も、その一つであろう。こうした傾向は、必ずしも一般民衆にとどまっておらず、むしろ知識人ほど、自国の文化を軽侮する向きが強いように思われる。
たとえば、昭和時代の戦後を代表する知識人のひとりである作家・司馬遼太郎は、我が国の「葬式仏教」について、本来の仏教(『春灯雑記』)からすると「信じがたいこと」であると述べ、未開時代以来の民間信仰が衣をきてお経を読んでいるだけにすぎないとして日本仏教を酷評している。
ところで、日本仏教の檀家制度の成立と葬儀との関わりについて、「葬式仏教」の語の生みの親でもある圭室諦成の『葬式仏教』は、次のように解説している。
庶民が仏教にもとめているものは、①葬祭②治病③招福の三つである。歴史的にみれば、まず治病、つぎに招福、十五世紀ごろから葬祭という順序になる。そして葬祭化してはじめて、仏教は庶民の信仰を独占することに成功している(略)。
寺檀関係は、江戸幕府が設定したものであり、それが寺院を堕落させたという俗論が仏教界に支配的である。しかし、幕府はほとんど完成していた寺檀関係を、たんに制度化したにすぎず、また僧侶が役人気取りでいたところに問題があるのであって、制度そのものに責任を転嫁するのは、かならずしも妥当ではない
圭室の見解によれば、葬式仏教は、仏教各教団の教化が十五世紀の我が国の村落に浸透した結果、誕生したものである。それにともなう檀家制度の成立には、政治的意図が大きく働いたとしても、もともと実情に合わないものは永続しなかったであろうし、まして今日まで存続するはずもない。つまり、圭室に従えば、日本仏教を「堕落」させた原因は、葬式仏教や檀家制度にあるのではなく、自らを支える制度の重い歴史的意味を深くわきまえなかった僧侶にあると言うほかはないことになる。近ごろ、三離れ(葬式離れ、墓離れ、寺離れ)は、つまるところ一離れ(僧侶離れ)であるとささやかれる所以である。
映画「おくりびと」の原作者と言われる青木新門は、現代の僧侶の問題をつぎのように指摘する。
死というものと常に向かい合っていながら、死から目をそらして仕事をしているのである。(略)
己の携わっている仕事の本質から目をそらして、その仕事が成ったり、人から信頼される職業となるはずがない。
(『納棺夫日記』文春文庫増補改訂版)
「葬式仏教は真の仏教ではない」と言われ、僧侶がそれを鵜呑みにして自らもぼやいているだけであれば、たしかに日本仏教の前途に光明を見い出すのは難しいであろう。
近時、大手流通企業が葬祭業に進出し、「お坊さん斡旋」をするとして、そのホームページ上に「お布施の価格表」を公開し、マスコミでも報道された(産経新聞 七月二日号など)。これを見て、多くの心ある僧侶は顔の赤くなる思いがしたであろう。私たちの反省すべき点は多いと言わざるを得ない。
今回の第二十回「法華経・日蓮聖人・日蓮教団論研究セミナー」に於ける、鈴木隆泰、湯浅治久、小谷みどりの三先生の御講演は、ひとり日蓮教団のみならず、日本仏教の葬儀の意義の再発見に新たな光をあてるものと確信している。
研究所の仕事は、本来、一般に向けてのものではないが、新しい試みとして、本書は、広く仏教に関心を有する方々にお読み頂けるよう、日蓮宗新聞社を通じて頒布することとした。
この小さな冊子の大きな意図を受け止め、それぞれの立場で生かしていただければと念ずるものである。
葬式仏教は仏意に適わないのか
山口県立大学教授 善應院住職
鈴木 隆泰
今ご紹介にあずかりました、山口県立大学から参りました善應院の鈴木隆泰でございます。本日は「葬式仏教は仏意に適わないのか」というテーマでお話をせよということでございますので、今から一時間一〇分ほど頂戴しまして皆様の前で、お話をさせていただきたく存じます。
お手元には資料を二部お配りいただいていることと思います。一つは「葬式仏教は仏意に適わないのか」という四枚とじのレジュメでございまして、もう一つは、私が二〇〇五年にうちの大学の論文雑誌に書いた「日本仏教は『葬式仏教』か―現代日本仏教を問い直す―」です。基本的にこの二つに沿って進めてまいりたいと存じます。
全部を読むことは時間的にできませんが、重要なところ、最初の出だしの部分は、少し長いですが、これに沿って読ませてください。「日本仏教は『葬式仏教』か」のほうをごらんください。
◇ ◇
1、「問題の所在」
近代になって、西洋文献学に基づいた新たな仏教学が始まりました。その近代仏教学が描き出したインド仏教の姿というものは、総じて高度に哲学的な教義を持ち、極めて理性的、合理的、脱儀礼的、そして脱呪術的な性格を持つものでした。仏教の起源に置かれた歴史的人格としてのブッダ・シャーキャムニ(釈尊)は、宗教家というよりも哲学者・道徳家として扱われることとなり、また、仏教を解明する材料としても、南伝上座部所伝のパーリ仏典に代表される初期仏典(原始仏典)――「小乗仏典」と呼ぶのはいろいろ支障があるようでございますので、私は「初期仏典」と呼んでおります――や論書等が好まれることとなりました。大乗経典にあらわれる偉大な宗教家、そして救済者としての壮大なブッダのイメージや、その中に説かれる種々の儀礼や呪法は、初期仏典や論書から導かれる哲学者・道徳家としての歴史的ブッダ釈尊像にそぐわないとみなされてきたわけです。
そのような手続きのもとに描き出されてしまった、いわゆる「インド本来のオリジナルな仏教」と、漢訳された大乗経典を聖典として仰ぎ、そこにあらわれる壮大なブッダを尊崇し、そして葬儀や祈祷など種々の儀礼・呪法に携わる日本の伝統仏教との間には、極めて大きな溝、乖離・ギャップが生み出されてまいりました。日本仏教を「葬式仏教」と呼ぶときに、そこに「本来の仏教とはかけ離れ、変質し堕落した仏教」という侮蔑の意味が、程度の差こそあれ込められていることが多いことは、このような事情を反映したものと言えるでしょう。
さらに問題だと考えられることは、このような評価が日本仏教の根底を揺るがしかねないものであるにもかかわらず、今日に至るまで両者、つまりインドの仏教と日本の仏教の間に横たわる溝を埋めようとする作業や、両者の距離をきちんと測定しようという作業が充分になされてきたとは言いがたいのではないか、という点にあります。その結果、日本の伝統仏教に携わる、殊にわたしたちは、誠実であろうとすればするほど、自らの勤行・修行はおろか、時には自らの信仰についてさえ、その正当性――正しいのか、正統性――ちゃんと釈尊からつながっているのか、に疑問を抱き、苦悶することとなりました。
しかし、本当にインド仏教は哲学的、理性的・合理的・脱儀礼的・脱呪術的であって、日本仏教とはかけ離れた姿をしているのでしょうか。また、仮にそうであったとしても、それはそのまま日本仏教の変質や堕落と言えるものなのでしょうか。
今回は内外の最新の研究成果を援用しながら、その距離測定を行ってみたいと考えております。
私自身はずっとインド仏教のことを見てまいりました。日本のお寺に生まれて育ちましたけれども、やはり日本の仏教は何か違うのではないかと思って、インドをずっと見てきました。インドをずっと見てきて初めて、今まで先人たちが仰っていた、「インド仏教というのはすごいのだ」「とてもエリートなのだ」「格好いいのだ」というのとは違う、もっと生々しい、どろどろとした、人間くさい、ある意味ではわたしたちと同じインド仏教の姿が見えてまいりましたので、これをお伝えすることが逆に私の義務ではないかと考えて一連の成果を発表し続けているところでございます。
◇ ◇
2に参ります。「初期仏典を中心とした仏教―四例」です。こちらの四枚組のレジュメを見ていただきますと、この四例を挙げるだけでも、かなりショッキングだと思われます。
まず①「祈祷は役に立たない」。今わが宗派ではちょうど多くの方が行堂を成満するという時期ですけれど、この経典には「祈祷は役に立たない」などというステートメントがございます。
②「呪術に携わるな」。
③「出家者は葬式にかかわるな」。
そして④「沐浴・水行は無意味だ」。少なくとも字面を読む限りこのような文言が見えるのです。このようなものをもとにして「日本の仏教はおかしい」という言説が長らく行われてまいりました。
まず、どのように記述されているのかを簡単に見てまいりたいと思います。再び厚い方のレジュメをご覧ください。
①「祈祷は役に立たない」。
ある村長がおりまして、釈尊に聞くのです。「バラモンというものがさまざまな祈祷をやるけれども、釈尊さんよ、あんたもやるのかね」と言うと、「例えば石を水に投げ込んで浮け、浮けと言ったら浮くだろうか、浮かない。もし油をまいて沈め、沈めと言ったら沈むだろうか、沈まない。それと同じなのだ、村長よ。その人が生前に行った業によって、善い者は上に浮かび、悪い者は沈むのだ。祈祷をやっても無意味だ」ということが確かに書いてあります。
②「呪術に携わるな」。これも非常に古い経典、『スッタニパータ』、最古層の経典です。ヴェーダの占い、呪術、星占い、さまざまなことを「やってはいかんよ」と書いてあります。
③を飛ばして④に参ります。④「沐浴・水行は無意味だ」。
インドでは水に入って心身を清めます。バラモンがそれをやって震えているわけです、寒い寒いと。そうすると、それを見た一人の比丘尼が「何をやっておるんですか、バラモンさんよ」と。そうするとバラモンは「何を言ってるのだ。水に入れば清らかになるんだ」と言うと、比丘尼はそれを笑うわけです。「もし本当に水に入ってきれいになるんだったら、魚や亀だっていつもきれいだろう。また、水が悪業を流すのだったら、同様に善業も流しちゃうんじゃないの。だから水行なんか意味ないよ」と言ってしまっているわけです。かなりショッキングです。
そして、③「出家者は葬式にかかわるな」、『涅槃経』ですね。大乗の『涅槃経』ではないほうの、初期仏典の『涅槃経』です。ここを読んでみます。
アーナンダが問います。「大徳よ、私たちは如来の遺体をどのようにしたらよろしいのでしょうか」。そうすると、入滅間近の釈尊は「アーナンダよ、そなたたちは如来の遺体供養にかかわるな。アーナンダよ、そなたたちはどうか自身の目的(利益)のために励んでもらいたい。自身の目的に専心すればよいのだ。自身の目的に勤め励み、専念しなさい。アーナンダよ、如来を信仰するクシャトリヤの中の賢者たち、バラモンの中の賢者たち、資産家の中の賢者たち、彼らが如来の遺体供養をなすであろう」、ここです。これが一番の論拠となって、葬式に出家者はかかわってはいけない、それは在家者の仕事だということがずっと唱えられてきたわけです。そして、葬式に携わっている日本の伝統教団というものは「堕落している」と、特に在家教団から批判を受けることになってまいりました。
もしこの文言をそのまま……実はこれはわたしはあえて誤訳しています。今までの人たちの誤訳をあえて使いました。もしこの日本語訳を見てしまうと、「いや、日本仏教、だめじゃん」となってしまうのですけれども、実はさまざまに誤解なり間違った解釈がなされてきたのがわかってまいりました。順に論破してまいります。
◇ ◇
3、「①②③に対する反論と反証」です。
まず、「祈祷は役に立たないのだ」という①に対しては、全然違うことを言っている経典があるのです。それは『シンガーラ青年への教え』という経典でして、漢訳では『六方礼経』です。在家の青年シンガーラが家に代々伝わる祈願として、東西南北、そして上と下の六方を日々拝むのです。なぜやっているかわからないのですけれどもずっとやっている。そして幸せを祈願しているわけです。それを見た釈尊は、それをやめろとは言わないのです。そのままやっていいけれども、それに新たな仏教的意味を付与していく。決して祈祷や祈願というものを禁止しているのではなく、「従来の、バラモンと同じことはしない」と言っているのです、単に。バラモンとは違った道を歩む。全然このような祈願をしないとはどこにも書いていません。先ほどの①の文章を読めばわかってまいります。「バラモンはこうやってるけど、釈尊さん、あんたはこうするの?」と村長は聞いているのです。それに対して「わたしは違う」と言っています。「バラモンと違うことをする」と言っているだけで、「全くやらない」とはどこにも書いてありません。次に示すように、祈祷・祈願は実際に行われてまいりました。
②に対する反証、パリッタ呪です。「呪文・呪術に携わるな」と言われますけれども、今伝統的な仏教の流れを引いていると自負している南伝仏教――南アジア、東南アジアに広がっているテーラワーダ・ブッディスム――彼らは基本的に呪術を多用します。パリッタといいます。パリッタというのは防護という意味です。防御、防護です。悪いものを遮断して、好ましいものを呼び込む。攘災招福祈願のための呪文です。これを日々唱えている。そのために今の南伝仏教、上座部仏教は「パリッタ仏教」と呼ばれるぐらいです。ただしヴェーダの呪術ではありません。仏教独自の呪文です。だから、やはりこれもヴェーダやバラモンと同じことをしないというだけで、仏教独自の呪術、占いを禁止しているわけでは決してないということです。
そして、ついに本題です。③に参ります。③に関しては、この四枚紙レジュメの二ページをめくっていただきたいと思います。
先ほどあえてわざと誤解を招きやすい訳を提示しておきました。ここでは今回のために用意してまいりました、より正確な訳を見てまいりましょう。ここでまず問題になるのはシャリーラプージャーという言葉です。シャリーラといいますと大体仏舎利でありますから遺骨と思われがちですけれども、シャリーラは複数形ですと遺骨ですが、単数形だと体、そして遺体の意味です。プージャーというと供養だと考えられがちですので、シャリーラプージャーは遺骨を供養する、もしくは遺体を供養する。葬式だったり納骨会、そのようなものに思われてしまって、どちらもだめだと思われてきたのですが、どうもそうではない。これもちょっと手間がかかりますけれども、大事なところですので、レジュメを読んでまいりたいと思います。おそらくこの原文に関して最も新しい日本語訳だと思います。
アーナンダが問います。先ほどと一部重なっておりますが、時間を惜しまず読んでみたいと思います。
「大徳よ、私たちは如来の遺体をどのように処置したらよろしいのでしょうか」。そこで世尊が答えます。「アーナンダよ、そなたたちは如来のシャリーラプージャーに」――あえてここでは遺体供養とも遺骨供養とも言っていません、あえてシャリーラプージャーで残しています――「シャリーラプージャーに携わるな。おまえはやらなくていい、在家がやってくれるよ」と。シャリーラプージャーは在家がやってくれると言っているのです。そこでアーナンダがもう一度問います。「では、大徳よ、如来の遺体はどのように処置されるべきなのでありましょうか」「アーナンダよ、転輪聖王の遺体を処置するのと同様の方法で如来の遺体を処置すればよいのである」「では、大徳よ、転輪聖王の遺体はどのように処置されるのでありましょうか」「アーナンダよ、まず転輪聖王の遺体を新しい布で包む。新しい布で包んだら、今度は打った綿」――油が染み込みやすいように綿を打ちます――「綿で包む、打った綿で包んだら、さらに今度は新しい布で包む。このようなやり方で転輪聖王の遺体を五百重に包むのである。それから鉄製の油槽の中に納め、もう一つの鉄槽で蓋をし、あらゆる香料を含ませた薪を積み上げて、転輪聖王の遺体を荼毘に付す。そして交通の要所に転輪聖王の遺骨塔(ストゥーパ、卒塔婆)を建立するのである。アーナンダよ、このようなやり方で、転輪聖王の遺体は処置されるのである。アーナンダよ、転輪聖王の遺体の処置と全く同様の方法で如来の遺体も処置されなければならない。交通の要所には如来のストゥーパを建立せよ。誰であれ、そこで花や香料や顔料を献げて礼拝したり、心を清めて信じるならば、そのことによって彼らには長きに亘り、利益と安楽がもたらされるであろう」。
少し飛ばして「如来・応供・正遍知はストゥーパを建立されるにふさわしい。(中略)ではアーナンダよ、どのような道理にもとづいて、如来・応供・正遍知はストゥーパを建立されるのに相応しいのであろうか。アーナンダよ、これがかの世尊・応供・正遍知のストゥーパなのだと言って、多くの者たちが心を浄めて信じる。彼らはストゥーパの前で心を浄めて信じたことで、死後、現在の身体を失った後に、善趣である天界へと生まれ変わるのである。アーナンダよ、まさにこの道理にもとづいて、如来・応供・正遍知はストゥーパを建立されるに相応しいのである」。
これが一連の流れです。この中で結局シャリーラプージャーとは何を言っているのかというと、もうこの中に答えがありました。それは、遺体の前でお経を読んだりすることではありません。遺体の処置手続きです。つまり、まず遺体に死に化粧をして、次にそれを納棺して、そして点火する。荼毘のお経を読むのではありません。点火するのです。そしてその次に、遺骨塔を建立するのです。これもまた遺骨塔の前でお経を読むのではなく、遺骨塔を建てるのです。言うなれば、今の日本で言えば納棺師の仕事と火葬場の人の仕事と石屋さんの仕事です。それは「在家者がやってくれますよ」と言っているのです。決してそこで何かお経を読んだり、遺体に対して礼拝したりすることを言っているのではありません。最後にストゥーパの礼拝のことが載っていますが、これはストゥーパが建立されてシャリーラプージャーの一連の手続きが終わった後に人々はどうするかという話をしているのです。
この遺骨供養にせよ遺体供養にせよ、供養という意味がとても拡大してしまって誤解されてしまいました。シャリーラプージャーは明確に納棺、荼毘、そして遺骨塔建立に至る一連の遺体処置手続きです。「それはアーナンダよ、おまえはやらんでよろしい。在家者がやってくれるよ」と言っているのです。
納棺の仕事、点火の仕事、そして墓石を作る仕事はやはりわたしたちは余りやらないと思います。多くはその専門の方に任せているのではないでしょうか。現代の日本と何も変わりはありません。
ただ、本当に出家者はこれを全部できなかったかというと、そうではないのです、本当は。例えば私たちも自分の師匠が遷化した際には清浄衣を着させ、そして棺に納めると思います。私も早めに師父を亡くしましたので、そのような儀式に参加させていただきましたけれども、その場合には納棺手続きをわれわれがいたしますよね。そうなのです、実はインドでもこのシャリーラプージャーを出家者はやっているのです。では、なぜ釈尊はアーナンダに禁止しているかというと、ご存じだと思いますが、アーナンダはまだこの段階で覚っていないのです。まだ未熟なのです。彼は有学です、まだ無学になっていない。ですので、おまえはやらなくて、おまえは修行をしろと言っているのです。事実、釈尊の遺体に点火するのは摩訶迦葉の仕事でした。摩訶迦葉はちゃんと荼毘の点火をしているのです。出家者はやっているのです。つまり、修行が完成していないアーナンダに対する禁止なのです、これは。
実際に、これも非常に誤解を招いてきたところですけれども、南アジア、東南アジアの仏教は律中心です。それに対して東アジア仏教は経が中心です。経蔵と律蔵で、経中心か律中心か。で、律が余り知られていない。律を詳しく読めば、どのように仲間のお坊さんの葬式を営むか、行事を事細かく説明しています。やっていたのです、サンガの中で。同僚のお坊さんが亡くなったときに仲間内でやっていたのです。ですから、「出家者が葬儀にかかわるな」「携わるな」というのはまず明確な誤解であることがわかります。
ただし、インドの仏教出家者たちは、同僚の人たちの葬儀はやっても、在家者の葬儀は絶対できなかったのです。同僚の出家者の葬儀はやっても、在家者の葬儀にはタッチできない。そのようなジレンマがありました。なぜだったのでしょうか。それについて次、4、「インド仏教と儀礼」で述べてまいります。
◇ ◇
再び「日本仏教は葬式仏教か」の三四ページをごらんいただきたいと思います。読んでみます。
インドの伝統仏教は、「涅槃」という世俗を離れた究極目標を目指す出家者集団、いわば超俗的価値観を持った宗教エリートである出家者たちによって担われていました。彼らの第一関心事は自己の修行の完成です。在家者との関係も、威儀正しく振る舞うことによって自らを福田たらしめることが中心です。自らがきちんとしていること。立派な宗教家に布施をすると、そこで功徳が育つのです。そしてその功徳を摘み取るのは布施をした在家者です。だから、徳の高い宗教家には布施が集まる。仏教教団で一番裕福だったのは釈尊です。徳の高いお坊さんほど裕福です。徳の低いお坊さんに布施をしても功徳が少ないのでだめなのです。彼らには、自らが福田であることをアピールする必要があるのです。「自分は立派な宗教家ですよ」「わたしに布施をすると、立派な功徳が育ってあなたに返りますよ」。そして、在家者からの尊敬と布施を獲得し、修行生活を守っていく。存続しなくてはいけない。自らが修行すると同時に仏教を存続させる必要がある。そのためには布施を受けねばならないのです。かすみを食っては生きられません。
一方、在家の仏教徒というものは常にカーストに属しています。インドの社会はカースト社会でして、インドにいながらカーストを抜け出すためには出家するしかないのです。出家するか、インドを離れるか、もしくは死ぬしかありません。インドの在家仏教徒は通常カーストに属していて、カーストの儀礼をバラモンにやってもらうのです。同時に「あの仏教のお坊さんは福田だ」といって布施をする。そうして外護していたというのがインド仏教における在家と出家の関係です。
仏教はカーストを作ることを断固拒否するわけです。この四枚組のレジュメのほうに書いてございます。カーストをインド語ではジャーティと申します。明確な文言で、「生まれ(ジャーティ、カースト)によって賤しい者となるのではない。生まれによって尊い者となるのでもない。人は行いによって賤しい者ともなり、行いによって尊い者ともなるのだ」。
四ページ目に参ります。仏教は生来の、生まれついての浄・不浄の差別に基づくカーストを断固拒否します。そして、人の浄・不浄、尊い・賤しいというものは生まれではない。その人が尊い行為を行っているか、賤しい行為を行っているかによって決まるという徹底した行為主義の宗教です。
釈尊自らが自分のことを行為論者、キリヤーバーディン、カンマバーディンと呼んでいます。有名な七仏通戒偈。「一切の悪をなすことなく、善のみを修習せよ。自らの心を浄めよ。これが諸仏の教誡である――諸悪莫作、衆善奉行、自浄其意、是諸仏教」、ひたすら行為です。行為をして浄めていく。ここに尽きてしまう。これが仏教が非常に行為主義が強いことのあらわれです。
そのような仏教ですから、カーストについては受け入れることを拒否する。しかし仏教はカーストを理念的に否定していますけれども、カーストをやめましょうと社会運動を起こしたことはインドではありません、決して。新仏教徒は別ですけれども、古代においてはありません。なぜか。社会運動をしてしまったら、その集団は社会集団になってしまいます。もしそれをやってしまうと、仏教者集団が一つのカーストになってしまうのです。社会運動をしないということによって僧侶は出家者たりえるのです、インドでは。
四ページ。「福田と通過儀礼」。インドで宗教家が布施を得る方法は二つです。一つは先ほど説明しました福田です。自分は立派な福田なのだ、福を育てる田んぼなのだ、だからわたしに布施しなさい。もう一つは、儀礼を執行してあげることです。さまざまな儀礼を執行してお布施を受けるのです。
儀礼にはいろいろなものがあります。ただ、出家の仏教者がタッチできなかった儀礼があります。それが通過儀礼です。通過儀礼、結婚式や葬式の執行法はカーストごとに決まっています。このカーストに属している人はしかるべきときにこのような人を呼んでこのような儀式をしなさいと決められています。そして、それにタッチした瞬間に仏教カーストができてしまうのです。通過儀礼を完備した集団は、インドでは一カーストを形成します。カーストを否定した仏教は通過儀礼を執行することができなかったのです。
カーストを否定するということは、最初はインドではとても効果的でした。仏教がインドに広がるきっかけになったのは、ご存じのように、紀元前三世紀のマウリヤ王朝の第三代アショーカ王が仏教を厚遇したことです。マウリヤ王朝はインド最初の統一王朝です。統一王朝を作るときに、カーストごとにルールが異なっていると統治しにくい。ですので、カーストに縛られない統一的な真理を説く仏教を利用したのです。そして、マウリヤ王朝が滅びた後、今度は外来の勢力が入ってくる。インド古来の考え方からいえば、外来人はすべて野蛮人です。わたしたちも。「ムレッチャ」と呼ばれます。そのような外来の王様にとってカーストはやはり障害です。また、ギリシア・ローマとの交易も盛んになり、商業が発達します。その中でもカーストはやはり障害です。カーストが低い者は高い者に物を渡せません。高い人が低い人に渡す場合にはぱっと捨てて、「拾え」と言うのです。このようなことをしていたら、商売はできません。外来の王様のインド支配だったり、商業の発達だったり、そのような中でカーストを利用しない、カーストを認めない仏教というのは非常に都合がよかったので、もてはやされます。
しかし、その時代も長くは続きませんでした。ローマ帝国が分裂して東西交易が弱まっていく。商業がだめになってくる。そうすると都市が衰退する。都市が衰退するとインドの中心がまた農村に戻っていく。農村はいい意味でも悪い意味でも、両方の意味で非常に古い因習が残っているところです。都市では薄れていた、商業社会では薄れていたカーストというものに重きを置く。そしてまた紀元後四世紀のグプタ王朝の成立によって、非常にインド的な伝統的価値観が見直されてくる。そこで仏教は逆にピンチに陥ります。今までカーストを認めなかったことがプラスに働いていたのが今度はマイナスに働いてくる。ヒンドゥー、バラモン全盛になってきます、四世紀以降。そして、それ以降は二度とインド宗教界の頂点に仏教が君臨することはなくなります。そしてどんどん衰退していって、最終的には滅びていくということになります。
よくイスラム教の人たちが侵入してきたから仏教は滅びたと言われますが、それはきっかけにすぎません。イスラム教が攻撃したのは仏教徒だけではありません。ヒンドゥー教徒もジャイナ教徒もすべて攻撃しています。でも、仏教だけが滅びてしまいました。どうしてか。カーストがなかったからです。再生産できないのです。ヒンドゥー教徒の家に生まれた者はカーストでヒンドゥー教徒になります。ジャイナ教徒の家に生まれた人はカーストがありますからジャイナ教徒になります。自動的に再生産されるのです。継続性がある。仏教はそれを最初から断ち切ってしまっていた。仏教は元より、常に新しい命、在家者も出家者も外から供給するしかないのです。その中で仏教が滅びていくことになりました。
でも、仏教は何とか生き残ろうとしました。その一つが、今までだめだ、だめだと言っていた沐浴や水行を「実はいいのだ」と取り込むことです。
◇ ◇
5、「インド仏教徒の叶えられた願いと叶えられなかった願い」です。
『金光明経』の中で沐浴、水行というものを肯定的に受容する。それは、今まで仏教ではできなかったことを、「仏教だよ」と言うことによって信者を取り込もうとした、仏教の生き残り策の一つです。例えば日本でも、多くの在家の方というのは、お葬式は仏教式でやっても、お正月になると神社に行きますし、また結婚式はキリスト教式や神前式でやる。このような方々が多いですけれども、篤信家になればなるほど結婚式もやはり仏式でやりたいと思うようになります。そのようなときにインド仏教はこたえられなかった。葬式もそうです。どれほど仏教のことが好きでも、自分が死んだときに仏教のお坊さんは手も合わせてくれない。その中で仏教は、衰退していたこともあり、さまざまな儀礼を取り込んで生き残りを図ります。しかし、どうしてもできなかったのが通過儀礼です。
四枚紙レジュメのほうをごらんください。「〈サンスカーラ〉が結ぶ〝諸行無常〟と通過儀礼」。なぜサンスカーラは通過儀礼なのだろうか、諸行無常と通過儀礼は関係あるのだろうかと思われるかもしれません。諸行無常、これの元々の意味は、「もろもろのサンスカーラは同じ状態にとどまっていない」という意味なのです。これは仏教の根本的な教説の一つですね。「諸行無常であると智慧を持って覚るとき、人は苦を厭離する。これが清浄(涅槃)へと向かう道なのだ」と古くから説かれてまいりました。諸行無常は非常に大事なものだと考えられています。諸行無常の原語「サンスカーラ」、これは形成力、形成作用です。このサンスカーラが形成するものは自分です。自己を作り出すのです。このサンスカーラは常に同じではありません。「諸行無常」と言っているので、永久には続きません。だから、悪人も善人になれますし、善人も悪人になってしまうことがある。賤しい人も尊くなれるし、尊い人も賤しくなってしまう、逆にすると。凡夫が成仏できる道理もここにあります。
そして、諸行無常というのは、もろもろのサンスカーラの、その効力は永久には続かないのだ、という宣言なのです。仏教ではサンスカーラは自己形成力のことですが、まさしくインド一般においてサンスカーラといえば通過儀礼です。通過儀礼のことなのです、サンスカーラといったら。仏教は諸行無常という言葉の中に表と裏の意味を潜ませています。表の意味は、「自己を形成するサンスカーラというものはいつも同じではない。だからきちんとサンスカーラを制御しなさい」「尊いことをする自分を作るのだ。悪いことをする自分を作ってはいけませんよ」というのが表の意味ですが、裏の意味として、「ヒンドゥー・バラモンがやっている通過儀礼、あんなものの効果はいつまでも続きはしない」「あんなことをやっても意味がないのだよ」という、もう一つの意味を含ませている。自分たちは通過儀礼にタッチできませんので、その通過儀礼の効力自体を否定する。そのような意味が二重にかけられています。サンスカーラという言葉を自己形成作用という意味で使うのは、本当に仏教だけの文脈で、インド一般では通過儀礼の意味でしか使わない言葉です。
インド社会の制約の中で、さまざまな願いにこたえようとして仏教は儀礼を取り込んできました。「これも仏教式でやってほしい」「やってやろう」「これもやってくれないか」「やりましょう」……。しかし、何度も繰り返しますが、どうしてもできなかったのが通過儀礼なのです。通過儀礼をやったら、その瞬間にカーストをつくってしまうのです、仏教カースト。それを仏教は断固拒否したのです。これは余りに潔いと思います。おそらく仏教カーストを作っていれば生き残れたでしょう。現に今では仏教カーストはあります。だからインドで仏教は復活したのです。あれは仏教カーストを作ったからです。しかし、伝統的な仏教はカーストを作ること、生まれながらの差別を断固拒否して、インドから消え去る道を歩んだのです。ただ、カーストを否定したからこそ、カーストのない社会では生き残ることができました。そして、東アジアに伝わって、今わたしたち日本人のもとにも仏教があるのです。
そのように考えるときに、葬式をしているということは決して仏教の堕落でも変質でもありません。宗教は本来人間をトータル、ホリスティックに見るはずのものです。生まれてから死ぬまで、そして死んでからも、トータルで全体を見ていくものが宗教だと思います。そのときに、福田としては存在している、また、祈祷などはしてくれる、でも、葬式をしてくれない、死後の安心をくれない――このような宗教団体は生き残ることが非常に難しかったのです。特に日本人は古来、死後の世界というものに非常に強い関心を抱く国民性を持っています。日本で仏教が根づくためには、葬式と一緒になる必要があったのです。死後の安心、死後にきちんと祀って、よい祖先、ご先祖さまになっていただく、それが日本人の一般的な他界観です。そこで仏教というものが重宝されたのです。
中国は古来、文化先進国でした。今でも中華人民共和国や中華民国というように、中華思想がある。世界で一番華やかで、中心は自分たちだ、という観念です。その中国すら取り入れた天竺からのスペシャルマジックが仏教だったのです。その仏教を日本は導入したのです。
最初は国家仏教として天皇の祖先神を強くして、鎮護国家をする。仏教パワーで天皇家の祖先神を強くする。ほかの祖先神が強くなると反逆を起こすかもしれません。だから仏教を隠し布教を禁止したのです。ですが、鎌倉以後――湯浅先生がお話しくださると思いますけれども――仏教が大衆化してくる。そこには葬式というものがありました。それをしてあげることによって仏教が民衆に根づいていく。一般の人たちは仏教の教義などはわからないのです、当時から。多くの場合、今もそうだと思います。簡単なことはわかるかもしれませんけれども、詳しいことはよくわからない。ただ、お坊さんがそこに来てお経を読んでくれた、その事実が大事なのです。逆にそこが葬式仏教の抱える、一番の問題なのかもしれません。お経の意味はわからないけれども、そこで何か儀式をやった。そこで日本人は安心してしまう。それ以上に深化が進んでいかない。教義のことをいろいろ言っても、なかなか通じない。もちろん通夜説法なり葬儀のときの説法は大事だと重々感じておりますけれども、いつもいつもうまくいくわけではありません。儀式さえやってくれればいいと思っている方がいて、教化不足と言われればそれまでなのですが、それが今までの多くの日本の仏教の姿だったのではないかという気がします。
願いを叶えるというのはとても大事です。どのような時代でも、人々の願いにこたえられない宗教集団が生き残ったためしはありません。「自分たちの教義ははこうだ」ということだけでは生き残れません、ニーズがないと。ニーズがあって、それにこたえていく、そのようにして、どのような世界でも宗教は生き残ってきたのです。宗教の側から「これを信じろ」「あれを信じろ」と押しつけるだけでは生き残れてこなかったのです。そのような意味で、日本人が葬式、葬儀に並々ならぬ関心を払っていたからこそ日本の仏教は葬式を中心にして発展し、今日まで来たのだと思います。そして今日、そこから新たな一歩が必要になっているかと思います。
◇ ◇
6番、「種々の問題と巧みな方便」。
願いにこたえる、とても大事なことだと思います。人々の、まさに心のうめきのようなものを聞き取る。そしてそれにこたえていくことは宗教者として当然のことだと思います。ただそれだけに終始していては恐らく今後の発展はないだろうとも思います。例えばお金をもうけたい、商売繁盛。一〇〇万円もうけたら二〇〇万円欲しくなる。二〇〇万もうけたら五〇〇万欲しくなる、とどまるところがない。そのようなことだけでは恐らく続いていかないのではないかと思います。お手元の「日本仏教は葬式仏教か」には「霊感商法」や自殺の問題を挙げてありますので、後ほど読んでいただければと思います。
ここでは、方便という問題について述べたいと思います。方便というと、どうも本当のことではない二義的なもの、便宜的なものという意味合いが強いのではないかと思います。確かに「正直に方便を捨て、ただ南無妙法蓮華経と唱える人」というお言葉もございますので、「方便というものは二義的だ」、本門・迹門で「ここは迹門だ」「ここは本門なのだ」というような議論がされてきましたけれども、方便というのは決して真実と違った二義的なものではありません。例えば、健康な状態というものがいわゆる真実だとすると、方便は薬だったり治療です。健康状態というのが大事なのは当たり前です。ですけれども、健康を「はい、あげます」とは与えられない。健康になるために病人にはさまざまな治療を施す、それが方便です。手段です。そして、例えばおなかの痛い人にはおなかが痛い人用の薬を、頭の痛い人には頭の痛い人用の薬を差し出す。応病施薬――もちろん万能薬もあるかとは思いますけれども。決して薬は真実ではない。教えというものは言葉です、言葉というものは真実になり得ません。「不立文字、教外別伝」ではありませんが、例えば富士山に登った体験がない人に、富士山に登ったことをどんなに言葉で説明しても伝わりません。釈尊もそうでした。覚りの体験というものを伝えることはできないのです。誰も覚りを体験していないから、それを言葉に託すと通じない、勘違いされてしまう。言葉というものはお互いの間で、ある言葉とある意味が一致している場合に通じるのです。例えばわたしがここで「サッバパーパッサアカラナン、クサラッサウパサンパダー、サチッタパリヨーダパナン、エータンブッダーナサーサナン…」と言っても、「何のこっちゃ」と。言葉と意味の関係が結びついていないときには通じません。覚りもそうでした。教えも全部そうです。覚りに至るための手段。
おなかの痛い人にはおなかの痛い人用の薬を上げるのがどうしても必要なのです。それしかないのです。頭の痛い人には頭の痛い人用の薬を上げるしかないのです。どれがよくてどれが悪い、「頭痛薬と腹痛薬のどちらが偉いのだろうか」、そのような議論はあり得ないのです。真実に至るための手段を出す能力、それが法師が発揮すべき方便を出す能力です。「法師品」をはじめ、なぜ『法華経』で法師があそこまでたたえられるのかというと、法師には、方便を出す、その能力が求められ、期待されているからです。
葬儀も祈祷も、ある意味ではそのような方便です。その方便を活用しながら、いかに相手を覚りのほうに持っていくのか、そして自分も進んでいくのか、という能力がなければ、恐らく今後生き残っていけないのではないかと思います。
わたしは日本の仏教が葬式を執行できるというのは、ものすごいメリットだと考えております。インドでできなかったのですから。繰り返しますが、自分が信仰している宗教家が、「死んだら知らないよ」というのは、やはり余りに悲しいです。日本にはカーストがありませんので、正々堂々と葬式を実行できますし、やってまいりました。これまで営んでまいりました。そこに善巧方便の力というものを組み合わせることによって、次の地平というものが開けてくるのではないかと思いますし、万が一それができないときには、伝統教団というものは甘んじて衰退の道を辿らざるを得ないのではないかと危機感を抱いているものの一人でございます。
◇ ◇
次に、インドの仏教についてお話ししたいと思います。
わたしたちはやはり東アジア仏教ですから、どうしても例えば「大乗が偉くて小乗というのはだめなんだ」、実際に大乗経典には「小乗はだめだ、だめだ。小乗の連中は覚れないのだ」と書いてありますし、だからこそ『法華経』という経典が「いや、すべては一つ、一乗なのだ」というように納めとっておく必要がある。どうも大乗と小乗はインドでは仲が悪いのではないかと思われているかもしれませんが、それは誤解です。仲よく住んでいます。
先ほど申しましたけれども、南アジア、東南アジアの仏教は律中心です。「どのように行動するか」ということで、仲間か仲間ではないかを分けます。つまり、その人の行動です。一方、東アジア仏教は経中心ですので、何をするかではなく何を考えるか、何を信じているかで分かれたのです。例えば中国でさまざまな宗派ができましたが、いわゆる所依の経典、「どの経典に基づくのか」ということで分かれています。天台宗がありますね。華厳宗もできました。さまざまな宗派がありましたけれども、どの経典が一番すごいのか、そこで教判――教相判釈というものが生まれてまいりました。日本でもそうですね。「どの経典に基づくのか」ということでさまざまな宗派が分かれる。
インドではどのような経典を信じていても一か所にいられます。彼らが分派するときは、律が違う場合です。律が違うときは一緒に行動できない。逆に言うと、律を守っている限り、どのような教えを信じてもいいのです。大乗経典は在家者が作ったのでは決してありません。サンガに属する出家者が作成いたしました。もちろんそれは勝手に作ったのではありません。方便を出したのです。
経典、お経というものは、釈尊だけが説いたのではありません。釈尊は在世のときから弟子たちに「おまえたちよ、二人して同じ道を行くな。別々に行けば多くの人に教えられるけれども、二人一緒だと、こちらの人は聞けなくなってしまう。ばらばらに、できるだけ多く布教してこい」。そして、会った人にその人なりの教えを説いていく、方便の力を弟子に求めました。つまり、釈尊在世のときから教えを説いていたのは釈尊だけではないのです。大乗経典だけが後世の創作と思われているようですが、それは誤解です。初期仏典(原始仏典)の中にも、仏弟子が説いたものは幾らでも入っています。問題は、ある一つの教えが涅槃に向かっている方向なのか、そうではないのか、サンスカーラを制御する方向なのか、そうではないのか、それによって正しいのか間違っているのかが、仏説なのか非仏説なのかが決まります。
八正道がございますね。正見(正しい見解)に始まり正定(正しい精神統一)に終わります。「何が正しいか」とは書いていないのです。でも、あれは前後の文脈を見れば、涅槃に向かう方向が正しいのです。つまり、いろいろな道はあっても、涅槃に向かっていればそれは一つ、正しい道である。それを経典によっては応病施薬や応病与薬、対機説法と表現しますし、『法華経』では一乗と表現したのです。
あるサンガに属していれば、集団の規律――律に従っている限り、人はどのような経典を信じてもいいし、どのような経典を制作しても構いません。どのような方便を出してもいいのです。それがインドの仏教の姿でした。それによってほかの宗教とは全く違った姿、例えばキリスト教では聖書は二つ、イスラム教ではコーランほぼ一つというような限定された聖典であるのに対して、仏教では大蔵経という極めて膨大な典籍群が作られるようになりました。「八万四千の法門」と言われますように、それはどれが正しくてどれが間違っているかではない。それぞれが対機説法でありますし、強いて言えば、『法華経』の観点から見ればすべてが一乗だということになると思います。
そのような中で、在家者は出家者からの教えを受けるわけですけれども、とにかくインドにおける知の偏在というものは現代日本と比べ物になりません。知る者と知らざる者との知識の差はものすごく大きいです。例えば日本では進学率が高い。義務教育もほぼ実施されている。文盲率も低いです。そうすると、かなりの方は話せば何となく通じる。インドではそのようなことはありません。知る者は知っている、知らない者は知らない、その差はまさに激しいヒマラヤの山脈の形のようです。一方、日本は富士山のような感じです。まさに国を代表する山と同じような気がいたします。富士山は非常になだらかな感じですね。すそ野はとても広い。一方、ヒマラヤ山脈は峰がそびえ立っております。それが国民性と関係あるのかどうかはわかりません。偶然の一致かもしれませんけれども、おもしろいと思っています。
インドでは一般の人たちは仏教のことがわかりません。仏教が何を教えているのかほとんどわかりません。ただ、「あの人はどうも立派な宗教家らしい。だから儀式をやってもらえばいい」。教えを聞いたとしても、それはまさに「うそをついてはいかんよ」「悪いことをしてはいかんよ」「殺してはいかんよ」「盗んではいかんよ」というような、いわゆる日常的な話にとどまっていて、諸行無常だったり縁起だったりという話、そして一乗というような話はほぼ在家者には無縁だったと思われます。
例えば『法華経』にしても、他のどの経典にしても、インド一般で社会運動になったことはただの一度もありません、近現代を除いて。『法華経』はインドではほぼ書写行に限られます。『法華経』の、例えば五種法師と呼ばれるようなこと、中には「比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」と、在家者も含まれるような記述もしてあります。そして「クラプトラ、クラプトリー――善男子、善女人」と呼びかけて、いかにも在家者が入っているかのような記述がしてありますが、考古資料、そして歴史資料に基づく限り、残念ながらインドで『法華経』が信仰された、修行された例は書写行をおいてほかにはないと考えられます。たくさんの写本が残っています。しかし、『法華経』に則って何か人々を救おうとした動きがあったかというと、ないのです。これはやはり、社会運動をしてしまうとカーストを作ってしまう。ある意味で大乗経典というのはインドにおいては大きな夢、叶えられない夢だったような気がしています。やろうと思っても、どうしても実行できない、実行した瞬間にカーストを作ってしまう。どんなにいい教えであっても、カーストをつくることはできない。そしてインドから仏教は消えていくわけですが、はるか遠い東アジアの国、中国だったり朝鮮半島、そして日本において仏教が、特に大乗仏教が非常に盛んになりました。
大乗仏教を含めた仏教が社会運動となるのは恐らく日本の鎌倉期以降ではないでしょうか。中国においてはやはり朝廷、中国の皇帝とのかかわりが強く、余り民衆仏教という色合いは……。もちろんないわけではございません、あるわけですけれども、日本と比べて色彩が薄いように思われます。よく言われるのですが、『法華経』に関して言うと、インドで注目されたのは一乗思想。そして中国で注目されたのは永遠性――久遠実成。だからこそ、「『法華経』の久遠実成の釈尊と、『大乗涅槃経』の法身の釈尊と、どちらの永遠性が優れているのだ」「大日如来と釈尊とどちらが永遠なのだ」という議論が起きてくる。悠久の歴史を持つ中国では時間の永遠性が求められますし、カーストのあるインドでは統一、人々は平等だというところが求められる。それに対して日本では、社会運動化してくるというところ、特に日蓮聖人が自らを上行菩薩になぞらえられまして社会運動をされていく。これはインドでも中国でも叶えられなかった大乗仏教の夢なのではないかと感じています。
そのような意味で、まさにこの極東の地が有縁の地となって仏教が花開いたということはとてもすてきなことだと思いますし、感謝しております。でもそれは単に日本人が元々持っている死後の観念に乗って葬式をしているに過ぎないという側面もある……。繰り返しますが、葬式をすることはとても大事です、日本人がそれを求めたわけです。何度も繰り返しているように、人々の願いにこたえられない宗教集団であれば滅びていたはずです。日本で仏教が残ってきたということは、それが人々の願いにこたえてきたことの証しです。ただ、単にこたえるだけでよいのか。もちろん葬式以外のさまざまな活動が行われてきたわけですが、もっともっとそちらのほうをやらねばならないのではないか。そして、その中で真の意味で葬式仏教として輝いていくという道。だから、葬式仏教を離れるのではありません。葬式仏教を軸にしながら進化させていくというのでしょうか、仏教の本領発揮、単に日本人の宗教観念に乗っているだけではなく、そこに、もちろん願いですから、それを叶えることは大事ですけれども、それを軸にしながらより進化させていく。せっかく日本という国は文化的にいって仏教が本当に社会運動になっていきますし、宗教、信仰として深められていくその土壌、文化的背景があるわけです。インドでも中国でもなし得なかった、その夢というものを、日本だからこそできるのではないか。それは恐らく宗派に限らず日本仏教全体の課題ですし、逆に、できることだと思うのです。
海外などで悔しい思いをしたことがある方もいらっしゃると思います。律中心の南伝仏教から見た場合に、わたしたち日本の出家者というものは、出家者としての資格を認められません。「律を守っていない」「そもそも妻帯しておるであろう」、さまざまに言われますが、それに対してきちんと説明ができているのでしょうか。
私だったら、と言ったら何ですけれども、きちんと説明する手だてはあると思います。なぜ妻帯するのか。ごめんなさい、妻帯と言うと男中心のようですね。異性とそのような関係を持って結婚するのか――別に結婚しなくてもいいのですけれども……。いろいろ難しいのです、この問題は。(笑)
何ら差別的な意図はございませんので、よいように酌み取っていただきたいと思います。異性と性的交渉を持つ、それに対して非常に厳しい、出家者とみなされない場合もあると思いますけれども、これもやはり日本独特の善巧方便と言えるでしょうし、律中心には動いていない仏教があるのだということ。そして、仏教が社会運動として成立しているのだと。その社会の中でまさに泥から生まれて、そこで美しい花を開かせる蓮華のように生きているのだということをアピールしていく必要があろうかと思います。
◇ ◇
どうも世界の仏教の中心というと、まずダライ・ラマ一四世が出てきて……。私も尊敬している方ですが、やはり日本仏教ではない。そしてまた、仏教というと東南アジアの仏教が話題になってきて、日本の仏教というと世界の仏教を代表するような位置にはどうも置かれていないような気がして、とても残念な気がいたします。すごい力があると思いますし、それを発揮していくことによっていろいろなことができると思います。仏教では、違ったものを両方正しいのだと言えますね。それが涅槃の方向に向かっているのであれば、違っていて構わないわけです。異端だということを言う必要がない。すべてのものを応病施薬といったり、もしくは一乗ということで包含してきた。もしくは教外別伝、教えは違っても、結局一番大事なことは、「覚りに到ればいいのだ」と。違ったものを包含する知恵があると思います、仏教には。日本の仏教が持っている力が輝くことによって、日本の中で仏教というものが重きをなしていくことはもちろんですし、世界の中でも仏教が力をもっともっと発揮する時だと思います。その過程として、ますます日本の中で仏教が認知され、そして今まで持っていたよい伝統としての葬式仏教がますます深化され、そして、真価を発揮し、そしてさらに進化、デベロップしていく。三つのシンカをたどって発展していくということは、あり得ると思いますし、逆に仏教でなければできないのだと思っています。
自分のできる範囲というものはもちろん限られておりますけれども、少しでもそのようなことにタッチしたいと思っております。例えば教壇に立つときでも、私は国際文化学部というところにおりますが、仏教を専門に勉強する人はほとんどいないところです。地方の小さな大学です。そこで多様性を許容するという観点から仏教を説明すると、非常に学生が目を輝かせて聞いてくれるのです。学びたい人はいっぱいいます。そして、今世界が抱えている問題点に気づいている若者はいっぱいいるのです。何かしたいと思っているのです。でも、何をどのようにしたらよいかがかわからない。仏教が持っている価値というものは、若い人たちに、私は絶対に通じると思っています。私は私で、もちろん自坊もございますけれども、大学の教壇に立ってそのような、微々たるものではありつつ、営みを続けている者でございます。もし日本の仏教徒が一丸となってそのようなことができたら、特に若い人たち、もちろん「お年寄りはだめ」と申し上げているのではありません。どうも若い人は仏教離れと言われますが、決してそうではないような気がします。アプローチの仕方だと思います。地域の核となって、お寺で若い人たち、お年寄りも含めた若い人たち、「心の若い人たち」に対する教化をしていくことで、ますます今後仏教が栄えていくといいと思って、本日のお話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
「葬式仏教」と中世の日蓮宗
市立市川歴史博物館学芸員
湯浅 治久
こんにちは、ただいまご紹介いただきました湯浅です。
私はお坊さんの世界とは全く無縁のところで研究し、博物館学芸員という職業についているのですが、日本の中世史が専門ということで、やはり宗教の問題は避けては通れず、ほそぼそと研究をいたしております。それで、先ほどご紹介いただいた『戦国仏教』という本を日蓮宗という宗派をテーマにして昨年書きまして、そちらのほうをお目通しいただいて、このたびこのようなシンポジウムにお招きいただきました。
まことにありがたいことですが、果たしてご期待に添えるようなお話ができるかどうかわかりません。ですが少しの間おつき合いいただければと思います。そこで、私の今日のお話のタイトルですが、「『葬式仏教』と中世の日蓮宗」といたしました。早速配布した資料に従ってお話しさせていただきます。
◇ ◇
葬式仏教という言葉、私も前から存じておりましたが、このたびの趣意書の文言に明らかなように、いささか負のイメージがあるようです。これは淵源をたどってまいりますと、恐らく歴史的には近世、江戸時代の制度的な立場、寺請制度あるいは檀家制度というものに行き着きます。
すなわち、檀家制度というものは一家一寺制、皆様にこのようなことを言うのも本当に「釈迦に説法」ですが、中世以来、私の考えで言えば戦国時代以来、お寺と民衆との接触が強まってから成立していく檀家制度というものがある。そしてそれを、江戸時代になって、権力の側と申しますか、幕府が利用するような形で、庶民の支配機構の末端の役割を果たしていく、恐らくそのようなものが淵源として位置づけられるような気がいたします。
これはどのようなことかといいますと、「寺請証文」というものをお寺が発行して、ありていに言えば、その人間をその社会において認定する役割を、現代ではもちろん戸籍というものがございますが、そのようなものとして寺院が機能していくということでありまして、当然その中には寺院と人々との檀家関係、師檀関係というものが形成されるわけです。
ただ、恐らく江戸時代の師檀関係というものを考えますと、そこには「ロックイン効果」といわれるものがあるようです。これは中島隆信さんという方が書かれたご本から学んだわけですが、経済学的に言うと、選択の余地のない関係、移りたいなといってもなかなか移れないという関係をここで形成してしまっている。恐らくこのようなものが近代社会に至ってもそのまま継続している部分がある。そしてそれがある種の息苦しさの淵源になっていくというようなことがあるのではないかと思います。
ところが、今日私がお話をするような中世、平安時代から戦国時代と考えてよろしいかと思いますが、その中世の葬式や墓制、お墓の在り方を考えると、このようなものとは全く異なる状況があるようです。中世の葬送の一般のあり方を前提とすると、恐らく寺院が葬儀を行う、あるいはお墓にかかわるということはまた違った意味を持ってくるのではないかと思います。
配付した資料に書かせていただいたように、これは中世の葬送というもののあり方の一つの到達点として葬式仏教というものを考えてみるべき、ということになるのではないかと思います。近世以降の関係、ある種の息苦しさや支配の道具というものの性格はあるかもしれません。しかし、そのような支配とか、あるいは先ほども鈴木先生が少し言及されていたような「堕落」でしょうか、近世以降の仏教が「堕落」していくという話というのは、有名な辻善之助さんという日本仏教史の大家が唱えて以来、ある種の通説になっております。しかし、最近の歴史学者や宗教史研究者はこのようなものを再検討しようとしているのではないかと思いますが、私もそのような「堕落」論、その始まりとしてではなく、もっと中世における到達点、その積極的な役割を明らかにするべきではないかと思います。
そこで、手前みそですが、私の話の副題に書かせていただいたように、「戦国仏教」、本のタイトルですが、そのような考え方、とらえ方がありまして、そのような視点から考えていくというのが、葬式仏教の再評価の一つの文脈に沿うのではないかと考えました。これは恐らく主催者の皆様もそうお考えになったのかとも思いますが、今日のお話はそのようなことで、「戦国仏教」という視点からものを考えて、葬式仏教をめぐる現在の評価を相対化する一つの視点を皆様にお示ししてみたいと考えております。
そこで、今日のお話の手順を少しお話ししておきますが、まず最初に「鎌倉仏教」という言葉、これは皆様も非常に人口に膾炙する、なじみ深い概念であり言葉だと思いますが、そのような鎌倉仏教から戦国仏教という考え方の転換がどのような形で起こっているのか、それをまず考えたいと思います。それを前提にして、つぎにそこに至るまでの中世の葬送、墓制のあり方を少しお話し申し上げてみたい。これが恐らく全く異なる世界ということの中身になります。そして、そこから第三番めの話として鎌倉仏教というものと葬送とのかかわりを検討していく。そしていよいよ、恐らく十五世紀の半ばぐらい、応仁・文明の乱という乱が起こる時代ですが、そのような時代からいよいよ戦国仏教という実体が立ちあらわれてくる。そこら辺をお話ししたく思います。
そして最後に、ある意味で少し余談になるかと思いますが、中世と現代との関係を少し、勝手なお話になるかと思いますが、お話しさせていただきたいと思います。資料は三枚、A3のものをお示ししております。適宜ご参照願えればと思います。
◇ ◇
そこで早速、一、鎌倉仏教から戦国仏教へというところに入らせていただきますが、鎌倉仏教といいますと、恐らく皆様の一般的なイメージは、「鎮護国家」というような、国家のために祈るというような古代の仏教に対して、「民衆の救済」というものを高々と掲げて、そして日蓮聖人をはじめとするようなすぐれた祖師と言われるような各宗派の開祖があらわれる。
浄土宗や浄土真宗、日蓮宗、時宗、曹洞宗といったような多様な宗派がありますが、そのようなものが鎌倉時代以来躍動する。そして、それが中世という時代の宗教の最も代表的な在り方である、というものであると思います。この考え方を全く否定する根拠はございませんし、これはこれである種の本質を言い当てていると思いますが、現在、歴史学の中で仏教史あるいは中世史を研究しようという人たちの集団にとっては、実はこの鎌倉仏教という立場から研究を行うような人は余りいないのです。
顕密仏教という言葉があって、実はそのようなものが中世において主流であるという考え方が一九七〇年代の半ばぐらいに提唱されたのです。黒田俊雄さんという大阪大学の先生がそのようなものを提唱いたしまして、顕密仏教あるいは顕密体制論というものを提起しています。
その中身はどのようなものかと申しますと、伝統的な八宗、先ほどもお話がありました南都の六宗、三論や成実や倶舎というような、皆様もうご存じのものですが、その南都の六宗と、それから天台宗と真言宗を合わせて八宗というそうですが、それがある意味で、中世的な転換を遂げていく。そして、中世の主流な仏教の体制になっていく、という話です。
それはいかなるものかというと、何というのでしょうか、古代仏教から中世仏教へ転換点として確認できるところは十世紀と言われているそうです。十世紀というのは九〇〇年代ですね。関東では平将門という人が反乱を起こす時代です。この時代は律令体制というものが破たんする。国家的な体制が破たんする。そうすると、国家や地方を問わず財政が破たんしていくわけです。
そうすると、それ以前から国家によって保障されていた、実際にいろいろな田地や物を供給されていた古代寺院がそのままでは立ち行かなくなる。そこで彼らは、ある意味では今の時代の大学のようなものかもしれませんが、規制緩和ということで、自分たちの自立の道を模索するというようになるようです。逆に言えば、生き残りをかけていく。そこで行われているのが個人や来世の祈りという領域に積極的に官僧が進出していくということでありまして、折から成立していく貴族社会――天皇だけではないところがミソですが――貴族社会に密教や浄土教というものが盛んになっていく、というものが一つの道筋です。
また、このようなものは実は民衆自体にも及んでいくわけでして、やはり十世紀でしょうか、尾張国の百姓らが国司である藤原元命という者を排斥するような申状(訴状)を出す、というような動きがあります。これは現在の住民リコール運動のようなものでございまして、国司という支配者がそのような形で排除される。この時期に仏教界で明らかになるのは悪僧という人たちの動きでして、この悪僧たちが活躍することによって朝廷への強訴といわれるようなものも積極的に組織をされるようになる。
そのような中で比叡山あるいは高野山というものに代表される、あるいは南都でしょうか、巨大な寺院が積極的に荘園というものを自らのもとに取り込んでいく。そのことによって宗教権門、非常に巨大な宗教的な勢力として自立していく。それが十世紀から十二世紀ぐらいの時代の仏教の動きであったというのです。
ポイントになるのは、その中で、例えば鎌倉仏教がお得意としている民衆の救済、易行というのでしょうか、お題目を唱える、お念仏を唱える、方便と申しますか簡単な行いで、救済を行える。そのようなものが、鎌倉仏教の時代から始まったのではなく、実はこの顕密仏教の中でも行われていたのだということがわかってまいりました。そのような形で祈祷やあるいは治病――病気を治すような祈祷をもって積極的に民衆に入っていくという動きも見えるようです。ただし、これはある種の支配の体制、国家の体制ということで、最終的には国家がそのようなものを組織して、民衆を支配する方策となっております。例えば年貢を払わなければ「地獄に落ちるぞ」、というような形で呪縛をするということで、この顕密体制は非常に強固な支配体系の理念であった。最終的にはそのようなことになるようです。
では、そういう中から、どのような形で鎌倉仏教あるいは戦国仏教が出てくるのかということですが、鎌倉仏教はその中で祖師たちが革新的な思想をもって変えようとするわけですが、残念ながら、それが全般的な民衆や武士や貴族たちに受け入れられることには至らなかったということになります。そこで、それが本来的に民衆あるいは社会に受け入れられていく過程を考えなければいけない。そのようなことで、戦国仏教という研究概念が提起をされてくるわけです。
それもやはり早い段階からありまして、一九七〇年代の半ば以降、京都の藤井学さんという方が日蓮宗の研究をされておられますが、そのような方が戦国仏教という概念を提唱されている。その中では、顕密仏教、顕密体制が、王法と仏法というものが相互依存をして成り立っている、お互いにもたれかかっているという考え方がありまして、王法仏法相依論というのですが、それに対して、実は仏法のほうが上であるということを日蓮聖人の教典類から導き出し、戦国仏教という考え方を提唱していった、という研究の経緯があります。
そこで、室町から戦国期の研究の中で私たちの共通の認識でありますのは、一向一揆、真宗の民衆運動でございますね、一向一揆であったり、あるいは京都で行われた天文法華の乱というような非常に激烈な運動がありました。ただ、私自身は、そのような運動を認めると同時に、恐らくそのような頂点を考えるだけでは社会に宗教が敷延していくことはとらえがたいのではないかと考えまして、むしろ日常的な生活や現実の人々の営みというものでしょうか、なかなかそのようなものを抽出するのも難しいのですが、そのような目線からこの戦国仏教の成り立ちを考えてみたいと思ったわけです。
資料にも書きましたように、伝統的な八宗というものがその後、秀吉の時代の千僧供養、大仏供養というのがありますけれども、ご存じのようにさまざまな軋轢があったわけですが、この中世末期に至りますと、南都六宗と天台、真言であった伝統的な八宗が、真言であり、天台であり、律宗であり、禅宗であり、日蓮宗、浄土宗、時宗、一向宗という、まさに鎌倉仏教を担ってきた各教団が秀吉に認められてこの八宗に取ってかわっていくという動きがあるようです。そこら辺を見ると、中世の前半であります十世紀から十二世紀に対して、恐らく十三、十四世紀から十五世紀にかけて新たな変革が起こってくる。そして、それが戦国仏教というものを、日蓮宗だけではなくて全体として形作っていく。そのような動きがあるのではないかと思うわけです。
◇ ◇
では、戦国仏教の特色として幾つか私が考えたことを述べさせてください。一つは、シヴィアな社会を生き抜くという視点です。これは中世、特にその後半が非常に社会環境、自然環境としてシヴィアな時代であったということが歴史学の中でかなり明らかになってまいりました。皆さんご存じのように、文応元年(一二六〇年)、日蓮が『立正安国論』を前執権北条時頼に献呈いたしますけれども、これは直接のきっかけとしては、正嘉というやや前に起こった大地震、その地震の様を見て、日蓮が現世を救済しなければいけないという思いを深めた。『立正安国論』の冒頭にあるような、あれは鎌倉の悲惨な状況だと思いますが、「骸骨路に充り」というような、巷に死体がごろごろするようなことは、正嘉の地震あるいは災害によって起こされたものであるということが言われてきたわけです。しかし、実はこの災害や地震の史料をいろいろ集めて分析いたしますと、これは藤木久志さんという戦国期研究の大家の方がおよそ二万件近い災害記録類をピックアップしてデータベースを作られる、高志書院というところから本が出ておりますが、それを見ると、実はこの十三世紀を限って見ても、冒頭から終わりまでかなりさまざまな災害や地震というものが列島のどこかで起こっていたことが明らかになったわけです。つまり正嘉だけではないということです。
そしてまだ十三世紀は断続的であったものが、十四世紀を挟んで十五世紀は長期的な寒冷化の時代を迎える。つまり寒くなるということです。現代は暖かくなると大変だと騒いでおりますが、やはり、実は暖かいのも大変なことになっていったりするのですが、前近代社会においてはこの寒冷化というものが決定的な難しい問題を引き起こします。そして、十五世紀には長雨や長期的な寒冷化の中で、飢饉や災害がそれこそ日常的なものと化すと言われております。それを考えると、この戦国仏教が目指したものは、そのような悲惨な生活世界に入っていくこと、そして宗教がそこで定着すること。ありていに言えば、私も少し書かせていただきましたが、社会的な保障システム。その中身は具体化するのはなかなか難しいのですが、そのようなものの構築を目指していたということも考えられるのではないかと思います。
資料にも書きましたように、一つには民俗との習合というようなものがございます。つまり庶民が何を願って――先ほどの鈴木先生のお話ではありませんが――いるのか、そしてそれに対してどのような答えを出していくのか。そのようなことを必死に考えていく、そういう時代なのではないかと思います。
私の本の中で『常在寺衆中記』という十五世紀の記録、一〇〇年に渡る記録を分析した部分があります。常在寺というのは河口湖畔にある日蓮宗の寺院だと思いますが、ここに一〇〇年間の記録があるのです。これを見ると、一〇〇年間に二十回を超える飢饉があり、その飢饉によってさまざまな人が倒れていく、そのような様子が書かれています。
しかし、この記録でより興味深いのは、実はそれと同時に世間が富貴、豊かになるということも書きとどめていたり、そのところの作物で何がとれる、あるいは何がとれない、今年は作柄が悪い、よいというようなことを日蓮宗の僧侶が克明に書き継いでいる記録であるということです。
また、銭というものが鎌倉時代には非常に重要なものになってゆきますが、その銭が枯渇してしまう。うまく流通しないのです。そうするとたちまち物が高くなるという、現代でもあり得る話ですが、そのようなことを詳細に書きとどめていく視点が生まれてくるわけです。これはやはり生活者の目線に立って僧侶たちが生活している。その中で寺や堂や庵を建て、そしてそこで岡宮の光長寺という、ご存じの三島の有力寺院の貫主を迎えて出開帳をするというような動きを見せていたりすることがあります。これが民俗との融合ということかもしれません。
◇ ◇
それからもう一つやはり重要なのは、葬送への関与というものです。これも本の中で紹介させていただきましたが、千葉県松戸市に本土寺という大きな寺院がございます。ここには十五世紀から近世に至って書き継がれている過去帳が存在しておりまして、私たち地域史を研究している者にとっては非常に貴重な史料でして、皆様もご存じかもしれません。
これを分析いたしますと、やはりほかの記録でわかるような飢饉や災害のときには、グラフを書いたのですが、死者がはね上がるのです。非常にふえていく。それから、その死亡の季節を分析すると、要するにどの月に一番死んでいるのかということだと思いますが、これを分析された田村憲美さんという方によりますと、一番人々が飢えるのは春先なのです。要するに米がとれない、端境期を越せない。春を越して夏になると麦が実ります。麦秋という季節には、ご存じのように麦ができるので一息つくのですが、それまでの春を越せない状況が書かれている。これは河口湖の寺院の記録でも「春詰まる」とか「春飢える」とか、そのような言葉が頻繁に出てまいりまして、どうやら中世の劣悪な生産状態といいますか、生産力のなせるわざかもしれません。そのようなことがわかってくる。春を越せずに人々が亡くなっていくということがあるようす。
ただし、ここで過去帳に結縁をしているような人々は葛飾地域の中でも恐らく土豪クラスの有力な人々であると言われています。そのような人々、農業をし、商業をし、有力者として土地に息づいている人たちでさえも、春を越せないということがある。
そして、一番興味深いと私が思ったのは、そのような死亡の季節が、近世になるとそうではなくなるのです。春は越せるようになる。それはやはり近世の生産力が上がってくるということだと思います。それに対して、天明など江戸時代も飢饉が襲います。実はそのときの過去帳を分析いたしますと、中世の過去帳と同じになるのだそうです。つまり、江戸時代の飢饉の状態が中世の日常であったのです。そのような厳しい社会、われわれには想像を絶するような社会の中で、葬式仏教というものが生まれていく。やはりそのことの大きさは考えるべきではないかと私は思うわけです。
そして、それと同時にこの十五世紀から以降というものは、基本的な生活の単位、私どもが生きている……と言うのはちょっと語弊がありまして、最後に申し上げますが、私どもが生きてきた村や町というものはもう最終的な解体過程に入っているような気がいたしますけれども、とにかく江戸時代を生きて昭和という時代までは辛くも生き残っていた共同体的な社会、村や町の社会というものが歴史的に確実に生まれてきてわたしどもの目にとまってくるようになるのが十五世紀半ばであるという研究があります。これは私もそのような論点に立っていろいろな研究を行いまして実感を持っていることですが、やはり先ほど申し上げた応仁の乱以降、われわれの感覚でわかるような共同組織が生まれてくる。
では「その前は何なのだ」と言われるとなかなか難しいのですが、あるにはあったのですが、恐らく密度が低い。村、集落というものを考えれば、昔の集落というのはまばらだったのです。昔というのは十五世紀以前。散村と申します、あるいは疎塊村といいまして、固まりがある。実はそのような村も今でもあることはありますが、おおむねそのようなものが主流であった。それが十五世紀半ば以降になりますと、集村化としてガチッと固まるようになるのです。
もうおわかりのように、高校の教科書などでいう惣村というようなもの、惣というものが生まれてくるということですが、昔はこれは関西あるいは京都の周辺の現象だといわれていたのですが、どうもそうではない。そうではなくて関東や東国、東北、そのようなところでもそれなりにそうした集落が動いてくるということも最近の考古学――地下を掘る学問ですが、考古学によって明らかにされているようです。そして恐らくそのような動向と、戦国仏教の動きというものが連動するのであろうというのが戦国仏教の考え方の一つの根拠になると私は考えているわけです。
◇ ◇
さて、それでは、そのような社会が生まれる前、恐らくそれが中世の一般的な姿と考えていいのですが、そうした社会のなかで葬送はどのようなものであったのかということを二としてお話し申し上げたいと思います。
しかし、この葬送や墓制の研究というのは歴史学の中でも非常に大きな蓄積がありまして、なかなかすべてを把握するわけにはいきませんし、私も非力であるわけです。しかし最近、レジュメにも書きましたように、佐藤弘夫さんという東北大学の先生が、『死者のゆくえ』という大変興味深い本を書かれておりまして、これを拝見すると非常によく説明することができると考えまして、今日はその三段階の把握というものを皆さんにご紹介して、その中で中世の葬送について考えてみたいという章を設けました。佐藤さんのお書きになられた本の中の図を最後のページにつけておきましたので、これを適宜参照しながらレジュメもごらんいただきたいと思います。
佐藤さんはどのように言っているかということですが、まず、古代から十世紀ぐらい……十世紀から十一世紀ですか、そのぐらいまでの間の葬送や墓制の在り方。そこに書きましたように、「遺骨に対して全く関心を払うことなく、遺骸を放置して顧みなかった古代の人々」ということを言われています。これに対して十二世紀以降、院政期と申しますから、皆様の中では末法思想がはやる時期という認識の方も多いと思いますが、この時代になりますと、「火葬骨を大切に霊場というところまで運んだ中世の人々」という区分をしていらっしゃいます。
それに対して江戸時代ですが、「墓を作って骨を納め定期的に墓参りを繰り返した近世以降の人々」と。これは恐らくそれ以降近代に至っても通底する考え方だと思います。そして現代。「遺影を部屋に飾る現代人」とあるわけでありまして、このあたりは私の後にお話しされます小谷先生の分野かもしれません。
このような三つの段階を経て戦国仏教の時代が生まれるわけですが、若干その中身について解説しておきますと、大きなポチの下に少し書いたものを読ませていただきますけれども、平安時代半ばまでには天皇や貴族、高僧などのごく一部の人を除いて、墓が営まれることが基本的にはなかった時代であるというのです。ましてや庶民は風葬や遺棄ということに甘んじている。そこで放置されている遺体はそのままになり、そして墳墓自体も忘却される。つまり追善供養のような墓参りがなされないということです。
例えば十二世紀に成立した中世の絵巻物である『餓鬼草紙』というものあります。これはおなかが大きくなった餓鬼がお墓のあたりで骨を食べたりしているというおぞましい絵巻ですが、あの世界です。で、そのようなものは古代人の死生観が反映していると。魂の重視と裏腹の肉体の軽視があり、死者の魂は鎮魂自体は施されるのですが、それを施された後、身近にある他界――これは他界観念というものが一つのキーワードになっておりまして、身近にある他界にとどまる、非常に身近なものであるという観念があります。やがて古代国家というものが始まり、神となる死者が出てくる。そしてその頂点に立つのが天皇の霊ということになり、古墳のような造立が行われることになりますが、私はこの辺はよくわかりませんので省略いたします。
これに対して十二世紀、霊場が各地に生まれる。その霊場に骨を納めることによって往生するという観念が広がってゆきます。これは何といっても代表は高野山であるわけでして、このような霊場が各地にできる前提には彼岸世界というものが拡大するという動きがあります。すなわち霊場や霊地に行けば極楽往生が約束される。そこで庶民も含めて人々はそこに納骨を積極的に行っていくことになる。
そして、そのような思想が最もミニチュアな世界にあらわれているものが供養塔の一つ、板碑というものだと佐藤さんは言います。板碑というのは、ひょっとしたら皆様のお寺にもご所蔵されているかもしれませんが、いわゆる緑泥片岩という青石で作った薄いお塔婆です。私も昔そのようなものを集めて、企画展などをやったことがありますけれども、市川にも三〇〇基ほど、数えたらありました。このようなものを建てることによってそこをミニチュアの霊場としていく。そしてそのような作善をすることによって往生を願うということでして、さまざまなミニチュア、ミニ霊場というものが展開していくという動きがあるそうです。
そして、納骨信仰がやがて衰退をする。板碑自体の衰退がほぼ十五世紀いっぱいということでして、昔はよく戦国大名があのようなものは忌まわしいのを捨ててしまったという話がありましたが、実はそうではなく、社会の観念、考え方が変わってきたということ思います。そこの中で墓標がその中に入り込んでくる。それと同時に、社会の観念が変わったことのあらわれですが、他界観念というものが縮小化し、他界浄土というものに対するリアリティーが衰退していく。この中で現世利益というものが正面から論じられていく動きになるのだそうです。
その中で初めて墓所、墓ですね、そしてそのお墓を持った市中寺院というものが村や町の中にあらわれてくる。すなわちこれが十五世紀半ばの大きな転換であり、その主体となるものが庶民層にまで広がった家であったということになります。戦国仏教の段階に至る前の葬送の実態を若干書いておきましたが、先ほど申し上げたように、風葬や遺棄というものが一般的でありまして、葬式というのも上層部を除いてなかなかされていなかったのは言うまでもありません。
そこに対する一つのキーポイントとして、葬送に対する僧侶の関与というものがあります。松尾剛次さんがよく書かれていることですが、顕密仏教自体の葬送観というものは死穢を遠ざけるというもので、「国家的な受戒を行った官僧」と松尾さんは言うのですが、そのような正統な僧侶は葬送には関与しないというのです。死穢にはさわらないという話になるようです。
◇ ◇
では、先ほどの鈴木先生のお話ではありませんが、誰が実際の葬送を行うのか。さまざまな局面がありますが、それは聖あるいは遁世僧というある種の僧侶の集団です。こうした人々が国家が認定した官僧に成り変わって行っているようです。
これは穢れというものに対する中世の観念といいますか、そのようなものが非常に大きな影を落としているのだと思いますが、その中で、例えば真言律宗といわれるような宗派が中世では奈良、大和の叡尊や忍性という人々が起こすわけでありますが、鎌倉にも下って非常に大きな力を持ちます。その中ではやはり上層部の僧侶は葬送にはかかわらず、「斎戒衆」というような下層の僧侶を組織して――その人たちは聖系の僧侶だということですが――そのような人たちが葬送を行うプロ集団として分離していくような動きもあるようです。
こうした人々の中で一番多く葬送にかかわる人たちは浄土宗あるいは念仏宗の僧侶でして、そこに書きましたように、ご存じの源信から始まる浄土宗、浄土教の考え方があり、天台宗から浄土教へ流れていく葬送仏教の淵源の『往生要集』に書かれている二十五三昧講あるいは三昧僧というものが生まれてくる。彼らがさまざまな動きをとりながら、例えば十三世紀以降は法然浄土教に習合していくという動きがあるようです。皆様ご存じのことだと思います。
ところでこのような中世の段階の墓や葬送の在り方を最もよく体現する「場」として、中世都市というものを挙げておきたいと思います。都市というもの自体はある程度普遍性があると思いますが、穢れを拒否する、または穢れを排除する場であると言えるかと思います。
すなわち都市のど真ん中に死へのけがれや墓というものを作らせない。例えば鎌倉幕府の法令にもそのようなものがあります。そうするとどこにお墓ができるかといいますと、都市の周縁、端っこのほうにできるわけです。例えば京都、これはご説明するまでもなく、鳥部野や蓮台野、そして化野というところでして、やがてそこに寺院ができてくる。そして鎌倉ですが、この池上にも身近な鎌倉ですが、鎌倉の周縁にもやぐらというものがございます。
ご存じのように、鎌倉の固い岩盤をくりぬいて、そこに五輪塔や火葬骨などを入れるというお墓であります。あのような形でやぐらが形成される。多いのは、そこに書きましたように極楽寺の周辺、律宗の拠点ですね。地獄谷という名前があるような葬送の場であった。あるいは、日蓮聖人が鎌倉にやってきた場所であります名越、あそこも葬送の場である。そして、最も大きな鎌倉の葬送の場は由比ヶ浜のあたりの浜です。あの浜には数千体といわれる人骨が中世に眠っていて、集団墓が形成されている。あるいは、あそこで処刑とか、あるいは都市の中で出た死体をあそこに集めたりした場所でした。発掘、考古学の成果でそのようなことがわかっております。
また、もっと周辺に目を向ければ、六浦というところが横浜の金沢区にございます。金沢文庫などがあるところです。あそこに日蓮宗の上行寺という寺院がありますが、その裏山でかつて一九八〇年代に上行寺東遺跡というものが発掘されました。岩盤をうがってお堂の施設があり、それは恐らく骨堂、あるいは無常堂といわれる墓堂であり、お骨を納めるそのような周縁の場があったということで、遺跡を残したいということで中世史研究者は大分動いていたのですが、残念ながら破壊されてしまいました。
このようなものを総称して、先年なくなられた東京大学の石井進さんという中世史の大家がいらっしゃいますが、一九八○年代に石井進先生はこれを「都市鎌倉の地獄の風景」という印象的な言葉で論じておられることをご紹介しておきます。
また、地方都市として静岡県の磐田市というところがあります。ジュビロ磐田の本拠地で有名ですけれども、あそこではやはり一の谷中世墳墓群が発掘されました。磐田は遠江国の国府でして、やはり国府というのは地方都市として大きな意味を持っています。その北側の外れの丘陵地帯を宅地造成しようとして掘ったときに、非常に多くの、多分何百体……千までいったかどうか、土まんじゅうのような墓、あるいは集積墓という、供養塔のメモリアルなものがない、まさに中世の葬送の在り方の一つと言っていいと思いますが、そのようなものがたくさん出ております。そこではやはり永代の供養がされていない。だからこそ忘れられて、おそらく中世後期にはそのところが荒れ地になっていったわけです。
このように、中世都市といわれるものが、自治都市としてある種の自由な風を呼び起こすというようなことを言われたこともありますが、その中世の都市のど真ん中には墓は営まれなかったということをご記憶いただきたいと思います。
◇ ◇
さて、先を急ぎますが、三では鎌倉仏教と葬送ということで議論を立てたわけですが、やはりここでも聖や遁世僧というものが活躍して、そこにある意味では鎌倉仏教の祖師の皆様も系譜として位置づけられるということを論じたわけです。その中で、少しはしょりますけれども、日蓮の場合は、出世間主義というのでしょうか、やはり世俗とは一定の距離を持って修行し、信仰するという立場を貫いたということが高木豊さんなどによって言われていたと思いますが、これがやがて弟子たちの中では現世主義へと傾倒していく。現世主義へと継承していくというのは、やはりある意味では括弧付きですが、「堕落」という文脈で語られる場合もあります。
ですが私の場合は決してそうではない、むしろ生活世界に近づいていく一つの過程であるとも見ることが可能ではないかと位置づけたのであり、そのような動き自体は間違いなく存在すると考えております。いわば、仏教的な福徳一致思想から経験的な福徳一致の思想へと、現世利益が梶を切っていく。その中でキーパーソンとなるものが有徳人という存在です。
これを端的に言えばお金持ちのことです。しかし、この徳というものは、経験主義的であれ仏教主義的であれ、「徳が高い」の「徳」を含みますので、単なる拝金主義ではありません。有徳人というお金持ちたちが仏教を積極的に受容していくようになる。それが一つの社会の動きの結節点になるようです。
恐らく鎌倉仏教自体は祖師の思想を受容するという中において、原理主義や改良主義、その両方を持ちながら社会に浸透していく、そのような機能自体が結果的に見てその強さの秘密であったのではないかということを本の中で書かせていただきましたが、当たっているかどうかわかりません。そしてやはり、律宗や時宗、禅宗、浄土宗というものも日蓮宗に劣らずそのような性格を含め、有徳人をつかまえていく動きを持っていく。そして、ここが重要なところですが、恐らくそれ自体は顕密仏教といわれている真言や天台あるいは南都の仏教も同じなのです。やはりその中に、恐らく近世以降の日本仏教といわれるものの形成の萌芽があるのです。
たんに顕密対鎌倉というような「対立の構図」ではなく、中世史の学会はどうしても対立の部分を強調しますし、私自体もそれに引きずられて、あれかこれかというような議論をいたしましたけれども、しかし、多分そうではない。それらが恐らくそれぞれに変わっていく、というのがもう一つの大きなポイントであるのではないかと思うわけです。
◇ ◇
時間も余りなくなってまいりましたので、資料の四に入りたいと思います。有徳人というのはお金持ちであり、徳も持っているのですが、残念ながら身分を持っていません。十二世紀の『信貴山縁起絵巻』という、これも「鳥獣戯画」とあわせて国民的な絵画であるといわれている絵巻があります。朝護孫子寺に命蓮という修験者、念者がおりまして、それが蔵の中のお米を飛ばしたりするという、贈与の問題に興味がある私には別の意味で非常におもしろい絵巻ですが、その中にも実は山崎というところの徳人が出てくるのです。町場の有徳人がすでに十二世紀から寺院を支えているわけですが、その有徳人は「下種徳人」といわれています。
「下種」は「げしゅ」あるいは「げす」と読むのでしょうか。先ほどの鈴木先生のお話ではありませんが、そのような種姓(カースト)観念に基づいたある種の人間の差別的な呼称だと思いますが、身分的には低いながら、そのような人たちが宗教や宗教者を積極的に支えていく動きがやはり中世を通じてあることを示しています。それが満面開花していくのが戦国仏教、十五世紀の時代であると考えたいわけです。
資料の四の最初には、「菩提寺の時代」と書かせていただきました。まさに最初にお話し申し上げたような江戸時代につながる菩提寺の思想がここで出てくるということになるわけです。
葬式仏教あるいは近世も含めた仏教の、大変大きなお仕事をされている圭室諦成さんという方が一九六三年に『葬式仏教』という本を書かれておりますが、この中で十五世紀半ばから十七世紀半ばの二〇〇年に、現在の寺院のほとんどが勃興している。さらに言うと、十六世紀半ばから十七世紀半ばの一○○年間に多いということは、実はその圭室諦成さんのお子さんでいらっしゃる圭室文雄さん――私もちょっと院生時代に習ったことがあるのですが――のご著書でいわれております。二〇〇年か一〇〇年かは難しいところですが、いずれにしろこの時代が現代につながる寺院ができてくる非常に大きな変革の時代である。これは議論をまたないわけです。
その中で市中寺院というものが、先ほど申し上げたように出てくる。積極的に都市の中にも墓が営まれるわけです。これは京都などで高田陽介さんがよく言われていることでして、たとえば都市鎌倉の中でも、やぐらや周縁の墓地が不明確になっていくのと裏腹に、名越に日蓮宗の寺院ができてくる。長勝寺とか安国論寺など今も存在しますが、そのような寺院の中に境内墓地が出来てゆく。発掘するとそのような墓地が出てきます。そして大町でしたか、本覚寺という日蓮宗の本山がありますが、そこには夷堂があったりして、まさに福徳思想を背景にした日蓮宗寺院が積極的に出現していく。そのような時代がやはり戦国時代であるということになるわけです。
そして、そこで行われている葬送や追善については、これも膨大な研究がありまして、いろいろと参照することが可能かと思いますが、先ほど申し上げた高田さんの研究を参照いたしますと、例えば地方にもある。備前国牛窓の本蓮寺であったり、あるいは、美濃国平野の龍徳寺という禅宗であったり、京都の浄福寺という念仏宗がその実態をよく追うことができます。
これは古文書、歴史の史料が大変多く残っている寺院でして、それを逐一、史料をこつこつと分析いたしますと、確かに京都から地方都市に至るまで、あるいは地方の村に至るまで、境内に墓地を伴ったお寺がたくさんできてくるということ事実があります。これを高田さんはトップモード、当時のモダンな思想そのものである、あるいは斬新な寺院の経営方法であるというような現代的な言い方をされておられますが、ある意味ではそのような点もあるのかもしれません。
ただ、江戸時代とは違って戦国時代の一つの特色として指摘しておかなければいけないのは、僧侶の関与や檀那の立場というものがそれ以降の整然とした形のようなものでは決してなかった。むしろシヴィアなとり合いの世界であったということです。例えば私の本の中で、日親、十五世紀の偉大な僧侶だと思いますが、日親の書かれた『折伏正義抄』を見ますと、千葉の千田庄(多古町)のあたりは本寺と末寺の僧侶が檀那をとり合っている、檀那をつかまえ、檀那にするということをさまざまな立場の僧侶が争っているさまを「見苦しい」と書かれていたと思います。
◇ ◇
一つだけ異なる史料を今日提示したいと思って持ってまいりました。三枚めの史料をごらんいただきたいと思います。三枚めの右の下のほうに、能永寺という、これは今の横須賀の追浜の近く、深浦というところ辺りにある時宗寺院ですが、そこの古文書をあげておきました。
これは永正十三年といいますから十六世紀の初頭の一五一六年。そのときに相河というこの周辺に非常に多い氏族の名が出てきます。実は戦国時代の相河というのは、この追浜あるいは六浦や瀬ヶ崎というあたりに大変に多い名字でして、対岸である房総の富津の方面にも分布していることから、江戸湾を経めぐっていた商人ではないかという説もありますが、その人たちがお寺とどうかかわっているかを示している大変に興味深い史料なのです。
若干読ませていただきます。「われらのことは」と書いてあります。「富岡のほうりう寺の旦那に候らえども」、富岡という地名もございます。そこの「ほうりう寺」という寺の旦那だったのが、「三人の者一度に死に申し候へは」、これは恐らく時代的に北条早雲の引き起こした戦乱によってこの相河の一類が死んだのではないかといわれています。で、そうしたらどうなるかといいますと、「富岡のほうりう寺、いのちのありて檀那ほしく候とて、御すて成され候間」というように、「いのち」が欲しいのだと寺院に言われたというわけです。この「いのち」というのは恐らく生きている檀那が欲しいのだということで、おまえたちは随分亡くなったのだからうちから出ていってくれという、非常にシヴィアなことを言い出されてしまったわけであります。「お捨てなされ候」ということですね。「そのままりゅうけんし候」というのは難しいのではしょりますが、「さまざまに合点なくて」、いろいろな寺院に檀那にしてくれと頼むわけです。金沢六ケ村の寺に頼んでも、「いのち大事とて合点なく候」。ほかの金沢のお寺に頼んでも「いや、あなたたちは亡くなった方ばかりなんで、ちょっと檀那には遠慮してくれ」と言われてしまうというようなことが書かれています。
その後、この相河氏は上行寺に行きまして――先ほどお話しした六浦の日蓮宗の上行寺ですが――ここでもやはり断られてしまう。そして最後には深浦、浦之郷にあるところの自得寺に頼んでもだめで、能永寺に行ってようやく何とか入れてもらえる。そのときには能永寺さんの数田、あやべ、すずきなどという檀那の方々にもいろいろやって、何とか入れてもらった。ですから、その後は、われわれは嫁をとりても、婿をとりても能永寺の檀家であるということを誓約しているのがこの文書であると思います。
つまり、近世以降のある意味で制度的に定まる以前の檀那関係というのは、お寺や檀那それぞれの環境や思惑がはらんで、大変にシヴィアな動きをしている。とり合いの世界である。きれいごとを言っていられないというような、戦乱で亡くなったとき、財力が落ちていたときには容赦なく寺院を追い出されてしまうというような動きがこの史料から伺えるわけです。
◇ ◇
そうした中で、町場や村の寺院が積極的に有徳人の財力を頼み、そしてさらに共同体を形成して、その共同体の中に寺院を受容させていくという動きが戦国仏教の動きとして確かに追えるようです。これはたとえば岡山の牛窓の本蓮寺の動向に明らかです。
ここにもたくさん史料がありまして、分析しやすいので本で書かせていただきましたけれども、この本蓮寺の場合は、最後の今ごらんいただいた資料の左側のほうに、牛窓本蓮寺の場所の図を出しましたが、瀬戸内海の今は風光明美な湊町、非常にいい場所であります。また石原氏という大檀那がいて、まずはそこに頼っていくのですが、いろいろ古文書を見ますと、やがてその牛窓港の中腹にある小高い丘に墓地を形成していく。これに対して住民が寄進ということで、田地を寄付したりして墓地を作っていくさまが非常によくわかるのです。
この地図で言えば本蓮寺上とか本蓮寺北とか、そのようなあたりが墓所だらけになっていく。残念ながらその写真を載せておくのを失念いたしましたが、大変に風光明媚、つまりとてもいいところに立つわけですが、そのようなロケーションを持つところに積極的に墓地を作っていく。
そして、有徳人石原氏だけではなく、牛窓港の住人をそこに葬っていくという動きがある。このようなロケーションのいい墓地を中世では勝地と申しまして、非常にいい場所にやはりついのすみかを作る思想があるそうですが、このようなものは、例えば私の勉強しております中山法華経寺の近くに二子というところがありますが、ここが二子浦と呼ばれた浦であって、日蓮が鎌倉に向かって船出したという伝説があります。この二子には多門寺というお寺がありますが、その裏のほうにも非常に段状になってお墓が密集しております。皆さんのお寺もそのようなところが多いのではないかと思いますが、そのような似通ったロケーションのところに戦国仏教が根をおろしていくという動向があります。
そしてその中では、若干興味深いと思ってご紹介しておきましたが、牛窓では牛王宝印という中世の呪符・お守り札を檀家さんに配って、港町に張っていただいているという動きがある。これも民俗との融合という視点で考えることができます。あるいは、その上のほうにご紹介したのは、市川市の大野というところの日蓮宗寺院のロケーションを示した地図です。若干見づらくて恐縮ですが、本を読んでいただければわかりますように、集落の核となるような寺庵、寺院が十五世紀になると確実にここにあったということがよくわかります。フィールドワークという研究の方法で、てくてく歩いたりすると、このようなこともよくわかってまいります。
その中で、浄光寺という寺院の土地では村の方たちが、写真を出したように、田植えを手伝う。この田のお米を食べるとよく乳が出るという評判が立ちまして、運慶にまつわる乳なし仁王という伝説があるのですが、そのようなものとして寺院の土地が息づいていく。その上は浄光寺のご祈祷の姿をあらわした、これは両方とも明治時代の絵はがきです。このようなこともやはり生活への定着ということを伺うことができます。
以上申し上げたように、私のお話自体は、恐らく何よりも中世の仏教というものが集団によって受容されていく、鎌倉仏教というものは確かに思想的には個人をターゲットにし、個人の救済を目指したものであったことは事実であるけれども、実は歴史的に見るならば、そのようなものは集団、共同体によって受容されていく。その共同体が非常に強い、シヴィアな環境の中で強い力を持っていくのが十五、六世紀である、それが戦国仏教の基盤となるということをお話し申し上げたわけです。お話の中身として、歴史的なことは以上です。
◇ ◇
最後に「おわりに」に入らせていただきます。あと五分ほどございますので、もう少しおつき合いいただければと思います。
「中世と現代」、と書きましたが、先ほど申し上げたように、中世に形成されたこのような戦国仏教のもとにおける葬送仏教あるいは村や町というものが、死滅しつつあり、決定的な変化を遂げているのが現代であると言っていいのではないかと思います。
これは恐らく歴史学だけではなくさまざまな学問分野や社会運動の分野で共通の認識ではないでしょうか。その中で、寺院や寺院をめぐる環境自体が激変していくのも当然です。
世代間ギャップと書かせていただきましたが、例えば私自体は四十の最後の年でございまして、私の上のほうには恐らく六十前後のいわゆる団塊の世代の方たちが社会を動かしている時代。この方たちは高度成長の中で目いっぱいお働きになられて、すごくアクティヴな動きをされた方たちです。私の世代は恐らくそれにつながる高度成長時代のしっぽを知っていながら、それが最後にはじけてバブルになって、その後急速に転換していくという時代の変化、そのようなものを非常に肌で感じた世代だと思います。これはひょっとしたら今日演壇に立たれた先生方も同じなのではないかと思います。
それに対してわれわれよりも十~二十年ほど若い世代、第三世代ということですが、この人たちは高度経済成長自体を知りません。さまざまな分野がございますが、わたしの知っている研究者の仲間でも大変にシヴィアな状況で、なかなか就職できないとかそのような話もありまして、余りいい思いをしたことがない世代。そして、それよりさらに下の若い人たちは、例えばそのような研究者を見て、研究自体やっていけるだろうかと思っている世代です。歴史学などでもやる方が減っているということを友人の大学の教員の方々に聞く場合が多いのです。もちろん博物館も例外ではありません。この先どれだけやっていけるかはわかりません。
というように、戦後という時代を見ても大変に大きな変革の波がいろいろあって、世代がちょっと違うだけで共有できないものが大変多いということを実感するようなことが最近多かったわけです。恐らくそれに対して人間がとれる一つの方策というのは、そこに書きましたような新たなコミュニティーづくりということにやはりなっていくわけです。
例えば広井良典さんの『コミュニティを問いなおす』という本がありますが、そこに書かれているように、これからは新たなコミュニティーづくりというものが必要になっていく。これは恐らく、わたしも含めて、これから高度成長時代とは比較にならないほど、地域社会にいる時間、滞留する時間が大変長くなるということを前提にしてやはり考えていかなければいけないということになるようです。そのような本も幾つかございまして、その中で、スピリチュアリティーというのでしょうか、広井さんに言わせれば、生と死を超えた次元のもの、そのようなものが大事になっていくということがあるようです。
大量死と老人の時代へという寂しい話を書きましたけれども、しかし、私自身もだんだんと年をとるに従ってそのようなものを実感する時代なので、お話ししているわけですが、ここまで来ると、中世と現代というものを安易な比較はできませんが、やはり私はシヴィアな「環境」というものを考えざるを得ないわけです。
中世は端的に言って飢えの世界です。それに対して現代はしばしば言われているように格差社会であります。これは説明する必要がありません。しかし、例えば葬式仏教が安定していた江戸時代といっても、最近の西木浩一さんの研究によりますと、巨大都市である江戸では異なる葬送の在り方があったと言われています。これは江戸という巨大都市を維持するために日雇い層、日雇層といいますが、そのような人が大量に流れ込む。そのような人たちが劣悪な環境と激しい労働の中でどんどん死んでいくわけです。当然葬式などはできない。そうするとどうするかというと、投げ込みという、これはレジュメに書き損じたので申しわけないのですが、投げ込むというあの言葉として、それが葬送だったという、もう説明は必要ないと思いますが、そのような状況が繰り広げられていた場合があるそうです。例えばわれわれの身近な中で、ハイチの地震の後に人々が折り重なっているあのような状況が、豊かな江戸、と言われている近世の巨大都市江戸の中でも確かに広がっていたという研究があります。
また、例えば湯浅誠さんが書かれた岩波新書の『反貧困』。ベストセラーだと思いますが、あの本の中で、貧困に対処する手だてとして「溜め」という言葉が使われていたと思います。これはアマルティア・センという、ノーベル経済学賞をとったインドの経済学者だと思いますが、センのケイパビリティーという概念がある。これは訳書でわたしもかじりましたが、「潜在的能力」というような学者の訳語を見てもさっぱりわからなかったのですが、湯浅さんはこれを「溜め」と表現するのです。これにはさまざまな要素があります。親兄弟でもあるし、仲のいい友達、それから人にかわいがられるような、かわいげのある能力とか、そのようなもの自体が身を助ける。何でもいいからそのようなものを持っている、あるいはそのようなものを共同的に積み上げていく、そのようなものがこれからは必要であるということを言われているのは、私はやはり中世を研究しながらも大変に感銘を受けたわけです。
そこに書きましたように、グローバリゼーションというものが世の中を席巻している現在、思想の一つとしてコミュニタリアニズム(共同体主義と訳します)というものもあるわけですが、このような非常に厳しい派遣労働やそれにまつわるさまざまな悲惨な話は、マルクス経済学では「労働力の商品化の無理」というそうです。このようなことが蔓延している中に、新たなコミュニティーというものは、大変に模索は難しいのではありますが、やはり必要なのではないかという感想を漏らさざるをえません。余り歴史学の研究会ではこのようなことは言わないのですが、やはり問題が問題なだけに少しお話しさせていただければと思ったわけです。
最後になりますが、そのようなわけで、やはり十五、六世紀、中世のそのようなシヴィアな時代に葬式仏教というものが生まれていく、そのことの意味はやはり非常に重いと思います。これで私のお話を終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
「葬式仏教」の公益性と仏教再生
第一生命経済研究所主任研究員
小谷 みどり
第一生命経済研究所の小谷と申します。会社の名前が経済研究所とありますけれども、私は、今髙佐主任からご紹介いただきましたように、専門が死生学と、もう一つが社会調査でございます。わたしより前の午前中の先生方お二人とは全く違って、私は文献調査というのは大の苦手でございまして、死生にまつわるフィールドワークですとか社会調査を中心にしております。
フィールド的には終末医療から亡くなった後の葬送、お墓の問題が私の専門分野です。そのような意味で、私は今日「葬式仏教の公益性と仏教再生」というタイトルをちょうだいいたしましたけれども、仏教についても、ましてや日蓮宗についても全く門外漢でございます。今日は死生学の観点から葬式仏教がやるべきこと、どこに公益性があるのかというお話をさせていただきたいと思います。
◇ ◇
レジュメを用意させていただきました。最初に葬式仏教の公益性の公益性とは何ぞやということについてお話します。
日蓮宗に限らずどこの宗門でもお寺の公益性についての議論が最近なされておりますけれども、一体お寺は何をすれば公益性があるのか。葬式仏教だけではいけない、あるいは葬式仏教ではいけない、だからお寺は社会活動しなければいけないのではないのかという議論もあります。私はこの考え方というのは必ずしもそうではないのではないかと思っております。すなわち、今日も今からお話しさせていただくわけでございますけれども、社会活動に手を着けるよりも葬式仏教を十分なものにして行くのが先ではないかというのが私の議論であります。
現に、お坊さん方がやっていらっしゃる社会活動のうち、わたしたち一般の生活者から見て成果が上がっていると思われるものはほとんどありません。なぜなら、お坊さんだけで活動なさっていらっしゃるから。自死の問題にしても引きこもりの問題にしてもビハーラにしても、お坊さん以外の専門家はたくさんいらっしゃいます。そのような人たちとまず協同しなければいけない。つまり社会活動するには僧侶は教学以外に多角的に勉強しなければいけない。僧侶でなくてもできることをするのではなく、僧侶でなければできないことをまずするべきではないか。にもかかわらず、お寺の公益性を求めるがために社会活動をしなければいけないのではないのかというのは、本来の葬式仏教がないがしろになってしまっている。そのせいで寺離れ、仏教離れが起きているというのが私の考えでございます。
では、まず、公益性というのは誰が判断するのかということです。お寺の公益性とは何ぞや。お寺の公益性は誰が一体判断するのか。これはちょうど一年前の日蓮宗のセミナーでお寺の公益性というのがテーマでございまして、私も講演録を拝見させていただきました。その中に答えが出ておりますけれども、例えばNPO法人――レジュメに書かせていただきましたけれども――というものがございます。比較的公益性が高い、利潤を求めることを追求としない法人とされておりますけれども、そのNPO法人の中でもより公益性が高い法人に認定NPOというものがございます。この認定NPOになりますと税制優遇とかいろいろな特典があるわけですけれども、普通のNPOと認定NPOは何が違うのかといいますと、寄付金が全収入の二〇%以上あることです。つまり寄付金が多ければ多いほど、その法人は社会から支持されている、公益性がある、信頼されていると判断できるということです。これが公益性の基準としていいかどうかは別にして、認定NPO、NPOの中でもより公益性が高い法人というのはそのような基準で決められています。
これをお寺に当てはめると、布施が、あるいはお寺に対する寄付金があればあるほど、出す側としてはそのお寺のことを信用しているわけですし、そこに公益性があると判断されるわけです。つまり、公益性というのは一般の市民が判断するものであるということです。お坊さんたちが公益性のあり方を考えるのではない。お寺以外の人たちが判断するものだということです。
それでは、一般の人はお寺に何を求めているのか、それを理解することが大事になりますけれども、レジュメの一ページめの下のところに書かせていただきました。これは仏教の超宗派で作っている全国青少年教化協議会というものがございますけれども、私はそこの付属の臨床仏教研究所の客員研究員もさせていただいておりまして、そこでおこなった調査の結果でございます。
これは一般の人たちに聞いておりますが、一般の人たちがお寺に参加してみたいと思う行事は何か。一番多いのは、説法を聞いてみたいという声です。この調査で、お寺とかお坊さんについて思うところを書いてくださいという欄を設けましたら、ご想像どおり、お寺やお坊さんに対する不満が圧倒的でした。しかし、中には少数ながら、うちのお寺のお坊さんはすばらしいと書いている人もいます。すばらしいと書いている人と、うちのお寺のお坊さんはだめだと書いている人の理由が同じです。それは法話なのです。法話がくだらないからあのお坊さんはだめだというのと、うちのお寺のお坊さんは法話がすばらしいと、法話の良し悪しで僧侶の評価が決まっているところがあるのです。
この法話というのは本当に重要で、自死遺族の方たちの中にはお坊さんのお葬式のときの法話に傷つけられた体験を持ってらっしゃる方がいらっしゃいます。とても心ない法話をなさっていることがあるのです。お坊さん自身は気がついていらっしゃらないのだと思いますけれども、受け手の遺族の方たちがどれだけ傷ついたか。
先ほど、うちのお寺の和尚さんは法話がくだらないと書いている人が少なからずいたというお話を申し上げましたけれども、そう書いていらっしゃる方は地方に多いのです。地方に行きますと、例えば近所の人の多くが同じお寺の檀家さんというケースがございます。地方はまだ地域とのつながりも強いですから、ご近所のお葬式に参列するときに、同じ僧侶の法話を聞くという機会がたくさんあります。どの家族がどのような死に方をしても、誰が死んでも、いつも同じ法話をする。もう聞き飽きているのです。またこの話かという。せっかくの葬儀の法話のチャンスをみすみす無駄にされています。お葬式に参列すると、することがありませんから、みんな強制的にせよ法話を聞くわけです。こんな最大の布教のチャンスをみすみす無駄にされているお坊さんが少なからずいらっしゃる。現実にお坊さんの側から考えてみれば、ふだんその方たちとご縁がなければ無難な法話をするしかないわけでして、結局は、果たして一つ一つの死に真摯に向き合って、葬式を行ってきたのかということが問われているのではないでしょうか。ですから、私は、今の葬式仏教が十分に機能していないから社会が寺から離れようとしているのだ、けれども葬式仏教自体は実は公益性があって、真の本当の意味での葬式仏教、今の世の中が求めている葬式仏教をすることが大切なのだと考えております。
では、お寺はどのような活動をすべきかという問いでございますけれども、一番多いのが死者・先祖の供養、それから仏教の教えを広める活動が続いています。もちろん社会活動をしてもらいたいという意見もないわけではありませんけれども、圧倒的にお寺というのは葬式仏教というイメージが強いわけです。これを払拭しようというのではなくて、葬式仏教という意識が世の中の人にあるのであれば、葬式仏教をきわめるべきであって、それが世の中の人が求めている仏教の公益性ではないかというのが私の考えでございます。
もちろん葬式自体が、先ほども申し上げましたけれども、最大の布教の場です。仏教の教えを広める最大のチャンスでございます。最近お寺がいろいろ門戸を開放して地域の人を集めたりなさってらっしゃいますけれども、それも人に来てもらわなければいけません。お葬儀や法事の場というのは強制的でも人が集まります。お坊さんの話を嫌でも聞くわけです。仏教にこれまで関心のなかった人にも法話ができる、それが最大の布教のチャンスなのです。そういう意味においてもそれの一つ一つを大切に、ないがしろにしてはいけないのではないでしょうか。
今の仏教は葬式仏教、死のイメージというのが非常に強いわけですけれども、では、お坊さんは死に直面したときに心の支えになるか。二ページ目の下のグラフを見ていただきましたらわかりますように、ほとんどの人はお坊さんが心の支えになるわけではないと思っているわけです。ところが、宗教を持つ、信仰があるということは、死に直面したときに心の支えになるかと聞いたら、七割以上の人がなると答えているのです。自分に信仰がなくても、死に直面したときには信仰があることが心の支えになるでしょうと言っています。ところが、坊さんの存在が心の支えになるという回答は大変に少ない。ここに今の葬式離れが起きている一端がかいまみえる気がしています。
今からいろいろなお話を具体的にさせていただきたいと思いますけれども、例えば、死ぬのが怖いという意識。当然終末期の患者さんは死を宣告されると「死にたくない、死が怖い」という思いに駆られるわけですけれども、死が怖いという意識の背景には大きく二つの不安があります。
一つは、死んでいくまでに痛みや苦しみがあるのではないかということへのおそれです。そのおそれがあるから死ぬのが怖いという意識につながる。これは特に日本人に強い感覚です。日本では痛みや苦しみに耐えてこそ明るい未来があるという考え方がありますから、患者も痛みや苦しみを我慢するという傾向がございますけれども、欧米では基本的に痛みや苦しみを取り除くことを重視しますので、終末期に痛みや苦しみがあるのではないのかという思いに駆られる人は少ないのですが、日本ではそのような意識がものすごく強い。それは医療が解決する問題です。
もう一つ、死が怖いという意識に非常に大きく影響するのが、死んだ後どうなるのかという不安です。すなわち、信仰、宗教による来世観、死生観がない人ほど、死ぬのが怖いという意識になるということです。死に行く人が安寧のうちに心静かに亡くなっていくためには、仏教による来世観をきちんと教育するということも私は葬式仏教の大きな役割ではないかと思っております。
けれども、現実にはお坊さんは死に直面したときには心の支えになるわけではないと思っている人が大多数です。
冒頭に私はお坊さんがやっていらっしゃる社会活動はわれわれ一般サイドから見ると効果が上がっているものは少ないと申し上げました。各宗派では、ビハーラ運動に非常に力を入れていらっしゃいますけれども、医療の現場でなかなか根づいていかない。その一つは、お坊さんが人の話にあまり耳を傾けようとしないことが一番の原因だと思います。お坊さんは説法、説教されるお立場でしょうから、人の話を聞かない。死に行く患者さん、死に行く患者さんだけではありませんけれども、お寺にやってくる檀家さんたちは話を聞いてもらいたいわけです。必ずしも説教されたいわけではないわけです。人の話をじっと聞くという傾聴は簡単に思えますが、いざやってみるとものすごく難しく、訓練が必要です。患者が何を求めているか、ニーズを把握せずまたスキルのないままにそのような現場に出ていかれるのはすごく向こう見ずで危険な行為だということになりかねません。
◇ ◇
公益性というのは一般の市民が判断するものであると。また、一般の人たちはお寺に葬式仏教というイメージを持っているし、死者供養、それから仏教の教えを広めるという活動に対して期待しているということを見てまいりました。ですから、葬式仏教には本来公益性があるのではないかと、だから葬式仏教を機能させるということが求められているのではないかと思います。
しかし、今東京では、直葬といいまして、お葬式を一切しないというものが二、三割にも達しております。そんなにあるのかと仰るお坊さんが多いのですけれども、お坊さんは直葬に触れる機会はあまりございませんでしょうから、直葬が増えている実態をなかなかおわかりいただけないというのが現実ではないかと存じます。葬式仏教には公益性があるといっても、その葬式がもう要らない、葬式に意義を感じないという人たちがたくさんいるわけです。
ましてや、お葬式をしたとしても、葬儀式は慣習として成立しているだけの話で、一般の方にとって、葬儀で重要なのは告別式です。最近のお葬式の傾向は葬儀の告別式化です。告別式のほうがずっと遺族の悲しみが癒える。あるいはその人を亡くした悲しみを共有できるのが告別式です。葬儀式ではありません。ですから、私はこれから宗教色のないお葬式がふえてくると思います。今まだそれほどふえていないのは、慣習として定着しているからです。これから葬儀の告別式がどんどん加速化してくるのではないのか、そうなったときにもう坊さんは葬式仏教さえも求められなくなっていることにもなりかねません。私は、今までの葬式仏教がいわゆる葬儀式だけにしかかかわってこなかったから、葬儀式だけの葬式仏教ならば必要ないのではないかという流れが起きてきたのではないのかなと思っています。
先ほどお坊さんのお葬式の法話に対する批判的な意見が多いというお話もさせていただきましたけれども、一つ一つのいのちや死に向き合って寄り添うということが、今の社会が葬式仏教に対して求めていることでございます。
死に場所が今ほとんど病院になっております。何らかの病気で亡くなっていくというのが一般的な人の死に方でございますけれども、医療や福祉では担えない心や精神の満足を与えられるのが仏教の役割ではないのかと、終末医療の現場を見ていて非常に強く私は感じております。
そのためには、お寺や檀信徒との日ごろからの信頼構築が欠かせない。檀家さんから死んだという連絡が入ってきてからでは遅いということです。
病気が告知された、あるいは余命告知されたという段階からお坊さんのところに一報が入ってこないようでは、私は本来の葬式仏教が機能できないのではないのかと思います。先ほどもビハーラの話で申し上げましたけれども、この人になら理解してもらえるのだという実感を本当に坊さんたちは与えられているのかが問われているのではないでしょうか。
私の問題意識をそこに整理して書かせていただきましたので、もう一度お話しさせていただきたいと思いますけれども、葬式仏教でいいのだと、基本的には葬式仏教をきちんと機能させるのが先だというのが私の意見でございます。しかし本当に今の葬式仏教は死に行く人や死なれた人に寄り添っているのか。寄り添っていないから、先ほど申し上げたように、葬儀の告別式化が起きているわけですし、坊さんは要らないという流れも加速しているというわけです。
もっと言うと、二点めに書かせていただきましたけれども、今、檀家であることは子孫にとって負の遺産だと思っている人がとても多い。このような話をいたしますと、お坊さんたちは「うちの寺は大丈夫だ」と思いがちです。なぜそう思うかというと、熱心な一部の檀家さんしかごらんになっていないからです。お寺に足しげくいらっしゃる熱心な檀家さんは皆さんのお寺の檀家さんの何割いらっしゃるか。ほとんどお寺にも来ない、物言わぬサイレント・マジョリティーは何を考えているのかということに思いをはせなければなりません。あっという間にサイレント・マジョリティーが大きな力になって檀家離れが起きていく可能性もあるのではないかという気がしています。
なぜそのようなことが起きるのかというと、答えは簡単で、檀家が信者であるとは限らないからです。お葬式での不満というと、戒名が高いとか、お坊さんのお布施が高いというようなことがよくあります。お金に関する、お布施に関する不平・不満というのがございますけれども、高いという不平・不満が起きるのも、そこにお寺への信頼、お坊さんへの信頼が薄いからです。
お寺やお坊さんに対して信頼があれば、お布施が高いという不平・不満は絶対に起こりません。そのような声があるということは、よく一般の在家がそのような経済至上主義にまみれているからだとおっしゃる意見もございますけれども、そうではなくて、そこには信頼が乏しい、信仰が薄いからそのような問題が起きてきているのだということです。
葬儀式だけの葬式仏教では信頼関係はうまれません。つまり葬式仏教の機能不全が原因で葬式離れや墓離れが起きているのではないのか。葬儀式だけのお寺、仏教であるのであれば、そのようなものは要らないということで寺離れにつながっているのではないのかということです。
世の中が変わっていくと、死の迎え方も変わる、葬送の在り方も変わりますが、今どのような葬式仏教が求められているのか、ということを見据えて、世の中に求められている葬式仏教を遂行するということに非常に大きな公益性がありますし、それは仏教の再生につながるのではないかと考えております。
◇ ◇
では、どのように葬送が変化してきたのか、あるいは葬送が変化してきた社会の背景についてお話しさせていただきたいと思います。三ページ目の一番下、左側は死亡者数と出生数を取り上げたグラフです。右肩上がりに亡くなる方がこれからどんどんふえてくる社会、多死社会がやってきます。二〇〇九年には一一四万四〇〇〇人、去年一年間でそれだけの方が亡くなっていらっしゃいますけれども、ピークを迎えるのが二〇四〇年、今から約三十年後、一七五万人の方が一年間に亡くなると推測されております。三十年間でこれから死亡者数が一・五、六倍になるため、メディアが最近は経済の観点から葬送ビジネスを取り上げるようになっています。今週も「週刊ダイヤモンド」がお葬式の特集をしておりますけれども、経済誌が葬儀とか墓とか寺の特集をするとものすごい勢いで雑誌が売れるのだそうでございます。とにかくこれからものすごい勢いで亡くなる人がふえますから、経済的に大きなマーケットになるのではないかという視点があります。
グラフに婚姻件数も一緒に載せましたけれども、少子化に伴う婚姻件数の低下で冠婚の数はこれから将来的にふえる見込みがありません。人生の通過儀礼で需要が見込めるのは葬祭しかないということで、そのような観点からでも葬儀マーケットが注目されています。
それから、右はどこで亡くなっているのかということを示したグラフです。ご承知のとおり、病院で亡くなる方がほとんど、病院で亡くなるのが当たり前という社会になっております。亡くなる方の八十五%は病院でお亡くなりになっています。ところが、一九七七年までは家で死ぬ人のほうが多かったのです。三十年前までは家で死ぬ人が多かったのに、あっという間に病院で死ぬのが当たり前という社会になってまいりました。しかし、これから亡くなる方の数はどんどんふえていきます。
病院というのは病気を治す場所でございますから、治癒の見込みがなくて死期が迫っている人を病院に収容するベッドがこれから足りないという時代がやってまいります。厚生労働省は在宅医療、家で最期を迎える医療にシフトしようという政策を打ち立てておりますけれども、果たしてそれが可能なのか。今の家族、今のライフスタイルにおいて、家で死ぬということが可能なのか。治癒の見込みがなく、末期のがん患者がいて、収容してもらえる病院がなく家に戻される方たちをがん難民と呼びますけれども、がん難民がどんどん増えてくるわけです。
病院から家に帰れと言われた場合に、たいていのご家族が医者にする質問があるのです。それは、「危篤になったら病院に入れてくれるか」という問いです。「危篤になるまでは、家で家族で見ましょう。ただし、危篤になった場合には病院にちゃんと入れてくれるでしょうか」という不安があるのです。医者は何と言うかというと、「危篤になったらそのまま動かさずに家族で看取ってください」当たり前の答えです。われわれはその当然の答えも、質問しなければわからないぐらい、病院で死ぬのが当たり前だと思い込んでいるのです。当然ながら、危篤になったから救急車で病院に運んでも亡くなるのですが、家でみんなで看取るという経験をしたことがないので、この三十年間であっという間に昔の過去の経験が忘れ去られていて、どうしていいのかわからないという家族がたくさんいるということでございます。
私は日本で人のいのちの問題とか死についてどのような教育がなされてきたのかというのを明治時代以降の教科書を調べたことがありますけれども、昭和十年代までの家庭科の教科書に死人の看取り方というのがきちんと書いてありました。そこには何が書いてあるかというと、危篤になったら、まず患者の居住まいを正せ。きちんと居住まいを正してから死なせろと書かれてあります。次に亡くなったかなと思ったら、鼻の上にちり紙を置けと。ちり紙が動かなかったら、多分呼吸がとまっているので医者に連絡せよ、というようなノウハウでございますけれども、少なくとも学校の教育の中で死人の看取り方をきちんと学んでいたわけでございます。学校教育で家族の死を扱わなくなって何十年もたち、ましてやこの三十年間で病院で死ぬのが当たり前という時代になっておりますから、家族で家族を看取るということがいろんな意味でできなくなってきているわけです。
◇ ◇
では、病院でどのような終末の光景が繰り広げられているのかということですが、日本人の長寿化で死亡年齢が非常に高齢化しております。昨年、一昨年のデータですと、一年間に亡くなった方のうち、八十歳以上で亡くなった方が初めて五〇%を超えました。五〇・一%でございます。
人生八十年と言われます。亡くなった方の五〇・一%は八十以上で亡くなっていますから、半分が人生八十を超えて生きているわけではございますけれども、これは実は男女差がすごくあって、男性の場合八十以上で亡くなる方は三分の一しかいらっしゃいません。女性の方の場合は六十五%以上の人が八十以上で亡くなっているのです。男性と女性でものすごく寿命の差がございます。男性の場合は人生八十年ではございません。八十年まで生きる人は三分の一しかいらっしゃいませんので、本日御聴聞頂いている皆様には、ぜひ日ごろからの人間ドックや健康診断を欠かさないでいただきたいと思います。
八十年まで男性は生きないというのが日本人の姿でございますけれども、女性の六十五%以上は超高齢者の死でございます。とにかく超高齢者の死がふえてきておりますから、そのような方たちのお葬式は、誤解をされるのを承知で申し上げますと、悲しくない。非常に淡々とした雰囲気のお葬式がふえてきております。また、子供たちも定年退職をしているという人たちが珍しくなくなりましたから、本当にお葬式にいらっしゃる人が非常に少ない。子供たちが定年退職していれば、まず仕事関係の義理で来る方がいらっしゃらない。それから、ご近所とのつき合いが薄くなっていれば、近所の方の参列も少ない。亡くなった方は非常に高齢ですから、亡くなった方自身のお友達の数も少ない。家族葬という言葉がございますけれども、望まなくても家族葬になってしまうというのが超高齢者の死です。
では、超高齢者は死んでも悲しくないのかということでございますが、実は病院で最後亡くなるという事象と非常に関係しています。高齢になればなるほど、最後の介護・看護の療養期間が長くなるという傾向がございます。ですから、高齢社会になって、老人医療の負担が非常に大きいということで、受益者の負担をふやそうというような議論がなされているわけでございます。ともあれ、亡くなったときにご家族の方はまず何を思うかというと、やっとこれで終わった。亡くなった方もつらい介護・看護の生活から解放されてよかったねという気持ちです。
それから、残された人たちもこれまでお金も使い、時間も使い、体力も使い、何年もの介護看護してきたこの生活から解放されてよかったなという、ほっとしたという安堵の気持ちが非常に強いわけです。そうした気持ちの中で葬儀が行われていくわけでございますので、なかなか悲しいという気持ちにはなり切れないというのが現状です。悲しめない状況にあるともいえます。
では、死の悲しみはなくなったのかということですが、予期悲嘆という言葉がございますけれども、死に別れる悲しみが患者がまだ生きているうちに前へ来ているのです。
具体的にお話し申し上げますと、例えば治癒の見込みがなくて死がさけられないことは医療技術で判断できるわけです。そのことを医療現場では家族に告知します。インフォームドコンセントという言葉がございますけれども、死に行く患者すべてに告知をしている病院は日本ではまだまだ少ない。日本では二人に一人ががんにかかり、三人に一人ががんで命を落とします。ですから、がんというと死の病気だというイメージがあり、治る場合に限ってはようやくほぼ一〇〇%告知をするようになりましたけれども、治癒の見込みがなくて死が避けられない場合、本人に告知をするというケースはまだまだ日本では少ない。
ところが、家族には一〇〇%告知されているわけです。家族は告知されたときにどう思うかというと、この人と死に別れるのだ、この人は死んでしまうのだ、この人と別れなければいけないのだという衝撃が走るわけです。それを予期悲嘆と呼びます。この人と死に別れなければいけないと、まだ患者が生きているうちに死の悲しみが起きるわけです。
医療技術は日進月歩しておりまして、告知を受けた後の余命がどんどん長くなっています。これがどう影響するかというと、予期悲嘆にある家族が、死の受容ができてもまだ患者が生きているという状況になります。そうなると今度は早く死なせてあげたいという思いになります。苦しい闘病生活から解放してあげたいという気持ちです。
わたしはその現場に伝統仏教の僧侶の姿をめったに見ません。ビハーラも死に行く人へのケアに重点がおかれています。が、ケアされるべきは家族ではないのかと。本人は告知をされていない。家族だけがすべてを知っている。その予期悲嘆にある家族は自分たちも生活しなければいけない。仕事しなければいけない。なおかつ患者の看護・介護がある。いろいろな問題を抱えているわけです。そのような家族をケアするのが宗教者の役割ではないかという気がいたしています。死に行く人は患者ですから、ケアする専門家はたくさんいます。家族は病人ではないので、医療者によるケアの対象外です。しかし非常に強い衝撃を受けているのは実は本人ではなくて家族であるのです。
今日はデータをお示ししませんでしたけれども、日本人の死生観が変わった、という議論がございます。日本人の死生観が変わったと言われる議論に、死んだら無だと思う人がふえているという説がございますけれども、実は死んだら無だという観点は「わたしが死んだら」、なのです。でも、大切な人が死んだら無ではないのです。わたしは死んだら無だけれども、大切な人は千の風になってのイメージなのです。無ではない。だから、いまだに墓参は国民的行事として定着しているのです。
誰の死を想定するかによって異なる死生観を持っているのが現代の日本人であって、死生観が変わったわけではない。本来そこに宗教による来世観があれば、わたしが死んでも、大切な人が死んでも同じはずです。そこに信仰がないから、わたしが死んだ場合と大切な人では違うということです。
それともう一つは、どちらの死が怖いかという話です。わたしが死ぬときと大切な人が死ぬときとどちらが怖いか。これは老若男女問わず、自分が死ぬときより大切な人が死ぬときのほうが怖いのです。自分の死が怖いというところだけを見ると、ほとんどの調査では、高齢になればなるほど自分の死は怖くなくなることが示されています。若い人ほど自分の死は怖い。しかし、自分の死と大切な人の死とどちらが怖いかというと、老若男女問わず、自分が残されることのほうが怖いわけです。自分が死に行くことより大切な人に先立たれる恐怖が強いということです。
高齢者の、単身、一人世帯あるいは夫婦二人世帯がふえております。子供がいても、子供と関係なく夫婦二人で老後を暮らす。そのような世帯の方は配偶者のどちらかが亡くなると一人世帯になるわけです。仏教界でも取り組んでおられる自死の問題では、働き盛りの人たちの問題がマスコミでクローズアップされますが、人数的に見て自死が一番多い層は、今も昔も変わらず高齢者です。高齢者が全体の三分の一以上をを占めます。高齢者の自死の背景の一つに高齢者のうつの問題がございますけれども、このような状況のきっかけの一つに配偶者との死別が指摘されています。昔は大家族で住んでいましたから、配偶者が亡くなっても、子供や孫と一緒に暮らしている中で自然に死を受容できたわけですけれども、今は夫婦二人で暮らしていて、その一人が亡くなった場合、二人が一人になったことの喪失感は、三人が二人になったことの喪失感より大きいのです。ライフスタイルの変容で死別の喪失感が肥大化しているのです。
では、大切な人を亡くした喪失感、孤独感はいつごろ露呈するかというと、亡くなってすぐではないのです。死別して半年以上もたってからなのです。ところが、法事は四十九日の後は一周忌まで何もないわけです。百箇日などはほとんど行われません。月参りがなければお坊さんはやってこない。ひとり暮らしになった遺族に対し、亡くなってしばらくの間は周りの人たちも、あの人は大丈夫かなと気にしますけれども、亡くなって半年間はとても普通に見えるのが一般的です。亡くなった死の悲しみが余り衝撃的ではないように周りからは映るのです。死後のさまざまな手続きに忙殺され、遺族は半年ぐらいはある意味ハイになっているからです。ですから、あの人は死別の悲しみを克服したと思われがちですが、実はみんなが気にしなくなった半年もたってから、生きがいの喪失とか、うつの問題は出やすいということが明らかになっています。その現場にもお坊さんはいないことも問題です。
ですから、死の悲しみが予期悲嘆となってまず亡くなる前へ来た。それから、孤独感や喪失感が亡くなって半年以上もたって出る。そこに葬式仏教はかかわるべきではないかと私は考えます。死に行くことよりも残されることのほうが恐怖であるからこそ、仏教が家族にかかわることに一つの大きな意義があるのではないのかと思います。
地域や親族のかかわりが変容し、こうした人たちをケアをする人がほかにいないこともあります。ですから、これは宗教が担うべき役割ではないかという気がしています。しかしそのためには、亡くなってから遺族からの連絡が入ってくるのではもう遅い。「お寺に行って話をきいてもらおう」と、日頃からの信頼が檀家になければ僧侶に関わる余地はありません。
それから、ビハーラ運動に絡めて申し上げますと、そのような家族や死に行く人へのケアも大切でありますけれども、死に行く人たちや家族に日頃からかかわっている人たちの死生観を醸成することがとても大事だと思っています。僧侶自身が直接活動するのではなく、そうした現場にいる医療者たちに正しい死生観を持ってもらう活動です。
また、死んだ後どうなるのだろうということへの不安がある人ほど死が怖いというお話をいたしましたが、死生観を醸成することで死の不安を軽減させることもビハーラの大きな役割ではないかと思います。
◇ ◇
次に、四ページ目をあけていただきたいのですが、葬儀の在り方が大きく変わった原因は、一つは病院での死、それから死ぬ人がふえてきたということです。死亡年齢の高齢化もあります。
核家族化と家族の多様化も影響しています。親が死んだら悲しいものだという前提が一般的にはあると思いますけれども、必ずしもそうではなくなっているという現実がございます。
私は先ほどわたしが死ぬときと大切な人が死ぬときとどちらの死が怖いかと、「大切な人の死」という言葉を使いましたが、実は自分にとって親が大切な人であるとは限らなくなっている。つまり、本当は悲しいはずの親の死を悲しめない子供たちがふえているということです。
例えば「おくりびと」という映画に涙を流して感動したとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいますが、納棺したり、遺体を着せかえたりするおくりびとの仕事は本来は家族の役割でした。納棺師さんというプロの職業の人たちは、北陸や北海道では昔からいらっしゃいましたけれども、全国的に出てくるようになったのはつい最近のことです。子供たちが親の遺体が気持ち悪くてさわれない。家族ができないので、納棺したり着せかえたりするのをプロに任せるようになってきたという現実がございます。
ご僧侶の先生方のなかには、僧侶が葬儀屋さんの手下になってしまったことが今の葬儀の大きな問題だという議論をなされる方がいらっしゃいますけれども、わたしはそれは間違っていると思います。
例えば家族でさえも、子供たちでさえもさわれない親の遺体を葬儀社は納棺するわけです。先ほど病院で死ぬ人が八十何%もいると申し上げましたけれども、僧侶の先生方は闘病生活が長かった檀家さんのご遺体を間近でごらんになったり、さわられたりされたことはおありでしょうか。
ここ最近、亡くなっていらっしゃる方のご遺体は、薬剤や栄養をいっぱい入れられてむくんでいることが少なくありません。太っていた人ががりがりになって亡くなるのではなく、スリムだった人がパンパンにむくんで亡くなることが多いのです。
元気だった日頃とは様相が変わり腐敗も早い遺体と葬儀社の方は接するのです。遺族は、自分たちもできないことをやってくれる葬儀社に信頼を寄せるのは当然です。わたしは別にお坊さんに納棺せよ、遺体をさわれと言っているわけではございませんが、遺族の気持ちとして、お商売とはいえ、親身に遺族によりそう葬儀社に信頼を持つのは当然ではないかと思います。
なぜ親の遺体が気持ち悪いと思うかというと、核家族化が一つの大きな原因であると思います。親の遺体が気持ち悪いといってさわれないというのは今の団塊の世代ぐらいの世代の人たちでありますけれども、そのぐらいの人たちから核家族化が進んでまいりました。結婚すると同時に親から離れ、以来何十年も親と一緒に暮らしていない。親が老いて、病に倒れ死んでいく姿を間近に見ないわけです。ところが、ご遺体になると、自分の目の前に返されるわけです。気持ち悪いと思うのは、動物的な本能ではないかと思いますが、核家族化によって家族に対する感情が多様化していっている結果ではないでしょうか。
◇ ◇
それから、延命措置をするか、しないかという大きなテーマがございます。患者自身がどうしてほしいのか、意思を明確にしていれば、その意思が尊重されますけれども、今亡くなっていらっしゃる方の多くは意思を明確に文書化されるようなことをなさっていません。そうなると、病院では、家族に延命措置をするか、しないかの判断をさせます。患者が高齢の場合、大概の家族は今は延命措置はしないという選択をする人が多いのです。
ところが、今日は二月九日、月の初めですから、延命治療をしないというご家族が圧倒的に多いのですが、月末になると延命措置をしてほしいという家族がふえます。年金ねらいです。患者自身は高齢で意識もなくて、チューブにつながれているだけです。ニートやフリーターの問題などもあります。親のお金を当てにして生きている子供たちにとっては、親が意識がなくても月をまたいで生きてくれれば自分たちの生活費が稼げるわけです。そのような人が多いとは言いませんが、そのような家族も実際に、散見されるようになってきて、いろいろなご家族がいらっしゃるなあと思います。
先ほど都内では直葬する人が二、三割もいると申し上げましたけれども、以前はお葬式をしない人というのはお金がないか身寄りがない、どちらかだったわけです。最近はお金もあって家族もいるけれどもお葬式をしないという人が多くなった。たいがいは、ご家族の考えではなく、亡くなった方本人の生前の希望によるものです。それはなぜなのか、死の自己決定意識の台頭という観点から考えたいと思います。
自分の死んだ後のこと、延命治療などもそうですが、生きているときに自分で死に方や死後のことを考えておこうという意識です。なぜそのようなことを考えたいかというと、家族に迷惑をかけたくないから。直葬も、葬式をするとみんなに迷惑をかけるからという思いで選択されている傾向があります。
現に高齢者の方たちから、「自分が年をとればとるほど訃報に接する機会がふえてくる。一回の香典が三千円、五千円にしても、月に何件もあったら年金がなくなってしまう。どうしたらいいのか」という質問をしばしば受けます。香典を出す側も迷惑だしお返しする手間も大変。そのような経験をした人はお葬式に来てもらうのも申しわけないという思いが強くなるわけです。
自分のお葬式を出すのであったら、その葬式代を孫の教育費に充ててほしい。あるいは、家族や親しい人たちでお葬式をするなら、見栄や世間体を気にする必要はない。その結果、お坊さんのお経は要らないとか、お坊さんは一人だけでいいから、そのお布施を子供や孫に残したいなどという人たちがふえてきたということです。
同じことが「ぽっくり信仰」にも現れています。日本人のほとんどの人たちが、ぽっくり死にたいと思う。これは日本の特徴です。
ぽっくり死にたいか、少しずつ弱って死にたいかと、もちろんこのようなことは自分で選べることではありません。ですけれども、欧米ではほとんどの人はぽっくり死にたくないと言うのです。日本人はなぜぽっくり死にたいと思っているかというと、「家族に迷惑をかけるから」と「痛みや苦しみがあるのがいやだから」。日本人が一番おそれている病気は、がんと認知症です。がんは痛いのではないか、苦しいのではないか。認知症になったら家族に迷惑をかけるのではないのかという思いがものすごく強いのです。
PPK運動というのは何年か前に、はやった言葉なのでご存じの方も多いと思いますが、長野県の施策でぴんぴんころり運動です。それから、GNP運動は静岡県の施策で、元気で長生きぽっくり運動。どちらも共通しているのがPでぽっくりです。ぽっくり死ぬのが理想の死に方だというのを打ち出しているわけです。しかし、ぽっくり死ねる人はほとんどいません。寝たきりになって、家族の介護・看護を必要とするようになった高齢者たちがどのような気持ちで死んでいっているのかということを葬式に関わるご僧侶たちに真剣にお考え頂きたいと思います。
それから、延命措置の問題もそうですけれども、社会に迷惑をかけないのがいい死に方だという価値観が蔓延してしまっています。葬式をするのも人に迷惑がかかる。だから葬式をしない。迷惑をいかに子供たちにかけずに死ねるかということが今の高齢者の大きな命題です。だから、みんな必死で、自分の死に方を考えているわけです。信頼している僧侶に「死んだあとのことは任せておけ!」と言ってもらえたら、どんなに肩の荷が下りる高齢者がいることか…、と思います。
◇ ◇
先ほど申し上げたように、自分が死ぬ場合と大切な人が死ぬ場合とで死生観が違います。自分で自分の死んだ後のことを考えたときには、自分は死んだら無だという観念で考えます。だから、葬式も要らない。墓も建てたらお金がかかるから、散骨してくれたらよろしいというわけであります。ところが、そこに大きな落とし穴があって、残された人たちが死を受容できないという問題が起きています。例えば全部海に遺骨を散骨してしまった人が「どこに向かって手を合わせたらいいのかわからない」という問題を抱えていたり、「お葬式は故人の遺志で無宗教、あるいはお葬式をしませんでしたが、一周忌をどうしたらいいか」という問題があるのです。宗教色がないお葬式、あるいは葬式をしないのであれば、一周忌などはしなくてもいいわけです。ところが、残された人は大切な故人のために何かしたい、偲びたいと思うのです。
死は本人だけの問題ではないので、特に死後の処遇にまつわる自己決定には大きな落とし穴があります。くり返しますが、わたしの死を考えたときと大切な人の死を考えたときとで死生観が違うということがあるからです。さきほども述べましたが僧侶が「死後は任せろ」と言って安心させてあげていただきたい。そのためには、僧侶への信頼、人間関係ができていなくてはいけません。でも、実際には死に直面したときにお坊さんが役に立つと思っている人はほとんどいないわけです。それを考えると、今の葬儀式だけの葬式仏教ではなく、本当の意味での葬式仏教を機能させることが世の中の人たちから今求められていることであり、それが仏教の大きな役割であると私は思います。本当に葬式仏教を機能させようと思えば、日ごろからの檀家とお寺との信頼関係の構築が欠かせない。そのためにどうしたらいいのかという問題を僧侶の先生方は考えていかれるべきではないかと思っております。
私はお寺は家族のきずなや地域のきずなをもう一回結びつける接着剤だと思っております。今の社会において、お寺に求められている役割は大きなものがあると思いますけれども、それがうまく機能していないことが大きな問題であり、寺離れにつながっているのではないでしょうか。
シンポジウム
司 会 では、貴重な時間でございますので、始めさせていただきたいと存じます。
フロアの皆様からのご質問を書面でいただきました。時間の制約があるものですから、すべてのご質問にお答えいただくというのは難しかろうと思いますが御容赦願います。
皆さんからお寄せいただいたご質問状を先生がたにお渡ししてございます。そのうちの幾つかを取り上げていただき、ご質問にお答えいただきながら、かつ、ご講演の中で言い足りなかった分を補足しておきたい部分というような具合で、先ずは十分ぐらいずつをめどにご発言いただきまして、それぞれの先生がたのそのご発言を基に、議論をさらに重ねていければと考えております。
では、ご発表順で、鈴木先生からお願いいたします。
鈴 木 ご質問をたくさんちょうだいし、ありがとうございました。日本では仏教が社会運動となるということを申し上げましたが、具体的にはどのようなことかというご質問がございました。私が考える社会運動というのは、仏教のお坊さんが何かをするというよりもむしろ、仏教の教えを生きざまとする、生活指針とする人たちが生きていく社会が建立され続いていくこと、それが社会運動だと思っています。つまり、インドでも中国でも、仏教はごく限られた人のものです。仏教の教えは何だか分からないのです。単に、あのお坊さんはすごいから、お布施をしていると、いいことがあるだろうというような認識なのです。そうではなくて、日本では、仏教の教えを伝えることができる。そして、仏教の教えを生きざまにして、自分の生活指針として生きることができる。そのような人たちが増えていくというのが、社会運動化するということだと考えております。
次は、天理大学のおやさと研究所の金子さまからちょうだいいたしました。礼にかなった、所属とお名前を書かれたうえでのご質問をありがとうございます。わたくしも敬意を払いまして、全文読ませていただきます。「インド仏教で見果てぬ夢(人々の来世の安心)を日本の伝統仏教が葬式仏教としてかなえたとするなら、今や葬式仏教が形がい化したからこそ、新仏教、在家仏教が人々の願いにこたえて、トータルな救い(葬式を含めた、人生のトータルな救い)を提供してきている。これが、常に進化する社会運動としての仏教の姿と言えないでしょうか」というご質問です。葬式仏教が本当に形がい化しているのか、またおっしゃるかたちが進化する社会運動としての姿なのかについては、この場では、時間の制約もあって、残念ながらお答えできません。ただ、今までの仏教に飽き足らない、そして、願いをこちらのほう、新仏教、在家仏教でかなえてもらおうという人があったからこそ、そのような教団ができて発展したことは、間違いなく事実であろうと考えます。
次です。今回の講演で、『葬式仏教は仏意に適わないのか』という演題に対する回答はされていないのではないか、というご質問でございました。つまり、釈尊が否定していない……、何でしょうね、ちょっと論理が追いにくいのですけれども。
司 会 否定していないからと言って、即肯定しているということにはならない、ということでしょうか。
鈴 木 ああ。そういうことですか。それに関しては、お答え申し上げたいと思います。仏教の目的をごく単純化するのであれば、「自利」と「利他」と言って間違いないと思います。そして、出家者はまず自利を求めて修行する。もちろん、自利利他円満でございます。利他。困っている人を救う。そこで困っている人がいれば、説法して助けてあげます。しかし、遠く離れたところにいる人、もしくは百年後、二百年後に現れてくる人を、その人一人では救うことはできません。利他を続けていくためには、仏教というものが続いていかなくてはいけないのです。もし仏教のお坊さんがいなくなってしまえば、だれも仏教を伝えてくれなくなる。三宝、仏・法、そして僧(サンガ)が三宝。そのうち一つなくても仏教が成立しなくなる。サンガが三つの宝の一つに挙げられているのは、サンガが持っている、仏教の伝承機能が重要だからです。サンガを維持することは、ある意味では至上命題の一つなのです。サンガがなくなれば、三宝帰依できず、自利利他行を実践する者もいなくなり、その結果仏教はなくなってしまいます。そして、自利利他をすることを釈尊は命じられている。ということは、サンガは存続せねばならない。民衆の願いにこたえて、葬式をする。それによってサンガ(教団)が存続するというのは、間違いなく仏意に適うものと考えております。
次は、個人的な問題でしょうか。私自身が葬式を執り行う際に、どのようなこだわりを持っているのでしょうかとのご質問です。「こだわりを捨てよ」というのが仏教でありますので、こだわりを持っているかと言われると、こだわりではなく、注意しているところ、こころがけているところだということでお答えさせていただきたいと思います。通常、私たちは健康なときには、健康であることを意識しません。人が「健康だな、いいな」と思うのは、例えば大酒を飲みすぎて、次の日、頭が痛い、気持ちが悪いと、「ああ、飲むんじゃなかった。健康はいいな」と。また例えば水にドボーンと落ちる。今まで空気があるのは当たり前だったのに、「あー、水ばかりだ。空気がない、大変だ、あ、顔が水から出せた、空気があってありがとう」。葬儀というのは、まさに猛烈に死というものを意識する機会だと思います。人間だれもが死ぬのは分かっています。自分も死にます。そして、皆さんも死にます。そして、皆さんや、わたしたちの大切な人も死んでいきます。死んでいくのは分かっているのですけれども、どこか遠いところに置いている。それを見つめ直す、いい機会だと思います。強い悲しみが心を洗う。まさに「良医のたとえ」ではないかと考えております。そして、そのような機会であることを弁えた上で、説法させていただくよう、こころがけております。
なぜか次は法名や法号について質問が来ております。「法名は日本だけのものですが、教義的意味づけはできるでしょうか」。直接の今日の話と関係ない気もいたしますが。ちなみに、釈尊が、初転法輪、最初の説法をするときに、昔一緒に修行していた五比丘の元にやってきます。それを見ていた五比丘は、最初は「あいつは、もう修行をやめただめなやつだから、あいさつするのはやめよう」と思っていたのですけれども、近づいてくるのを見て、その威厳に打たれて、「やあ、ゴータマよ」と呼びかけると、「正しく覚った者を名前で呼んではいけない」と言うのです。そのように、覚った者や、正しく修行をした者は、それ以前の凡夫の名前では呼ばないという伝統は、インド以来あるものだと思います。教義的意味づけになっているかどうか分かりませんが。また、インドの場合には、名前を呼んでしまうと、その人のカーストが分かってしまう場合が多いのです。ですから、出家した者は名前を変える、もしくは名前を呼ばない。単に「お上人」とか「先生」とか「世尊」とか「大徳」などと呼ぶという習慣があります。
また、法号・戒名について見れば、ある道に入った者が師匠から名前をもらうというのは、決して不可思議なことではないと思います。お茶の世界であれ、お相撲の世界であれ、落語の世界であれ、名前をちょうだいするのです。お答えになっているかどうか分かりませんが。
最後です。「正しさとは、涅槃、覚りの方向に向かうことということを、もう少し具体的にご説明いただければ」ということですけれども、それを判断するのが、おそらく「教師」という人に求められる能力だと思います。そして、自分で判断できない人は、師匠を取るのです。師匠は、自分、そして弟子がきちんと涅槃の方向に向かっているかどうかを判断する能力を持っていなければならないのだと思います、原理的には。基本的に、マニュアルではありません。方便というものは、その人によって違います。具体例を挙げることは幾らでもできますけれども、それがご質問者の答えに合致するとはかぎりません。マニュアルではないのです。その人、その人に合った処方せんを出して、それで導いていく。それが法師であり、教師の役目だと考えております。このような感じでいかがでしょうか。
司 会 てきぱきと数多くのご質問にお答えいただきまして、ありがとうございました。
では、次に湯浅先生、よろしくお願いいたします。
湯 浅 最初にお答え申し上げておきますが、今の鈴木先生の快刀乱麻のようなご回答や、原始仏教というのでしょうか、そのようなものに対する深い教義に基づいたお話や、先ほどの小谷先生の、非常に現代の、自分に身につまされるような信仰や仏教というものに対するお話は、いずれも私にとっては得難い経験です。今もずっと考えていて、質問を読みながら考えたことは、歴史学というものの持つ意味ということです。歴史学は、当時の資料を忠実に解釈して位置づけることで、当時の意識をまずは復元をする。あるいは、儀式の意味や、儀式の作法や、人々の考えや行動を復元して、それと現代とのつながりや断絶を考えるというように、残された資料に極めて忠実にやれということを、師匠筋からはさんざんたたき込まれているわけです。そのようなことをやりますと、宗教や信仰というものからは、とても手に負えないと撤退する人が多いのですが、私自身は、やはり地域の博物館にいたりして、地域社会を成り立たせている信仰や、人々の動きの中に定着しているものを避けて通ることができなかったということで、無謀にも本を書いてしまったというところだと思うのです。
それで、お話にご質問を何個も受けて、今ご紹介いたしますが、その辺が極めてよく露呈をしておりまして、痛いことばかりで、なかなか答えられません。例えば、葬送というものが全く行われなかった死体遺棄の時代から、僧侶や寺院によりそれがが行われるようになったと簡単に申し上げたわけでありますが、その転換が本当に何によって行われているのかというのは、環境や、そのような村の形成というのは、私のあくまで一つの仮説であったわけですが、そこから落ちる問題がボロボロと出てくるわけです。
例えば、葬送が行われなかった時代のことについて、葬送は夜、婚礼も夜に行われるというのは、どのようなことか。今ご質問を読んでいるのですが、「何か死と再生という観念と関係があるのかもしれないのですが、いかがですか」という質問を受けております。
これは、私の本の第二章のところで、勝田至さんという方の研究を前提にして、「葬送は夜。人目をはばかる意識もあった」と書いてしまったことに対するご質問だと思うのですが、私も勝田さんの研究を十分咀嚼しておりませんので、本当に人目をはばかる意識があったのかどうかを確認しなければいけません。そのようなことで、死と再生という意識も、あくまで現代を含めた一つの仮説として成り立ちうるかもしれませんが、今のところ明快にその是非をお答えすることができません。少し勉強させていただきたいと思っております。
それから、遺骸の遺棄ということをご質問いただいて、このご質問のペーパーは、お名前が記されておりませんが、遺骸の放置は、記憶の中に生きるのではないかと、興味深いご指摘をいただきました。もちろんそのようなこともあるかもしれません。現代人の意識の中にそのようなものがあるのも事実で、ひょっとしたら五百?六百年前の人間、それよりも何千年も前の人間も同じ感覚をもっている可能性はもちろんあるわけです。ですが、その意識の異同や変遷をこそ問う必要がある、と考えるのが歴史学の立場でして、これもちょっと勉強させてください。すみません。
それから、遺骸を放置している仏教とのかかわりがあるからこそ、葬式仏教が生まれたのではないかというご質問を受けているのですが、これは全くそのとおりだと思います。現象的にも連続するわけでありますから、本質的な問題を考えなければいけない。わたしの出した仮説が正しいかどうか、もう少し自分自身も考えて、皆様がたにもご専門の立場から教えていただきたいと思います。
同じく風葬・死体遺棄の問題については、あと二点ご質問をいただいております。当時の僧侶の場合はどうだったのであろうか。高僧という意味だと思うのですが、ご指摘をいただいております。これは多分確かだと思うのですが、顕密仏教の中での高い位の僧侶は、葬式、法要も行われるし、儀式もあったと思います。ただ問題は、十二世紀以前の場合には、そのような方であっても、墓や追善供養が連続しないというところが、佐藤弘夫さんのご指摘にもあったように、葬送や墓制に関する意識が全く異なるということだと思います。その点は、つまり、墓が忘れられてしまう。それが一般的であったというのは、少なくとも私にとっては衝撃ですし、皆様にとっても異世界といいますか、そのようなものとして映るのではないかと思います。もう一つは、これは非常に現代的な問題なので、小谷先生のほうにお答えいただいたほうがいいのかもしれないのですが、高額なお布施の問題と、これも匿名の方から頂きました。寺院の経済基盤はどうだったのかということです。現在の、高額なお布施に依存といいますか、頼っている葬式仏教に対して、これはいつから始まったのだと。かつての経済基盤はどうなのだというご指摘かと思います。
これについては、歴史学的には幾つか回答が出せると思います。一つは、田地や金銭のお布施、寄進の問題であります。寄進に関する様々な史料はたくさんありますので、私も論文を書いたことがあるのですが、ピンポイントで、一つ一つの儀式に対して、それを特定して、寄進やあるいは勧進ですね、勧進についてはお分かりだと思うのですが、そのような形で費用を集める場合があるというのが一点。それから、先ほどある方からご指摘を受けたのですが、「講」というものの役割があります。二十五三昧講も、いわゆる結社ということで、「講」の一つだと思いますけれども、様々な「講」が社会の中で機能しています。これは民俗の世界の中でも同じでして、「無尽講」とか「頼母子講」というものがそもそも宗教的な目的によって担われているということもあります。そのような経済基盤が確認できるわけです。
ただし、それと現代のお布施の問題がどうつながっていくのかは、これはあとの問題にもかかわるのですが、江戸時代の問題がよく分からないのです。江戸時代の、いわゆる体制の中で生きていた――と言っていいのかどうかも分からないのですが――仏教の中で、そのようなピンポイントの費用の拠出や徴収というのが行われていたのかどうか。この問題は、私の知るかぎりは、あまり研究がないのです。ですから、その点は大きな課題として歴史学は受け止めるべきだと思っております。
それから、戦国仏教そのものの時代、十五?十六世紀、あるいは江戸時代の問題について、二点ご質問をいただきました。これは望月先生から頂戴したものが一番大きな問題なのですが、湯浅は戦国仏教という概念を使って、仏教が地域に受け入れられていく過程を描いた、それは結構だというご趣旨だと思うのですが、しかしそれが近世的な新たな社会秩序の形成の担い手になっていったのだというところまで、果たして言えるのか、という、非常に難しいご指摘です。これは、体制仏教として江戸時代には檀家制度や寺檀関係というものがカチッと形成されていく、それに対して戦国までを見ると、実は体制の一つであったと論じたところとの溝、断層があるのではないかと、そこを明確にご指摘いただいたということで、これも痛いことなのだと思うのです。
やはり江戸時代の体制に至るにはもう少し別のファクターがありまして、国家的な宗教との関係や、それこそ民衆の中でそのようなものが選択されていくという問題がどのように伺えるのかという問題、実はこの問題も極めて研究蓄積が乏しいと思います。
江戸時代の檀家制度以降の研究はあるのですが、あと、私のやっているスタンスで、戦国仏教の研究はあるのですが、その間を埋める研究があまりない。というのは、実は史料がないということでして、わたし自身は、その点から逃げてしまいたい気持ちがあります。専門とはやはりズレますので。
ただ、観点を変えると、例えば近世の初期から、仏教が社会の中で、特に村落社会のことを申し上げていますが、様々な機能を担っていたという研究が、少しずつですが出ているようです。例えば、村の中で紛争が起こると、その仲裁に入っていく。つまり喧嘩の仲裁です。ガチガチの檀家で、ロックイン効果で固まっているだけではなくて、村という共同体そのものにアクセスする回路を持っていたということだと思うのです。その中でクローズアップされるのは、駆け込み寺です。中世にも、アジール(「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」)ということで、網野善彦さんがよく言われたような、マジカルな機能を寺院が担っていたということがありますが、江戸時代はそれが骨抜きにされるという議論があったかと思います。しかし駆け込みの問題も含めて、やはり村の秩序の中で大きな役割を果たしている部分がある。これはおそらく戦国期から連続性を考えなくてはならない問題だと思います。
それからもう一つは教育です。要するに、寺子屋を含めた、村の教育。先ほど、鈴木先生のお話の中に、リテラシーの極めて発達した日本社会のご指摘がございましたが、おそらくそれを担っているのは寺院でして、戦国期にはわずかですが史料があります。越前だったと思いますが、僧侶が教育をしている史料があったかと思います。それが満面開花していくのが江戸時代である。この二つを取れば、やはり、新たな社会秩序といいますか、そのようなものの形成に資する部分も確かにあったと言えるのではないかと思います。
そしてもう一つ、先ほど鈴木先生のほうにも質問をお寄せいただいた、天理大学のおやさと研究所の金子昭様でしょうか、ご質問をいただきまして、家族形態の問題ということです。これも非常に難しい問題です。先ほどの小谷先生のお話ではありませんが、家の終焉イコール墓の終焉ということだというお話で、それに対して、中世・戦国時代の庶民の家族形態について教えてくれというお話なのですが、この庶民の家族形態も一律ではいかない。十五、十六、十七世紀でかなり変化しているという研究があります。それで、十五世紀はほとんど分からないのですが、十六世紀になると、おそらく江戸時代の「夫婦かけむかい」という単婚小家族が基本だといわれているのです。これも、戦後はそういわれていたのですが、最近では、それほど一律に言えない。大家族もあれば、破壊された家族もある。家族を構成しえない人々は、日雇人、先ほどの日雇人のような存在になるのです。家族形態も非常に多様ですが、あえて言えば、江戸時代、十七世紀以降は単婚小家族化していく。それに対して、近世以前、十六世紀は、やはり有徳人が分解していくような、庶子とかそのような人々がいて、また下人のような存在を持っている、中家族のような存在が一般的だったのではないかといわれています。
ただし、それがどのような葬送関係に対応しているのかは、全く分かりません。私自身が多分勉強が足りないので、その点はできればこれから勉強させていただきたいと思います。
最後ですが、これも非常に大きな問題が匿名の方から寄せられました。戦国時代三百年、寺院と墓はどのような関係だったのか、というものです。これも、先ほど申し上げたように、十五、十六、十七世紀で家族形態が変わり、その中で板碑などがなくなって、供養塔が墓標化していくというような、膨大な作業を各地域でやらなければ完全には見通すことはできない課題でして、生半可なことは言えないことでもあります。
それから、鳥辺野などの仏教の、京都・鳥辺山などと仏教の関係をお知らせくださいというお言葉なのですが、これもわたしの説明の不備でして、そのような周縁的なものが全くなくなるわけではありません。例えばそこに念仏者や時宗のお坊さんが入って供養をして、その無常堂がやがて寺院になっていくということで、例えば化野の念仏寺のようなものができるという、一つのあり方もあるのだと思います。ですから、佐藤弘夫先生は多分全部ご承知の上で三つにきちんと分けたのですが、実はきっちり分けられるものでもない。もっと多様ものがあるのではないかと思います。お答えになりませんが。
ちょっと長くなりましたが、以上でよろしくお願いいたします。
司 会 湯浅先生、ありがとうございました。
では次に、小谷先生、よろしいでしょうか。
今、湯浅先生に、すべての質問に網羅的にお答えいただきましたが、時間に制約も御座いますので、無理にすべての質問にお答えいただかなくても結構でございますので。それでは、どうぞ。
小 谷 まず最初の質問は、直葬の増加は、葬送儀礼は元々地域社会の仕事だったけれども、それが機能しなくなったのが原因ではないのか、また、東京に出てくると親族とのつき合いもなくなるし、出てきてもらうのに遠方だからではないのかという点ですが、そのとおりだと思います。これは東京だけの現象ではなくて、地方でも同じだと思います。そして、地方ほど、変わり出したら、変化が速い。例えば、地方では、つい、最近までは家でお葬式をするというのが当たり前で、葬儀会館ができても、だれが利用するのだと思われていたかもしれませんけれども、だれか一軒が利用すると、あっという間に変わってしまう。その変化のスピードは、地方ほど速いのです。ですから、直葬は大都会の問題で、地方では大丈夫だと思うのは大間違いです。
それから二つめの質問は、家族が悩み苦しむことは、むしろ現代人の成熟にとって必要ではないか、どうしてそこに僧侶が介入する必要があるのかというご指摘でございます。私がお話しさせていただいたところで言えば、予期悲嘆とグリーフの領域です。特に予期悲嘆の過程には、私はここに僧侶が介入すべきだと思っています。それはなぜかというと、今まで経験したことのない問題に直面している家族に対し、死を受容させるためには専門家の手助けが必要だからです。いろいろな専門家が関わるべきですが、葬式仏教を僧侶はになっている以上、伝統仏教の来世観・死生観に基づいて、死を受容させる援助が可能なのではないのかと思っています。
三つめの質問は、葬式は今、現世中心だった新宗教も、人生のトータルな救済の位置づけにしつつある。残された遺族のケアは、この点で、伝統仏教よりも、現世中心の新宗教によるもののほうが優位に立つのではないのかという点です。私は宗教や仏教のことはよく存じ上げませんので、とんちんかんな回答かもしれませんが、残された遺族のケアが必要だと申し上げたのは、人々の悲しみや苦しみによりそうのが宗教の役割なのであれば、伝統仏教が関わるべきではないのかと思ったからです。また、何の信仰もない人にとって、伝統宗教に対する忌避感は少ないことも、伝統仏教が活動するうえで優位性があります。私も何の信仰もございませんけれども、町の中に日蓮宗のお寺があった場合に、入ることへの抵抗感は、新宗教の施設に入るより低いです。そのような意味で、伝統仏教にがんばって頂きたいと思います。
私自身、実際に人々の心に寄り添っているのは、新宗教のほうであろうと思います。ですから、新宗教がこれだけ伸びてきたのだと思います。そのような意味では、救いをすすんで信仰に求める人にとっては、新宗教のほうが優位かもしれませんけれども、そうではない人にとっては伝統教団のほうが忌避感がないという意味で、優位性があるのではないのかなと思います。
四つめの質問は、「親への供養は本来、生きているうちに行うべきものと思います。今それが崩れてきたのも仏教の責任だと考えられますか」というものです。私は仏教のことをよく存じ上げないので、「供養」の意味を知りません。ですから、仏教の責任かどうか分かりませんけれども、専門の社会学の観点から申し上げますと、一つは核家族化が大きいと思います。核家族で、信仰が継承されないという問題もありますし、祖父母から子供、親から子供、子供から孫という、価値観や教育が伝達されない。それが親子関係にも影響しているのかなと、私は考えます。信仰が継承されなくなった点については、子や孫に教化できていない責任が仏教にもあると言えるかもしれません。
それから、「介護する家族や残された遺族、医療従事者など、現在ケアを受けておらず、仏教が役割を果たせる分野があることはよく分かりましたけれども、具体的にどのような方法でその場所に入ることができるのか」という質問です。よく、病院に坊さんは入れないのではないのか、どうやって入っているのだというご質問をいろいろなところでいただくのですけれども、私はどうしてお坊さんが入れないのかが不思議です。その原因は、多分お坊さんが袈裟を着てこられるからです。袈裟を着なければいけないのかについては、私は門外漢でございますのでその辺のことはよく分かりませんが、袈裟を着て入るのは、他の患者にとっても「死」をイメージさせるという点で拒否されると思います。
最後のご質問は、残された家族のケアをどうしたらいいのかという問題です。月参りの習慣があるところは、これがケアをする場だと思います。ご家族と茶飲み話をするということでもいいと思いますし、大切な人を亡くして孤独にある人たちがお寺に集まる機会を作るということも、コミュニティの再構成にも大きな役割を果たすと思います。先ほどお寺・寺院という場所は非常に優位性があるというお話を申し上げましたけれども、ハードを使って何をするのかというのは、あとは先生がたの問題ではないのかなという気がしています。答えになっているかどうか分かりませんけれども、以上でございます。
司 会 ありがとうございました。
さて、本来、初めに、なぜ今回の教団論セミナーを「『葬式仏教』を考える」というテーマで開催するのか、何を目的とするかというようなお話をしないといけなかったのかもしれません。
ご案内のかたも多いと思いますけれども、ちょうど、ほんの二?三日前に、幻冬舎新書として、『葬式は、要らない』というストレートなタイトルの、島田裕巳さんの本が出ました。まだ私も読んでいる最中なのでございますが。
現宗研では、教化センターの連絡会議というのを例年開催しております。昨年、その会議を開きましたときに、あるセンターから、S学会の「友人葬」というものにかかわるビデオ資料のご提供をいただきまして、皆で拝見いたしました。ちょうど鈴木先生に論じていただいた、お釈迦様は出家が葬儀にかかわることを禁じておられるという話がとても大きく取り上げられて、彼らの論拠の一つとして挙がっていたというようなことがありました。
そんなことも御座いまして、今回はぜひ鈴木先生にご登壇願おうというような運びになりましたのですけれども、そのビデオにご出演になって、釈尊は出家者が葬儀にかかわることを禁じられたという話をしていらっしゃったのが、島田裕巳さんでございました。もちろん一方的にS学会に加担して話しているということではないのですけれども、大変売れっ子でおられますから、本宗内でも、あちらこちらで呼ばれて、講演などをなさっておられます。東京でも先年お呼びして、『立正安国論』の話をしてもらったりというようなことがありましたが、そのようなことにも参画されている人だということもご理解いただき、注意していただければと思います。
この島田さんの本の中に、葬式はいらない、葬式は贅沢である、という話が出てまいりました。贅沢だというのは、日本では、葬式に二百何十万円もかかって、諸外国に比べて高額である、というような話で御座います。扱われている数字の信憑性自体に問題があろうとも思いますが、葬式は贅沢だという島田さんの御指摘を読んでおりましたときに、戦時中に使われた「贅沢は敵だ」という言葉を思い出しました。
私もほぼ湯浅先生と変わらない年齢でございますので、その時代のことを同時代として経験しているわけではないのですけれども。
さて、その「贅沢は敵だ」ということについては、そういうスローガンが書かれている看板の、その「敵」という言葉の上に「素」という字を書き入れて、「贅沢は素敵だ」と書き直した事例がある、それこそが庶民の声だったというのを、どこかのものの本で読んだ記憶があります。葬式が贅沢なのであるとすると、その贅沢が〝素敵〟であると、どのようにしたら思って頂けるのか、やって良かったと思って頂けるような葬式に、どうしたらして行けるか、というようなところに、私たちの課題はあるのかなという気もいたします。
もちろん、葬式だけやっていればいいということにはなりませんし、先ほどの小谷先生のご指摘などにも応えていかないとならないのだと思います。開催趣旨にも書きましたような、葬式仏教に対する様々な批判をきちんと受け止めて、その上で、現実的には既成教団の基盤になっているところの葬式仏教というものに立場を置きながら、仏教者として何をなすべきか、というようなところを、これからの時間で考えて行きたいと思います。
三人の先生のお話を承っていて、先ず、鈴木先生が社会運動ということをおっしゃいました。社会運動というのは、仏教を信条とする人たちを結局増やすことだ、布教を強化していくことだという趣旨であったかと存じますけれども、そうだとすると、インドでそれをするとカーストを形成するという話になるから、できなかったのだというお話もされておられましたが、その二つのことのつながりがちょっと見えにくいように思いますので、まずその辺をご説明いただけないかと思います。
そして、社会運動、あるいは湯浅先生はコミュニティという言葉をお使いになっていらっしゃいました。小谷先生から、いま、寺院に対する忌避感は――有り体に言うとマイナスイメージでしょうか――少ないというお話がありました。そうではあっても、おそらくお寺に入ってきていただくだけのプラスが乏しい、魅力が少ないので門をくぐってきていただくことも少ないのだろうとも思いますが(私の寺だけの話かもしれませんけれども)、その魅力を増していくだけものをどう拵えていったらよいのか。プラスイメージを増やしていく工夫、つまりは社会運動化ということであり、コミュニティとのかかわりを如何に構築して行くか、ということになるのでしょうか。そうしたことへの何か御提言を頂けないでしょうか。
もう一つは、これも湯浅先生から、佐藤先生の資料をご紹介いただきながら、現世観と他界観というようなお話が御座いました。おそらくこれは、小谷先生の来世観というお話と直結してくるお話なのだと思います。スピリチュアリティというようなものは結構喜ばれて、昨今も「パワースポット」などという言葉がはやりになっているようでございます。そのようなものについては割に抵抗感なく受け入れてくださるような方が対象であったとしても、他界観・来世観となると、なかなかきちんとお伝えするのは難しいのではないでしょうか。私などは檀信徒をきちんと教化できている、できる、というだけの自信が、正直に申し上げて、あまりないのですけれども、その辺のことについて、何かお考えなり、「こうすればよいのでは」というようなものが、もしおありになれば、――なかなかそうは問屋がというところであろうとは思いますけれども、何かご示唆をいただければというようなことで、伺わせて頂きたいと思います。お三人の先生方にはに、少々無理やりな質問で恐縮なのですけれども……。
鈴木先生から、お願いできますか。
鈴 木 社会運動のところでございますか。私の専門はインドの仏教ですので、そちらのほうからしゃべりますと、とにかく、インドの仏教徒がわたしたちと同じような形で存在していたことは、まず絶対にないのです。インドの仏教の中心は、あくまでも出家者です。そして、在家者というものは、出家者を外護する存在として。出家者のパトロンですね。彼らは出家者が何を言っているか分からないのです。でも、何かすごい人らしい。だから、布施しておけばいいだろう。そして、時には何か、儀式をやってもらいたい。そのようなつき合いの仕方です。在家の社会生活というものは、全面的にカースト社会にゆだねてしまっている。たくさんの大乗経典はできましたけれども、それはやはり、ある意味では実現しない夢物語のようなものであった。それが、日本では実現できると。
つまり、単に「このお坊さん、なんかすごそうだから、お布施しておこう」というのではなくて、仏教の教えを聞いて、「なるほど。ああ、こういう生き方をしていこう」。結局それが、本当の意味での葬式仏教になるのではないか。つまり、死んだときに葬儀式をやるだけではなく、ある意味では死ぬ以前、そしてもっと元気なときからずっとずっと仏教に従って生きていけば、その当然の延長として、仏教徒として死ぬわけです。そして、仏教徒としての来世がある。そして、そのような人たちが増えていくようにする。基本的には説法を通してのことなのだと思うのですけれども、人々とかかわっていく。いわゆるリテラシーとして、それを受容する能力は、幸い日本人は持っておりますし、警戒心というのでしょうか、別に新しい宗教が危ないと申し上げるのでは決してございませんが、一般のかたからということで、小谷先生からございましたように、そのような意識があるようでございます。であるならば、それを利用・活用しない手はない。仏教のことをもっと、相手に応じて教え、それが生きる指針になっていく。それが、わたしたち教師というものに与えられた役割ではないか。それが社会活動だろうと思うのですが、お答えになっていますでしょうか。もっと直接的なことですか。
司 会 いえいえ。結構です。来世観のほうは、ではまた後ほどということで。
湯浅先生は、歴史学というのは、その時代の意識の復元なのだ、現代との相違を考えていくのだと仰っておられました。他界観・来世観となりますと、現代では、そうした観念自体が持たれにくくなっているという現実があるかと思われます。そうした中にあって、しかし、先ほど申し上げたような、スピリチュアルであるとか、パワースポットであるとか、そのような意識というのは、なくなっているわけでもない、というようなところが現代日本、あるいは現代日本人なのではないかと思われます。そのような中で、新たなコミュニティ作りというようなものを宗教者・仏教者が目指していこうとする場合について、御専門のお立場から、何かアドバイスをいただけないかと思うのですが。
湯 浅 私でよろしいですか。極めて難かしい問題でして、おそらくお答えできないと思うのですが、その前に、今の社会活動、あるいは社会集団を形成しないということで、よろしいのでしょうかね、鈴木先生のインドのお話の関連で、世俗的なことはカーストの社会に全部任せるということなのですね? とても衝撃を受けて聞いておりまして、もちろん、日本に仏教が伝来して、中世に入って顕密体制ができるなどというようなことの中で、そのようなものがどのように変容したのかという、恐ろしく難しい問題を、私が全く手が出ないような問題を考えなければいけないのですが、もしそれを踏まえるとすれば、日本の中世社会を、緩やかなカースト社会だと言う研究者がおりまして、やはり種姓観念を基にした差別といいますか、そのようなものが厳然としてある社会であると言われています。おそらく顕密体制といわれるような、ある種の分断支配といいますか、差別の構造というようなものがあるとすると、適合するようなものになるのかなと。このような位置づけが本当に正しいのかどうか、私自身おぼつかないのですが、そうすると、聖の世界から、鎌倉仏教の祖師を経て、それが集団化していくというのはすごく大きな問題であって、それが実は社会に定着していく一つの回路であったということになるのかなと思いまして、戦慄を持って聞いていたわけなのです。
それと裏腹に、多分、集団化すると、紛争が起こるわけです。社会集団というのは、自分たちの規律や行動様式をもって他者を排除するわけですから、中世社会の集団というのは、年がら年じゅう、紛争を起こしているわけです。これは僧侶の集団も例外ではありません。これはお話しするまでもないと思うのです。そうすると、中世社会の中で、最近いわれているのは、「自力の世界」といいまして、どこかにもたれかかったり、どこかに支配されるのがいいのか、それとも、自分たちの中で、ゴツゴツしてはいるけれども、自立をしていくのがいいのか。もちろん、これは集団のことです。そのような議論がずっとありまして、その問題と、戦国仏教といいますか、仏教の後半の動きはやはりこの問題と一緒に考えなければいけない、というこれは研究上の問題ですが、感想を持ちました。
そのうえで、髙佐先生のご指摘にもどりますが、とても難しくて、私は先ほど小谷先生のお話を聞いて、全くそのようなことがこれからの課題になるのだということを本当によく分かったような気がしました。コミュニティとかスピリチュアリティとかいう、社会学のかたがたが使われていたかと。広井良典さんというかた、千葉大の社会学の先生だったと思いますが。やはりもう少し議論が必要であると言わざるをえない部分がありますし、私自身は、博物館や行政の一環として、地域コミュニティのようなものにそれなりにかかわってもいるわけで、その中でできることというのは、寺院が過去ずっとそこにあって、例えば、地域社会の中でちゃんと歩くと、旧村のあたりの風景と、新しい風景というのは全く異なる。実は、そのようなものは、地元のかたには見えるわけです。ところが、新しく入ってこられたかたは、そのようなものは全く見えない。土地の名前である字であるとか、お墓であるとか、寺院のある場所とか、地面の緩い場所とか、水が出る場所とか、そのような環境の問題を問い続けていくのもやはりコミュニティ作りの一つなのではないかなと思います。そうした点で、歴史学というのは、ひょっとしたらお役に立つことができるのかもしれないなと思っています。
司 会 ありがとうございます。今、鈴木先生のご発表に対する湯浅先生からのコメントがありましたけれども、鈴木先生、何かございますか。
鈴 木 先ほど言い足りなかった、集団のことについても触れつつでよろしいでしょうか。先ほど、インドを見ていて、最初は違ったように見えたけれども、実は日本と似ているなという部分は、その人たちの生きざまの部分なのです。教義は大きく違います。例えば、今のインドの仏教徒も、東南アジアの仏教徒も、チベットの仏教徒も、特に『法華経』を信仰しているわけではありません。ただ、彼らがいかに、自分の聖性、聖なる者としての存在を保とうか、そして、いかに自ら修行し、人を救おうか、そして教団を存続させようとしているのか、というところに私たちと共通性があると感じたわけです。
宗教には、教義、このような教えを説くのだという部分と、ではどのように生活するのだという、単純に分けてしまうと二つあると考えて、ちょっと乱暴かもしれませんが、簡単に二つに分けてみます。ここに、経済学などの用語ですけれども、「上部構造」「下部構造」という概念を持ち込んでみます。いわゆる教義の部分が上部構造、そして生活の部分が下部構造になるのです。教えの部分を中心に、教ですね、教と律で、教の部分を中心に引き継いできたわたしたち東アジア仏教徒は、どうしても上部構造のことに目が行きがちです。そして、イデオロギー論争をして、分派を繰り返す。本当は、人間は上だけで生きているわけではない。下も含めて生きているわけです。ただ、日本にはそこはうまく伝わらなかった。例えば、イスラム教やユダヤ教という宗教は、上部構造も下部構造も両方持っているのです。まず、このようなものを信じろという教義もあるし、このように生活しろ、これを食べてはいけない、全部決まっています。仏教も南アジアや東南アジアでは決まっていたのですが、気候などの自然条件が異なることもあり、東アジア社会には下部構造が伝りませんでした。
実は、この葬式の話というものは、まさにその下部構造と上部構造の両方にまたがってくる。そのときに上部構造だけで話をしていると、話がかみ合わないことがあるような気がいたします。自分たちが今、仏教のどこをどうやっているのかということを意識する。そして、今の仮説がもし有効であるとするならば、上部・下部、どちらのことをやっているのかということを整理しておかないと、議論が錯綜することがあるように感じました。
司 会 一般には、下部構造も大事だという話ばかりになってしまっているような気もいたしますけれども……。
とは言いつつ、何しろ「法華経・日蓮聖人・日蓮教団論研究セミナー」でございますので、日蓮宗としてどうするのだという話にしなくてはなりません。
小谷先生は、伝統仏教寺院のほうが忌避感が少ないとおっしゃってくださったのですけれども、今、お寺を見た時に、そのお寺が何宗であるか分からないという実情がございます。お檀家さんのご葬儀があると、葬儀屋さんから宗派を聞かれてしまうということが、私の寺などはしばしばあったりするわけです。いかにわたしが葬式仏教ができていないかというだけの話なのでございますけれども、そのように、非常に宗教性が薄められた状態と申しましょうか、通仏教的な、日蓮宗としての特色を余りを出さないような形で、習俗、あるいは伝統と言われるようなものの中に入り込んでいるからこそ、伝統仏教寺院には忌避感が少ないのだと思うのです。
逆に言えば、小谷先生が、伝統仏教よりも新宗教の方が忌避感が高いとお思いになるのだとすると、それは「教え」をやっているからではないか。上部構造がかなり伴って、教えを実践しているからというような話になってくる部分があるのではないかと思うのです。
例えば日蓮宗であれば、霊山往詣というような来世観を教義的には持っているわけなのですけれども、それを提示していったときに、果たして受け入れていただけるのかな、というのが、有り体に言って、あります。「それはおまえの教化力の問題だろう」と言われてしまえば、それだけのことなのでございますが。先ほど申しました、薄められた宗教意識の中に、パワースポット程度の話なら皆さんそれほど抵抗感がなくても、そこへ教えとしての来世観を、ということになった場合、日蓮宗が「西方極楽浄土」と言うわけに参りませんし、当然、「霊山浄土」ということをお伝えしようとすることになります。果たして、それが一般に受け入れられるのでしょうか。受け入れていただけますかと伺っても仕方がないのではございますけれども、その辺の、命や死に向き合い、寄り添うということと、来世観を?醸していくということについて、それを小谷先生に聞いてはいけないのだなということを思いながら、なのでございますけれども、何かアドバイスをいただけないかという、厚かましいご質問をしたいのですが……。
小 谷 大概の日本人は信仰がないと答えますけれども、ほとんどの人は、宗教的な心は持っていると思うのです。例えば、何もないと思っていたら、「千の風になって」のあの歌に共感しないと思いますし、初日の出を拝むとか、お寺に行くと心が洗われるとか、そのような宗教的な心はあるのだと思いますけれども、宗教教団が怖い、気持ち悪いという感覚は強い。特にオウム事件以降一つの何とか教に所属することへの恐怖心、偏見のようなものが世の中にすごくありますが、パワースポットやスピリチュアルのような、宗教チックなものへの関心は、多くの日本人が持っていますし、また若い者ほど高い傾向にあります。〝何々教〟ということへの忌避感はすごくあると思いますが、伝統仏教に対するそれはまだ低いということです。
それと、われわれがお寺を選べないということが一番大きな問題です。日蓮宗の菩提寺があれば、西方浄土の来世観がいい人は、そのような宗派のお寺を選んで、自分の葬式をしてもらう、という選択ができない。檀家制度は現代においてはもはや存在しないのですが、現実、先祖を想うと菩提寺とのつながりは、切れない。そのようなしがらみの中にあって、寺を選べない、宗派を選べないことによって、寺離れが起きている。「うちの寺は日蓮宗なんだけど、本当は自分は浄土真宗のあの僧侶がいい」という人だっていて、そのようなことが問題をややこしくしているのかなと思います。
司 会 ありがとうございます。こういった場で、このようなことを伺うのも如何かと思いながら、懇親会の席で伺ったようなお話をこの場でご披露させて頂きたいのですが、小谷先生は、ご自分に万が一のことがあったときに、お葬式を挙げてもらうということを決めているお坊さんがいらっしゃるということをいつぞや承りました。どうしてその方にとお思いになったのか、その方の何が、信仰はないと仰っている小谷先生の心をそこまで引きつけたのかということを、ご参考までに聞かせていただけませんでしょうか。
小 谷 お人柄がすばらしいのもありますが、そのお坊さんのお経がとてもすてきだと思ったから。私は、先ほどお葬式において読経と法話はすごく大事で、最大の布教のチャンスだと申し上げました。まさしく、「何だか分からないけど、このお坊さんのお経を聞けば心が安らぐな、この人のお経ならあの世へ行けるかな」というような、何かぼんやりした感覚があるのです。
司 会 ありがとうございます。「あ、あの小谷みどりさんでもそういうこと言ってくれるんだ」というので、勇気づけられた方がたくさんおいでになるのではないかと思います。
ぼちぼちお時間が迫ってまいりましたので、取りまとめをしないといけないのでございますけれども。開催趣旨を申し上げた際に触れましたように、如何に葬式仏教を魅力的なものにしていくかということなのだろうと思いますし、同時に、それは如何に葬式仏教にとどまらずにいられるかということと表裏の関係になってくるということだろうと思います。小谷みどり先生ですらあのような感覚をお持ちなのですから、われわれ一人ひとりが魅力的な僧侶であればというようなことに、結局、収斂してくるのかというような気もいたします。私が取りまとめをしてもいかがなものかと思いますので、それぞれの先生がたに、それぞれのお話を踏まえられたうえで一言ずつご感想をお伺いいたしまして、締めくくりとさせていただければと思います。では、鈴木先生から。
鈴 木 接着剤というお話がありましたが、宗教を英語ではreligionといいます。このことばは元々「re」と「ligi?」からできているのです。「re」というのは「再び」です。regainやrecoverのように、「再び」です。「ligi?」が、つなぎ止めることです。合わせることです。いったん離れてしまったものをつなぎ合わせるのが宗教の役割だと、古来、理解されてきました。そのような中で、日本人というのは宗教心がないとよく言われるのですけれども、背景には、再結合(=宗教)がいらないように、「最初から和を保ちましょう」というような文化があったのではないかと思います。その中で、和が成立しないようなとき、例えば、湯浅先生の御専門である戦国でしょうか。あとは現代かもしれません。そのようなときに、何か壊れていったものをもう一度結びつけて、紐帯を作っていく。そこにreligionの役割が求められるような気がいたしました。仏教が、religionとしてきちんと機能するかの正念場だと感じております。
司 会 ありがとうございました。湯浅先生、お願いいたします。
湯 浅 見事なご指摘の次はやりづらいのですが、私は先ほど申し上げたことに本当に尽きるわけでして、お二人の先生や髙佐先生がいろいろと誘導されている問題について、とても目を開かされたという部分があります。繰り返しになりますが、そのようなものに対して歴史学というものもやはり開いていかなければいけないだろう、という思いだけは、強く持っております。今、鈴木先生がおっしゃったように、つなぎということであれば、まさしく歴史上においてもそれは妥当することであります。その結果、長い時代を経て、その地域にしっかり根づいたもの、そのようなものについては、歴史学というものは大変重視して、その成り立ちの淵源から現代まで、様々な形でそれを位置づけようと努力をします。それはひょっとしたら、現代もそのようなものが、葬式仏教なり、鎌倉仏教なり、戦国仏教なりが必要とされていることの一つの条件なのかもしれないなと、今思っておりました。私のできることはその程度かもしれませんが、そのようなことで、また模索を続けていきたいと思います。
司 会 ありがとうございました。小谷先生、よろしくお願いします。
小 谷 私は仏教を勉強したことがないので、鈴木先生や、歴史の観点からの、湯浅先生のお話は、とても勉強になりました。どの宗派も、若いお坊さんたちはこのままではお寺がいけないという危機感をすごくお持ちですが、何をすればいいか分からず、危機感ばかりが空回りしています。僧侶がやるべきことはたくさんあると、私は思うのです。お坊さんは、すごくやりがいのある立場だと思います。お坊さん自身がそれに気づいていないということが、寺離れの一つの理由なのだと思います。お坊さん自身が、自分が信じる教えをぜひ広めたいという信念と強い発心を持って、活動していただきたい。今の葬式仏教であれば僧侶は必要ないという声は強くなっていきます。しかしそれでいいのか。本来の葬式仏教であれば社会のニーズは絶対、私はあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
司 会 お優しい言葉をありがとうございました。そろそろお時間がまいっております。小谷先生のお言葉を使えば、葬式仏教を本来の葬式仏教に立ち返らせること。鈴木先生の言葉を使えば、葬式仏教を進化させること。三人の先生のご講義をいただいて、必ずやそのようなことにつながっていくセミナーになったのではないかと考えるところでございます。「葬式は、要らない」などというような、軽薄な言辞が出ないような社会をつくっていくために、結局はわれわれ一人ひとりがどれだけ魅力的な宗教者になれるかということに―このようなお話をすると、いつもそこに行き着いてしまうのでございますが、―叱咤激励をいただいたのかなというような思いがしているところでございます。どうも三先生、大変ありがとうございました。フロアの皆様も大変ご協力ありがとうございました。お疲れさまでございました。それでは、閉会式に移らせていただきます。
では、三原現代宗教研究所長の発音によりまして、まず玄題を三唱いたします。
三 原 南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。
司 会 引き続き、三原所長よりごあいさつを申し上げます。
三 原 六時間にわたる、長いセミナーでございました。ご講演してくださいました講師の先生に、厚く感謝申し上げます。また、六時間もの間、静かに先生がたのお話を受け止めて、聞いてくださった参加者にも、厚く御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
私ごとになりますけれども、現宗研所長に就任しまして一カ月半になります。金帰・月来でございますが、たまさかの土曜日、日曜日には、一日中、東京をブラブラ散歩して、時間をつぶしているということでございます。先日も東京駅の近くのオアゾの丸善書店へ行きましたら、松岡正剛さんという人の特集をやっておりました。そこで、『日本力』という、彼の著書を一冊買わせていただいたわけでございますが、その中に、松岡正剛さんを取り巻く外国人がいっぱいいらっしゃるのです。現在では、日本のすばらしさというものは、日本人には分からないと。外国人が、この日本のすばらしさに気づいていると。その外国人の一人が、日本人はなぜ日本仏教のすばらしさを学ぼうとしないのでしょうかという発言をしているわけでございます。
今日は、三人の諸先生のご講演の中から、必ずや皆さんがたも自分自身の可能性というものに気づかれたのではないかなと思うわけでございます。しかしそのためには、新しい視点というものをわたしたちは持つ必要があると思います。どうぞ、今日のご講演の中からその宝物を掘り出してお持ち帰りいただきたいと、このように思うわけでございます。今日は、大変長い間、ありがとうございました。
司 会 それでは、これをもちまして、第二十回法華経・日蓮聖人・日蓮教団論研究セミナーを閉じさせていただきます。どうもお疲れさまでございました。鈴木先生、湯浅先生、小谷先生に、もう一度盛大な拍手をお願いいたしたいと存じます。三先生、どうも大変ありがとうございました。皆様、大変お疲れさまでございました。
後 記
日蓮宗現代宗教研究所主任
髙佐 宣長
平成二十二年二月九日、「『葬式仏教』を考える」をテーマに、第二十回法華経・日蓮聖人・日蓮教団論研究セミナー(以下「教団論セミナー」と略記します)を開催いたしました。
この小冊子は、当日の模様を収録したものです。
「葬式仏教」―「現代の仏教を、葬式や先祖の供養をするだけだとして、非難の意をこめていう語。」と或る辞書にはあります。
伝道教団を標榜する日蓮宗にあって、「葬式や先祖の供養をするだけ」で充分であるとはもちろん言えませんが、本宗に限らず、現代日本の伝統仏教が、基本的に「葬式仏教」であることは否めないところであり、葬儀や年回法要が多くの寺院の経済的基盤を支えて来てもいます。
「葬式仏教」とはそんなに無価値なものなのか、「葬式仏教」の本来の面目とは如何なるものなのか。「葬式仏教」についての批判は批判として受け止め、「葬式仏教」に対する危機感を共有しつつも、日本仏教の立ち位置としての「葬式仏教」を再評価したい。そんな思いから、このセミナーを企画いたしました。
そもそも仏陀釈尊は出家者が葬儀に関わることを禁じられたのである、という議論があります。
詳しくは、鈴木隆泰師の講演に譲りますが、釈尊はその最期に当たり、出家者が自らの葬儀に関わることをお認めにならなかった、と長らく信じられて来ています。
筆者自身、学生の頃、そのように記した書物を読み、やがて、日蓮宗僧侶、日蓮宗寺院住職として、檀信徒の葬儀を営むようになってからも、その涅槃経の経説を、ノドに刺さったトゲのように感じながら過ごしていました。そして、教団というものは往々にして教祖の意思を裏切ることによって成立しているものである、などと解ったようなことをつぶやいていたのです。
平成二十一年の春、現代宗教研究所の研修会に、鈴木師においで頂いた折りに、それは「シャリーラプージャー」という語の解釈が誤っているのである、という師の所説を伺い、なるほど、と思いました。
その後、八十一頁の筆者の発言にありますように、昨年六月に開催した、その年の「教化センター連絡会議」に於いて、或るセンターの方から、S学会の「友人葬」に関わるビデオを御提供頂き、観る機会を得たのですが、そのビデオの中でこの問題がかなり大きく取り上げられ、「友人葬」の根拠の一つとされていました。その際も、出席していた各センターの代表の方々に鈴木師の御所見について御紹介したのですけれども、これは是非、当研究所としても、広く報せるように努めるべきなのではないか、と考えました。
というような次第で、昨秋、この教団論セミナーのテーマについて検討し、「葬式仏教」の再評価、という方向立てをした際に、講師として筆者の頭に先ず浮かんだのは鈴木師でした。
ちょうどその頃、湯浅治久先生の中公新書『戦国仏教』が、研究所、或いは宗務院で話題になっていました(昨年一月の刊行ですから、研究所内で話題にしたにしては、少し遅いかもしれませんが‥‥)。
鎌倉仏教が地域社会に根付いて行く過程は、「葬式仏教」が定着する道筋でもあったということについて、本宗の例を主にされながら論じられている、大変示唆に富んだ書物であるということで、「葬式仏教」をテーマとして教団論セミナーを開くのなら、是非この方の話を聞きたいという田澤元泰所長(当時)の鶴の一声で、湯浅先生をお招きすることが決まりました。
教団論セミナーは、公開講座部分の講師を二名とするのが通例ですので、慣例通りであれば、これで講演の依頼をする段取りになるのですが、そうなると、現代日本に於ける「葬式仏教」の再評価という問題を、きちんと論じないままになってしまう畏れが出て参ります。鈴木師や湯浅先生にその辺りのことについても触れつつ講じて頂くことも考えられましたが、「葬式仏教」は再評価されるべきであるけれども、それは「いまのまま」で可いわけではない、ということを、やはり別の講師に話して貰った方が、セミナー全体の構成が整うであろう、そして、なるべくなら、この問題は僧侶でない人に話して頂く方がよいのではないか、という相談になりました。そこで、『なぜ寺院は公益性を問われるのか』(臨床仏教叢書)などで、葬式仏教の公益性という観点から御見解を発表されておられ、当研究所が共催している日蓮宗の十一の教区の教化研究会議のうち四教区で講師をお勤め頂いていた小谷みどり先生を、という運びになりました。
と、ここまでが、昨年秋の、本セミナー企画段階の話なのですが、その後、葬儀をめぐる問題が、改めて世間の高い関心を集める状況になっていることは、本冊子を手に取られるような方であれば、申し上げるまでもないことかと思います。
シンポジウム部分でも触れておりますように、本セミナーが開催される直前に、島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)が刊行されました。三十万部を超えるベストセラーになっていると聞き及びます。氏の議論には多くの難点がありますが、世間の或る「空気」を掴んでいることは否定出来ないところであり、それが「葬式仏教」のマイナスイメージと密接に関係していることは、間違いのないところでしょう。
今年の五月には、大手流通グループのイオンが「お坊さん紹介サービス」を始めて、反響を呼んでいます。
昨年の秋から葬儀業に進出していたイオンは、葬儀の際に僧侶を紹介する事業を開始し、戒名の「ランク」毎に、お布施の「目安」を提示しました。本宗を始め、八宗派、約六百人の僧侶と連携しているとし、「寺院紹介サービス」と銘打ち、「きちんとした礼拝施設(お寺)を持ち、戒名を授ける資格(住職資格)を持った」僧侶を紹介するとして、当初は、「八宗派の総本山から許可を得て」いるなどと発表していました。
仏教会からは困惑や批判の声も聞かれ、イオン側もホームページからお布施の「目安」を削除するに至っていますが、どちらかと言えば、世間はイオンの「明朗会計」を支持しているようでもあります。
これもまた「葬式仏教」が本来のものになっていない、或いは、その進化が不足しているが故に起こっている事象であると言えましょうか。
教団論セミナーは、これまで日蓮宗関係者に限った公開講座として開催して来たものですが、今回は、当研究所も会員となっている、教団付置研究所懇話会に加盟している他教団の研究所にも御案内しました。
そして、従前は、宗門教師に配布して来たのみであった講演録を、日蓮宗新聞社から刊行して頂き、江湖の眼に触れることが出来るように致しました。
洛陽の紙価を高める、というようなことはないであろうにもせよ、仏教、宗教、文化に関心を持たれるひとりでも多くの方々に読んで頂けることを期待しております。
尚、日蓮宗新聞社の西條義昌師には、書物として上梓される過程の一切について手を煩わせました。表紙も、師のデザインであることを申し添え、感謝の言葉に代えます。
(平成二十二年十月十三日)