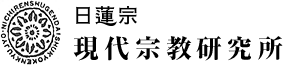記事公開日:2019年01月17日
第109回歴博フォーラム 死者と生者の共同性ー葬送墓制の再構築をめざしてー
【シンポジウム】
第109回歴博フォーラム
「死者と生者の共同性ー葬送墓制の再構築をめざしてー」
【主催】
国立歴史民俗博物館(大学共同利用機関法人 人間文化研究機構)
【共催】
早稲田大学人間科学学術院
【日時】
2018年12月15日 13時00分~17時00分
12月16日 10時00分〜17時00分
【場所】
早稲田大学大隈記念講堂
【発表者】
Ⅰ 無縁化への道程
発表1
「位牌・墓標と葬送」
谷川章雄氏(早稲田大学・教授)
この発表は、社会が無縁化する以前の近世〜近代の時代を中心として、位牌・墓標に注目し考古学的観点から、当時の人々の死生観について迫るという内容でした。
時代を経るにつれ、位牌・墓標の形態や扱い方は様々に変化し、両者に共通する点が次第に詳らかとなります。
位牌・墓標のどちらも、形の大きさや種類、戒名は身分の位に対応しており、両者には関連性があると言えます。
近代に入ると、「先祖代々」や「○○家之墓」という標記の位牌・墓標が登場します。位牌の場合は、これを「操出位牌」と呼び、「家」の中に「個人(故人)」を包括していくようになります。
『明治大正史 世相篇』(1931、柳田国男/著)の中では、昭和初期に風呂敷包みを持った老人が警察に保護されるという話が登場します。その風呂敷には、大量の、戒名が記された位牌が入っていたというものです。家で祀られべき位牌がこのように扱われたということから、この頃から無縁化の道程が始まったとして発表されました。
発表2
「両墓制の終焉と死生観」
朽木量氏(千葉商科大学・教授)
両墓制という、現代ではほとんど観ることの出来ない希少な制度について、朽木氏が実際に現地で研究した事例の報告をまじえた発表でした。
両墓制とは、亡くなった方のご遺体を地中に埋め安置する「埋墓」、遺族らが実際に参詣する対象となる「詣り墓」の二つが存在することであり、その成立過程については多くの言及がありました。
しかし、終焉に至る過程とそこから考えられる死生観の変化についての研究事例がほとんどなかったとされています。
奈良県宇陀市菟田野上芳野「さざんか霊苑」の事例は、両墓隣接型への移行がみられますが、「埋墓」を現状維持しようとする意識がありました。
同じく奈良県の桜井市小夫での事例では、火葬普及の現代においても両墓制を堅持する実態があり、またそれに伴い村内の様々なしきたりや工夫がありました。
両墓制は、管理面や衛生面など様々な部分で手間が多いものですが、それは遺族らによるところが大きかったと言えます。
管理のしやすさ、手間の少なさが(もしくはゼロ)が良しとされている無縁化の現代社会において、貴重な事例であるとともに死生観を問う上でも重要であると感じました。
発表3
「死者との社会構想あるいは妄想」
土居浩氏(ものつくり大学・准教授)
近代に入り、国家が亡くなった国民を把握するようになり、墓地管理についても様々な構想が出されました。
その代表的な人物として、井下清(1884〜1972)があげられました。
彼は東京都の公園課長として、霊園事業を行い、宗旨混在の共葬墓地の開発を大きく進めた人物であり、様々な用途に分けて使用できる半永久的な納骨堂、「永遠の霊園」構想を提唱しました。
また、民間人の中においても、増えていく死者、無縁化により管理されずに荒廃していく墓を憂いた人物として、細野雲外が紹介されました。
彼は様々な宗旨を問わず全ての人を対象とした綜合納骨堂、「不滅の墳墓」構想を提唱し、様々な主張を展開していたとされます。
両者において共通しているのは、「いかに死者に対して効率よく居場所を与えられるか」という技術的な問題でありました。
発表4
「デジタル時代の弔い方」
瓜生大輔氏(東京大学・助教)
現代のエンディング産業にデジタル技術を応用することにより、様々なモノ・コトが変化していく中で、現代人の死生観を観察することが出来るという観点から発表されました。
好む好まざるに関わらず、これから先、宗教儀礼としての葬儀・供養の参列者へのサービスはデジタル技術が駆使され、変化していくことになります。
位牌や戒名・法号を例にすると、「存在」を示す位牌、「生き様」を示す戒名・法号、「個人情報」である命日の3点でまとめられており、非常にコンパクトでミニマムな情報媒体と言えます。
それに対して、現代デジタル社会においては写真や音声、映像、文章などに代表されるように、さまざまな個人情報が豊富にあるため、相対的にその価値が低下してしまうと考えられます。
墓を例にとっても、骨壺の物理的な管理収納能力と故人を偲び参詣の対象の二つの面がありますが、後者をデジタルが代用している例がすでにあります。
近年話題になっている、搬送式納骨堂などではディスプレイに映し出された遺影を見ながらお参りすることができます。また、墓標に彫られたQRコードを読み取ることで墓誌や故人情報を読み取ることが出来る墓地もあります。
このように、埋葬としての物理的な機能と、弔いの体験や墓誌などの情報が分けられてしまう日が遠からず来るのではないかとの示唆がありました。
デジタルデータ特有の、適切に保管していれば半永久的に保存・閲覧できること、複製が容易であること、共有がしやすいこと、場所をとらないことが大きな利点としてあげられますが、逆に第三者からの改変が可能であったり、望まない不特定多数にパーソナルな情報を共有されかねないという欠点もあります。
SNSアカウントなど、生前の情報が多く詰まったものも、大事なデジタル遺品となりうるこれからの時代、多くの課題があると言えます。
一方でそんなデジタルデータの「不老不死」性を利用し、クローンロボットに生前の情報をプログラミングし、死者を蘇らせる技術開発・先行投資も進んでいます。
故人の姿形や中身までもロボットやAIなどによって複製することが可能になる時代が来るかもしれません。倫理的観点やグリーフケアの観点からも多くの問題があると思われますが、技術進歩の波は止まることなく、現代人の死生観はさらに多様で複雑になると言えるでしょう。
Ⅱ 縁なき人々の追悼
発表5
「無縁社会の3つの方向と共同性のゆくえ」
槇村久子氏(関西大学・客員教授)
単身化社会・無縁社会が進行していくと、イエ亡き時代の個人化する死の葬送墓制は3つの方向に分かれていくことを発表されました。
まず、1つ目には従来の葬送墓制がありますが、今後はイエ単位を中心とした従来の葬送墓制は減少していくと考えられます。今まであった永代供養墓、個人・家族墓から共同墓や樹木葬墓地へと移行していきます。
2つ目には自ら準備する葬送墓制があります。1975~1990年代に出現した「都市型共同墓所」と言われる墓です。都市型共同墓所を成立させている共通の要因には、➀個人単位である、②共同祭祀がある、③死後の平等性があるものとされています。
例を挙げますと、女の碑の会の「志縁廟」、東長寺の「縁の会墓園」、もやいの会の「もやい碑」、妙光寺の「安穏廟」、祥雲寺(現在知勝院)の「樹木葬墓地」、一心寺の「骨仏」などがあります。
3つ目には行政が関与する葬送墓制があります。行政が担う無縁者の葬儀・火葬・埋葬について、三市の例を挙げられました。
➀大阪市では、無縁仏の無縁堂への納骨について、“無縁”と思われる人が増加し、無縁堂が満杯状態になってしまい、2017年に新たに「慰霊堂」という名称の無縁仏が入るお墓を新設しました。引き取られない遺骨は1年間火葬場に保管後、大阪市設南霊園に引き継がれ、毎年秋に埋葬と慰霊祭が執り行われています。また慰霊祭には、生活保護や斎場霊園の関係から市の健康福祉局や環境局の関係者、遺族の一部が参加しています。
②京都では深草墓園で、春秋彼岸に慰霊祭が執り行われています。春季は仏教で秋季はキリスト教など多様な宗教により執り行われています。
京都市深草墓園では納骨件数と無縁仏(行旅死亡人と生活保護受給者)の納骨が増加している為、今後、行政の役割が増加していくと考えられます。
③横須賀市が行っているエンディングサポート事業では、経済的困難にある一人暮らしの高齢者の死後の準備が必要になる為、市役所・葬儀社との間に葬儀、納骨、死亡届出人の確保、リビングウィルについての生前契約を結びます。生前に死後の取り決めをすることで、その人が死後のことを心配しないで、生き生きとした人生を送ってもらうことを目的に作られました。
これからは、共同性を担っていた人々の変化により、共同性の変容と消滅が進行していきます。
死者と生者の共同性を誰が取り持つかということが大切です。家族が限りなく一代に近づいていく中で、死者と生者の共同性はいつまで必要とするのか、時間軸をどこまで考えていくのか検討することが課題であると述べられました。
発表6
「近親者なき人の葬送と助葬」
山田慎也氏(国立歴史民俗博物館・准教授)
行政が葬送を行う法的根拠と実態と、民間が困窮者に対して葬儀の執行を支援する助葬について発表されました。
氏名や住所、本籍が不明の死者に対しては、行旅病人及行旅死亡人取扱法が適用され、死亡地の市町村が埋火葬しますが、近親者に引き渡されることが前提となっているので遺骨を保管することが必要となります。
身元が判明している場合は墓地、埋葬等に関する法律9条によって死亡地の市町村が埋火葬します。ただし生活保護受給者は生活保護法の助葬扶助によって、葬祭を行うものがいないときは行政が対応することになります。
このような死者の対応について9政令指定都市の調査した結果、基本となる法律は同じですが、具体的な対応に相違点があり、状況によって担当部局が変わります。火葬、遺骨の収蔵、慰霊祭、主催、儀礼等はそれぞれの都市によって対応が異なります。
次に民間から生まれた助葬事業としては、困窮者の葬儀の執行を支援する「助葬会」が1919年東京に発足し、のちに大阪や京都にも成立しました。次第に社会に認知され、1929年に高齢者や児童、障害者等の生活扶助を目的とした救護法が成立し、改正を経て戦後まもなく旧生活保護法の成立で葬祭扶助制度が設けられ、現行の法律に引き継がれました。
これにより困窮者に対する葬儀を支援する助葬という考えが公的に位置づけられました。
これから近親者のいない人が死を迎えた時、どのように埋火葬されるべきか社会全体で検討していく必要があると述べられました。
発表7
「送骨と寺院」
村上興匡氏(大正大学・教授)
後継者のいない人が、死後の供養を寺院に委託する永代供養に代わる「送骨」と、過疎地における今後の寺院の役割について発表されました。
従来、亡くなる人の九割以上は仏教式葬儀で行われてきましたが、近年は「直葬」や「家族葬」というように簡素化された儀式に変わってきました。「家」の墓も核家族化や少子高齢化の影響で個人化し、最後の自己表現や遺族のグリーフケアが強調されるようになってきています。現代は終活などで、他人に迷惑をかけないという発想から、葬儀や墓は「個」を重視し「公」の性格を弱めています。死が公的な性格を弱めた結果、仏教寺院も公的な性格が弱まりました。
さらに、地方から都市へと人口が流れ、家じまいによる檀信徒の減少で地方の寺院は存続の危機に立たされています。
これにより、寺院を取り巻く状況も変化し、各仏教宗派が過疎地寺院ついて調査報告や対策を行い、ガイドブックを刊行するなど、対策を行っています。
妙心寺派の調査では、現在約30%の寺院が兼務をしています。40年後には兼務寺院の数が逆転すると考えられています。
都市でも少子化と共に、戦後地方から移住した人が高齢化したことにより、既存の宗教意識が低くなっていると指摘されています。
多死少子化社会の対応として、地方では過疎が進み、寺院が合併する一方で、僧侶と檀信徒の双方が後継者を育てる事に力を注ぎ、都市では、伝統宗教を引き継ぐ檀信徒や都市的な布教ができる僧侶を双方で育成することが必要と報告されています。
子どもが都市部に転出していて、地元にいる親が亡くなると、故郷の墓を「墓じまい」して、都市部の集合墓に合葬されることが多いと言います。
その中で遺骨を送り、合同供養墓に納骨するシステムが増加しています。これは継承者がいない人、また継承者を期待しない人の終活の手段になったといいます。
孤独死した人が、先立った配偶者の遺骨を保持している場合もあり、行き場のない遺骨を引き取る寺院や墓地はこれから必要となると考えられます。
地方の寺院が「送骨」を受け入れることは、新潟県の妙光寺の「安穏廟」や岩手県の智勝院の樹木葬墓地のように、地元より都市部の利用者をターゲットにしていることに通じていています。「送骨」は檀信徒に代わる、過疎地寺院の経済的支援者を獲得する方策という意味も持ちつつあります。
遺骨を郵送するという事は、公序良俗に照らして議論する必要はあるが、結縁者が無く第三者に委ねるしかない人のことを考えれば、一概に禁止することは難しいのではないかと述べられました。
Ⅲ 縁なきほ方向へすすむ墓
発表8
「〈2.5人称の死者〉の今後」
鈴木岩弓氏(東北大学・総長特命教授)
人が亡くなると、生者が死者をどのように捉えているかを人称に準え、今後何が重要なのかということを発表されました。
「死者」を想いのある死者と、想いのない死者の二種に分けることができます。
1つ目は想いのある死者で、家族や友人・知人など「私」にとって特別な想いのある具体的な死者(意味ある死者)です。2つ目は想いのない死者で、ニュースに出る事故の死者や道端にある墓地に葬られている、「私」が何も想いを寄せることがない抽象的な死者(一般的死者)です。
このことから、残された生者が死者の記憶を紡ぐのは、想いのある「意味ある死者」に限られます。
しかし、一定期間法事が繰り返される中で、最終年忌にトムライアゲが行われると、その死者に対する法事は終了し、その後は個人的な「イエの先祖」として祀られることになります。
トムライアゲを契機に「想いのある死者」は固有名詞を失い「先祖」という集合名詞で呼ばれることになります。
「死者」を人称の変化に準えると「死者」が生じた場合、「想いのある死者」は<二人称の死者>となります。生物学的には必ず存在した父の曽祖父は「先祖」ではあるが<三人称の死者>と切り捨てることはできません。しかし「死者の記憶」のある<二人称の死者>とも言えません。これを<二・五人称の死者>といいます。「想いのない死者」は<三人称の死者>と分けられます。
一般に「死者の記憶は」時間経過と共に<二人称の死者>から<二・五人称の死者>そして<三人称の死者>となり最終的に忘却されます。
以上のような「死者の記憶」のメカニズムを踏まえると「死者の記憶」が、ある期間継続されていくためには<二・五人称の死者>として継承される時期を持つことが重要であると述べられました。
発表9
「新たな死の共同性」
小谷みどり氏(第一生命経済研究所・主任研究員)
高齢多死社会の現状の中で、誰が老・病・死を支えるのかという発表をされました。
どんな人でも自立できなくなると、誰かの支えが必要になります。今までは、ほとんど家族や子孫が担ってきました。高齢世帯主が増加し、男性の生涯未婚率の上昇と共に、高齢多死社会となっています。
ひとり暮らしの高齢者が増加し、65歳以上のひとり暮らしの男性で、毎日会話する人は全体の約半数しかおらず、約6人に1人は2週間で1度も会話が無く、社会から孤立しています。また、60歳以上の男性の5人に1人は周りに頼れる人がいないと回答しています。
2000年頃は、死が訪れる時、子供が若い年齢である家庭が多く見られました。今では高齢化が進み、死が訪れる時には子供も高齢化し、90代と70代の親子で共に認知症になる時代です。
以上のように、これまで老・病・死を支える家族がいることを前提とした社会のスキームが綻びを見せる中で、誰が老・病・死を支えていくのかということに対して、横須賀市の終活登録やCCRCの取り組みについて紹介されました。
今年の5月に横須賀市は、市民であれば延命処置の可否、臓器提供の意思、エンディングノートの保管場所、葬儀の生前契約や菩提寺の連絡先、墓の所在地などを登録できるシステムを構築しました。
次にCCRCの取り組みでは、自分が元気なうちに「終のすみか」に移住し、ライフプランを立て、いずれ意思を表明できなくなったとしても、最後まで在宅で過ごせるように、医師、看護師、介護士、家族やボランティアが連携して支えるシステムが整備されています。
これからは、高齢化や生涯未婚率の上昇に伴い、老・病・死を家族が支えられなくなる為、行政やCCRCのような対応が必要になります。
また、この施設の共同墓の機能について触れられ、墓は収蔵の機能の他に、「死者と生者の対話の場」、「残された人の場」という大切な場所であるということを述べられました。
発表10
「無縁墳墓改葬制度と墓地埋葬秩序の再構築」
森謙二氏(茨城キリスト教大学・名誉教授)
埋葬や改葬の定義について説明され、無縁墳墓改葬制度の現状についての問題点を踏まえ、墓地埋葬秩序の再構築が必要であると発表されました。
〈家〉の存在を前提とし、継承者がいない祖先の収骨された墳墓を「無縁」として改葬し、家の永続性の例外として、制度化されたのが無縁墳墓改葬制度です。しかし、現代の少子化により、承継者不在の墳墓が大量に発生したことに対応するため、平成11年からは、多額な費用を必要とする全国紙の新聞広告から官報公告に変更され、無縁改葬広告が簡素化されました。制定から今年の3月までの間の官報の無縁改葬広告数は、制定当初は「公共工事等」の占める割合が5割程度でしたが、次第にその割合が減少し、「墓地整備等」の占める割合が8割程度まで上昇しました。市営墓地でも墓地使用権を返却する事例が増加し、無縁改葬だけではなく、一般改葬数も増加しています。
これは「墓地の永続性」という概念が崩れ、「墓地使用の永代」という観念も失われ、墓地が死者の「終の棲家」という観念もなくなりつつあるということです。
墓地の埋葬秩序は、「埋葬の過程」とそれ以降の「死者の保護」に分けられます。今までは「死者の保護」は子孫に委ねていましたが、個人化が進む中で、子孫が先祖(死者)の安全を脅かすようになってきました。
現行の墓地埋葬法には「死者の保護」を保証する規定が無いため、死者が「終の棲家」として「埋葬」される権利を保障し、死者の尊厳性を保つためのシステム(埋葬義務)を構築していかなければならないと述べられました。
【趣旨】
散骨や樹木葬、合葬墓、一日葬、直葬といった急速に変わる墓や葬儀、また墓の無縁化、孤立死や引き取り手のない遺骨といった諸問題など、社会のあり方が変わる中で死をめぐる文化が大きく変容しています。こうした状況について、学問分野を超えて総合的に検討し、誰が故人を追悼するのかという死者と生者との関係性をとりあげ、その社会的課題を指摘するとともに、血縁にとどまらない新たな関係のあり方についても考察していきます。
【コメント】
現代人の死生観やエンディング産業、宗教儀礼としての葬送を捉えていく上で、近現代の民俗文化や私たちを取り巻く環境への考察は欠かせないものです。
特に、死生観という概念的なものは直接的な正解がないので、それぞれの時代に扱われたモノ(位牌や墓標、骨壺、デジタルコンテンツなど)や、制度、コミュニティに目を向けて、そこから得られた情報を基に考察していくということでした。
2日間に渡り、全部で10回の多岐に渡る発表と数々の講評・質疑応答の中で多くの学びと気付きがありました。
多様で複雑な現代社会の中で、死者と生者との関係性は目まぐるしく変化していくことになります。
これからの時代、我々はどのように死と向き合い、どのように死を迎えていくか、ということを考えることで、寺院としての立場を示していかねばならないと感じました。