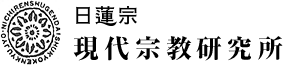貞観政要 2000年01月 発行
巻第八 論刑法第三十一
第一章
貞観元年、詔し大辟の罪を犯す者を以て、其の右趾を断たしむ。因りて侍臣に謂ひて曰く、前代、肉刑を行はざること久し。今、人の右趾を断つ。意、為すに忍びず、と。諌議王珪対へて曰く、古、肉刑を行ふは、以て罪を軽くするが為めなり。今、陛下、死を矜むこと多し。故に断趾の法を設く。一足を損じて以て其の大命を全うするは、犯す者に於て甚だ益あり。且つ之を見れば、懲誡と為すに足る、と。侍中陳叔達又曰く、古の肉刑は、死刑の外に在り。陛下は死刑の内に於て、降して断趾に従ふ。便ち是れ生を以て死に易ふるにて、寛法と為すに足る、と。〔▽六二八頁〕
第二章
貞観元年、太宗、侍臣に謂ひて曰く、死する者は再び生かす可からず。法を用ふること、須く務めて寛簡を存すべし。古人云ふ、棺を鬻ぐ者は、歳の疫あらんことを欲す。人を疾むには非ず。棺の售るるを利するが故なるのみ、と。今、諸司、一獄を覆理するに、必ず深刻を求め、其の考課を成さんことを欲す。今、何の法を作さば、平允ならしむるを得ん、と。諌議大夫王珪進んで曰く、但だ公直良善の人を選び、若し獄を断ずること允当なる者には、秩を増し金を賜はば、即ち姦偽自ら息まん、と。詔して之に従ふ。〔▽六二九-三〇頁〕
太宗又曰く、古者、獄を断ずるには、必ず三槐・九棘の官に訊ふ。今、三公・九卿は、即ち其の職なり。今より大辟の罪は、皆宰相・中書・門下の四品以上、及び尚書・九卿をして之を議せしめん。此の如くならば、冤濫を免るるに庶からん、と。是れ由り四年に至るまで、死刑を断ずること天下に二十九人のみ。幾ど刑措くを致せり。〔▽六三〇-一頁〕
第三章
貞観二年、太宗、侍臣に謂ひて曰く、比、奴、其の主の謀逆を告ぐるもの有り。此れ甚だ極めて弊法なり。特に須く禁断すべし。仮令、謀反する者有りとも、必ず独り成すを得ず。終に将に人と之を計らんとす。衆計の事は、必ず他人の之を論ずるもの有らん。豈に其の奴の告ぐるを藉らんや。今より、奴の主を告ぐる者は、皆、受くるを須ひず。尽く斬決せしめよ、と。〔▽六三二頁〕
第四章
貞観五年、張蘊古、大理丞為り。相州の人李好徳、素より風疾有り、言、妖妄に渉る。詔して其の獄を鞫せしむ。蘊古言ふ、好徳の癲病、徴有り、法当に坐すべからず、と。太宗許し将に寛宥せんとす。蘊古密に其の旨を報じ、仍りて引きて与に博戲す。治書侍御史権万紀、之を劾奏す。太宗怒り、東市に斬らしむ。〔▽六三二-三頁〕
既にして之を悔い、房玄齢に謂ひて曰く、公等、人の禄を食む、須く人の憂を憂ふべし。事、巨細と無く、咸く当に意を留むべし。今、問はざれば即ち言はず、事を見れども、都て争はずんば、何の輔弼する所ぞ。蘊古が、身、法官と為り、囚と博戲し、朕が言を漏洩するが如きは、此れ亦罪状甚だ重けれども、若し常律に拠らば、亦未だ極刑に至らじ。朕、当時盛怒し、即ち処置せしむ。公等、竟に一言無く、所司、又、覆奏せず。遂に之を即決せり。豈に是れ道理ならんや、と。因りて詔し、凡そ死刑有らば、即決せしむと雖も、皆須く五たび覆奏すべし、と。蘊古より始まるなり。〔▽六三三-四頁〕
蘊古、初め、貞観二年を以て、幽州総管府の記室より、中書省に直す。表して大宝の箴を上る。文義甚だ美にして、規誡と為す可し。其の詞に曰く、今来古往、俯して察し仰ぎて観るに、惟れ辟福を作す、君為ること実に難し。普天の下に宅り、王公の上に処る。土に任じて其の求むる所を貢し、僚を具えへて其の唱ふる所を和す。是の故に、競懼の心日に弛み、邪僻の情転た放なり。豈に知らんや、事は忽せにする所に起り、禍は無妄より生ずるを。〔▽六三五頁〕
固に以ふに、聖人、命を受け、溺を拯ひ屯を亨し、罪を己に帰し、恩を民に施す。大明、偏照無く、至公、私親無し。故に一人を以て天下を治め、天下を以て一人に奉ぜず。礼以て其の奢を禁じ、楽以て其の佚を防ぐ。左は言にして右は事、、出づるに警して入るに蹕す。四時、其の惨舒を調へ、三光、其の得失を同じくす。故に身は之が度と為り、而して声は之が律と為る。〔▽六三六頁〕
謂ふ勿れ知る無し、と。高きに居りて卑きに聴く。謂ふ勿れ何の害あらんと。小を積みて大を成す。楽は極む可からず、楽を極むれば哀を生ず。欲は縦にす可からず、欲を縦にすれば災を成す。九重を内に壮にするも、居る所は膝を容るるに過ぎず。彼の昏くして知らざるは、其の臺を揺にして其の室を瓊にす。八品を前に羅ぬるも、食ふ所は口に適ふに過ぎず。惟れ狂にして念ふ罔きは、其の糟を丘にして其の酒を池にす。〔▽六三七頁〕
内は色に荒む勿、。外は禽に荒む勿れ。得難きの貨を貴ぶ勿れ、亡国の音を聴く勿れ。内荒は人の性を伐り、外荒は人の心を蕩かす。得難き者は侈り、亡国の声は淫す。〔▽六三八頁〕
我を尊しと謂ひて賢に傲り士を侮る勿れ。我を智なりと謂ひて諌を拒ぎ己に矜る勿れ。之を聞く、夏后は饋に拠りて頻に起つと、亦魏帝は裾を牽けども止らざること有り、と。彼の反側を安んずるは、春陽秋露の如く、巍巍蕩蕩として、漢高の大度を推せ。茲の庶事を撫するは、薄きを履み深きに臨むが如く、戦戦慄慄として、周文の小心に同じくせよ。〔▽六三九頁〕
詩に云く、識らず知らず、と。書に云く、偏無く黨無し、と。彼此の胸臆に一にし、好悪を心想に損ぜよ。衆棄てて而る後に刑を加へ、衆悦びて而る後に賞を命ぜよ。其の強を弱くして其の乱を治め、其の屈を申べて其の枉を直くせよ。故に曰く、衡の如く石の如く、物を定むるに数を以てせず、物の懸る者、軽重自ら具はる。水の如く鏡の如く、物に示すに情を以てせざれ。物を鑒する者、妍蚩自ら生ず、と。〔▽六四〇-一頁〕
渾渾として濁ること勿れ、皎皎として清むこと勿れ。*もんもん(もんもん)として闇きこと勿れ、察察として明かなること勿れ。冕旒目を蔽ふと雖も、而も形無きに察せよ。*とう紘(とうこう)耳を塞ぐと雖も、而も声無きに聴け。心を湛然の域に縦にし、神を至道の精に遊ばしめよ。之を扣く者は洪繊に応じて響きを効し、之を酌む者は浅深に随ひて皆盈つ。故に曰く、天の経、地の寧、王の貞と。四時言はずして代序し、万物言ふこと無くして成を受く。豈に帝、其の力有りて、天下和平なるを知らんや。〔▽六四一-二頁〕
吾が王、乱を撥め、戡つに智力を以てす。民其の威を懼れ、未だ其の徳に懐かず。我が皇、運を撫し、扇ぐに淳風を以てす。民其の始に懐き、未だ其の終を保せず。爰に金鏡を述べ、神を窮め聖を尽くす。〔▽六四三頁〕
人を使ふに心を以てし、言に応ずるに行を以てす。治体を苞括し、詞令を抑揚す。天下を公と為せば、一人、慶有り。羅を開きて祝を起し、琴を援きて詩を命ず。一日二日、茲を念ふに茲に在り。惟だ人の招く所のままなり。天より之を祐く。争臣、詞直なり。敢て前疑を告ぐ、と。太宗、之を嘉し、帛三百段を賜ひ、仍りて授くるに大理寺丞を以てす。〔▽六四四頁〕
※『源平盛衰記』巻五
第五章
貞観五年、詔して曰く、京にある諸司、比来奏して死囚を決するに、五覆すと云ふと雖も、一日に即ち了り、都て未だ審かに思ふに暇あらず。五たび奏すとも何の益あらん。縦ひ追悔有りとも、又、及ぶ所無からん。今より後、京にある諸司、奏して死囚を決するに、宜しく二日の内に五たび覆奏すべし。下の諸州は三たび覆奏すべし、と。〔▽六四六頁〕
又、手勅して曰く、比来、有司、獄を断ずるに、多く律文に拠り、情、矜む可きに在りと雖も、而も敢て法に違はず。文を守り罪を定むるに、或は冤有らんことを恐る。今より、門下省覆し、法に拠りて合に死すべけれども、情、矜む可きに在る者有らば、宜しく状を録して奏聞すべし、と。〔▽六四六頁〕
第六章
貞観中、塩沢*ろ道(ろどう)の行軍総管、岷州の都督高甑生、李靖の節度に違ふに坐し、死を減じて辺に徙さる。時に上言する者有り、曰く、甑生は旧秦府の功臣なり。請ふ其の過を寛くせん、と。〔▽六四七頁〕
太宗曰く、甑生、李靖の節度に違ひ、又、靖、逆を謀ると誣告す。是れ藩邸の旧労、誠に忘る可からずと雖も、然れども国を理め法を守るには、事須く画一にすべし。今若し之を赦さば、便ち僥倖の路を開かん。且つ国家、義を太原に建つるや、元従及び征戦に功有る者甚だ衆し。若し甑生、免るるを獲ば、誰か覬覦せざらん。有功の人、皆、須く我が法を犯すべし。我が必ず赦さざる所以の者は、正に此が為めなり、と。〔▽六四八頁〕
第七章
貞観十一年、特進魏徴、上疏して曰く、臣聞く、書に曰く、徳を明かにし罰を慎む。惟れ刑を恤へよや、と。礼に曰く、上と為りて事へ易く、下と為りて知り易ければ、則ち刑、煩はしからず。上、疑多ければ、則ち百姓惑ふ。下、知り難ければ、則ち君長労す、と。夫れ上、事へ易ければ、下、知り易く、君長、労せず、百姓惑はず。故に君、一徳有り、臣、二心無く、上、忠厚の誠を播き、下、股肱の力を竭くす。然して後、太平の基、墜ちず、康哉の詠、斯に起る。当今、道、華戎に被り、功、宇宙に高く、思ひて服せざるは無く、遠しとして臻らざるは無し。然れども言は簡大を尚ぶも、志は明察に在り。刑賞の用、未だ尽くさざる所有り。〔▽六四九頁〕
夫れ刑賞の本は、善を勧めて悪を懲らすに在り。帝王の天下の与に画一を為す所以にして、親疎貴賎を以てして軽重を為さざる者なり。今の賞罰は、未だ必ずしも尽くは然らず。或は申屈、好悪に在り、或は軽重、喜怒に由る。喜びに遇へば、則ち其の情を法の中に矜み、怒に逢へば、則ち其の罪を事の外に求む。好む所は、則ち皮を鑽ちて其の毛羽を生じ、悪む所は、則ち垢を洗ひて其の瘢痕を求む。瘢痕、求む可ければ、則ち刑斯に濫る。毛羽、生ず可ければ、則ち賞典謬まる。刑濫るれば、則ち小人、道長じ、賞謬まれば、則ち君子、道消す。小人の悪、懲らさず、君子の善、勧めずして、而も治安にして刑措くを望むは、聞く所に非ざるなり。〔▽六五〇-一頁〕
且つ夫れ、暇豫の清談は、皆、敦く孔老を尚び、威怒の至る所は、則ち法を申韓を取る。道を直くして行ふも、三たび黜けらるること無きに非ず。人を危くして自ら安んずること、蓋し亦多し。故に道徳の旨未だ弘からず、刻薄の風已に扇ぐ。夫れ刻薄既に扇げば、則ち下、百端を生ず。人競ひて時に*おもむ(おもむ)けば、則ち憲章、一ならず。此を王度に稽ふるに、実に君道を虧く。〔▽六五一-二頁〕
昔、州犁、其の手を上下して、楚刻の法遂に差ふ。張湯、其の心を軽重して、漢朝の刑以て弊る。人臣の頗僻なるを以てすら、猶ほ能く其の欺罔を申ぶる莫し。況んや人君の高下するは、将た何を以て其の手足を措かんや。叡聖の聡明を以て、幽微として燭さざるは無し。豈に神、達せざる所有り、智、通ぜざる所有らんや。其の安んずる所に安んじて、刑を恤ふるを以て念と為さず、其の楽む所を楽みて、遂に先笑の禍を忘る。禍福相倚り、吉凶、域を同じうす。惟だ人の招く所のままなり。安んぞ思はざる可けんや。頃者、責罰稍多く、威怒微しく励し。或は供帳の贍らざるを以てし、或は営作の差違するを以てし、或は物の心に称はざるを以てし、或は人の欲に従はざるを以てす。皆、治を致すの急にする所に非ず、実に驕奢の漸する攸を恐る。是に知る、貴は驕と期せずして、驕自ら至り、富は奢と期せずして、奢自ら至るとは、徒語に非ざるなり。〔▽六五二-三頁〕
且つ我の代る所は、実に有隋に在り。隋氏の乱亡の源は、聖明の臨照する所なり。隋氏の府蔵を以て、今日の資儲に譬へ、隋氏の甲兵を以て、当今の士馬に況べ、隋氏の戸口を以て、今時の百姓に校べ、長を度り大を概るに、曾て何の等級ぞ。然れども隋氏は富強を以てして喪敗するは、之を動かせばなり。我は貧寡を以てして安寧なるは、之を静かにすればなり。之を静にすれば則ち安く、之を動かせば則ち乱るるは、人、皆、之を知る。隠れて見え難きに非ざるなり。微にして察し難きに非ざるなり。然れども平易の途を蹈むもの鮮く、覆車の轍に遵ふもの多きは、何ぞや。安にして危を思はず、治にして乱を念はず、存にして亡を慮らざるの致す所に在るなり。〔▽六五四-五頁〕
昔、隋氏の未だ乱れざれしとき、自ら謂へらく、必ず乱るる無からん、と。隋氏の未だ亡びざりしとき、自ら謂へらく、必ず亡びざらん、と。所以に甲兵屡々動き、徭役、息まず。将に戮辱を受けんとするに至りて、竟に未だ其の滅亡の由る所を悟らざるなり。哀しまざる可けんや。〔▽六五六頁〕
夫れ形の美悪を鑑みるには、必ず止水に就き、国の安危を鑑みるには、必ず亡国を取る。故に詩に曰く、殷鑒遠からず、夏后の世に在り、と。又曰く、柯を伐り柯を伐る、其の則遠からず、と。臣願はくは、当今の動静、必ず隋氏を思ひて、以て殷鑒と為さんことを。則ち存亡治乱、得て知る可し。若し能く其の危かりし所以を思はば則ち安からん。其の乱れし所以を思はば則ち治まらん。其の亡びし所以を思はば則ち存せん。存亡の在る所を知り、嗜欲を節して以て人に従ひ、遊畋の娯を省き、靡麗の作を息め、不急の務を罷め、偏聴の怒を慎み、忠厚を近づけ、便佞を遠ざけ、耳を悦ばすの邪説を杜ぎ、口に苦きの忠言を甘しとし、進み易きの人を去り、得難きの貨を賎しみ、尭舜の誹謗を採り、禹湯の己を罪するを追ひ、十家の産を惜み、百姓の心に順ひ、近く諸を身に取り、怒して以て物を待ち、労嫌して以て益を受くるを思ひ、自ら満ちて以て損を招かず、動かす有れば則ち庶類を以て和し、言を出せば而ち千里斯に応じ、上徳を前載に超え、風声を後昆に樹てん。此れ聖哲の宏規にして、帝王の盛業、能事斯に畢る。慎み守るに在るのみ。〔▽六五六-七頁〕
夫れ之を守ることは則ち易く、之を取ることは実に難し。既に能く其の難き所以を得たり。豈に其の易き所以を保つ能はざらんや。其れ或は之を保つこと固からざるは、則ち驕奢淫溢、之を動かせばなり。終を慎むこと始の如くすること、勉めざる可けんや。易に曰く、君子は、安、危を忘れず、存、亡を忘れず、治、乱を忘れず。是を以て身安くして国家を保つ可きなり、と。誠なるかな斯の言、以て深く察せざる可からざるなり。伏して惟みるに、陛下、善を欲するの志、昔時に減ぜず、過を聞きて必ず改むるは、少しく嚢日よりも虧けたり。若し能く当今の無事を以て、疇昔の恭倹を行はば、則ち善を尽くし美を尽くさん。固に得て称する無からん、と。太宗深く納用を加ふ。〔▽六五八-九頁〕
第八章
貞観十四年、戴州の刺史賈崇、所部に十悪を犯す者有るを以て、御史権万紀に劾奏せらる。太宗、侍臣に謂ひて曰く、昔、唐尭は大聖、其の子丹朱は不肖、柳下恵は大賢、其の弟盗跖は巨悪を為す。夫れ、聖賢の訓、父子兄弟の親を以てするも、尚ほ陶染変革して、悪を去り善に従はしむる能はず。今、刺史をして、化、下に被り、人咸く善道に帰せしめんこと、豈に得可けんや。若し此に縁りて皆貶降を被らしめば、或は恐らくは逓に相掩蔽して、罪人斯に失はん。諸州に十悪を犯す者有りとも、刺史は従坐するを須ひず。但だ明かに糾訪を加へ罪を科せしめば、庶はくは以て姦悪を粛清す可からん、と。〔▽六六〇頁〕
第九章
貞観十六年、太宗、大理卿孫伏伽に謂ひて曰く、夫れ甲を作る者は、其の堅からんことを欲し、人の傷つかんことを恐る。箭を作る者は、其の鋭からんことを欲し、人の傷かざらんことを恐る。何となれば則ち各々有司存し、利、職に称ふに在るが故なり。朕、常に法官に刑罰の軽重を問ふに、毎に往代よりも寛なりと称す。仍ほ獄を主るの司、利、人を殺し人を危くして自ら達し、以て声価を釣るに在らんことを恐る。今の憂ふる所は、正に此に在るのみ。深く宜しく禁止して、務めて寛平に在るべし、と。〔▽六六一-二頁〕